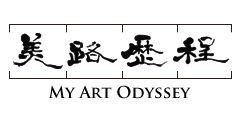

ボッティチェリの作品中、『ヴィーナスの誕生』と並んで世に知られた代表作は、『プリマヴェーラ(春)』であろう。『ヴィーナスの誕生』と同じく、ウフィッツィ美術館の所蔵になり、1477年から78年にかけて描かれた。
広く世に知られたこの名作も、一般的にシモネッタをモデルにしたとされる。だが、どの女性がシモネッタかというと、人によって指摘がバラバラなのである。
ある人は、中央のヴィーナスがシモネッタだという。その右のフローラだとも語られる。画面左、三美神の女性のうちのひとり、後ろ向きの女性がそうだとも言われる。いや、ここに現れているすべての女性が皆シモネッタなのだという人までいる。
『プリマヴェーラ』という作品自体、大変に著名な作品でありながら、寓意に満ち、作品解釈もなかなかに難しい。ただ、絵の裏付けとなる理念や趣意のうち、最も大きな、そして基本となる掴みどころは、春風を吹き込まれることによって、ニンフ(風を吹く男のすぐ左側の女性)がフローラに変じられる、この変容こそがポイントとなる。
つまりは、横に並んだ二人の女性は、実は同じ女性の「before」「after」を並べて描いたもので、それは冬から春への季節の移行の象徴であり、冬枯れの死の世界から命の息吹に溢れた春爛漫への復活、生の蘇りを意味するものなのである。
それを知れば、花冠に花模様のドレスを身に着け、花を振りまいているフローラの女性こそが、この絵の主格ということになる。
死から生への蘇りの象徴なのであれば、なおさら、シモネッタこそがその役割を担うにふさわしい。絶世の美貌を謳われた彼女は、1476年に病没している。『プリマヴェーラ』が描かれたのは、その翌年から翌々年にかけてのことなのだ。
春の訪れとともに、花の精のように蘇生したシモネッタ……。「蘇り」とは、「黄泉(よみ)帰り」=黄泉の国からの帰還を意味することにもなる。
やはりシモネッタがモデルだったとされる『ヴィーナスの誕生』のヴィーナスが、中世的な禁欲の闇を超え、海の彼方から大きなホタテ貝に乗って、白い裸身を誇らしげに輝かせながら現れたのも、蘇生という点ではまさにパラレルな構図を描く。どちらも、「黄泉帰り」の儀典のような絵なのだ。
ふたつの大作を通して見えてくるのは、ボッティチェリの画業の核に、「黄泉帰り」が打ち込まれていたということだ。シモネッタを蘇生させることと、ルネサンス的な「復興」が重なっているのである。
さて、『プリマヴェーラ』のモデル論でもう少し述べると、左端の男性については人物が特定できる。メディチ家の次男で、シモネッタの愛人だったとされるジュリアーノ・デ・メディチである。
三美神の後ろ姿の女性が、この左端の男の方向に視線を向けているので、この美神がシモネッタだと説かれる根拠にもなっている。
本来、ひとつの画面には並存するはずのない「before」「after」が並び描かれていたのと同様、この絵には、シモネッタの面影がいくつも重ねられ、並べられているのかもしれない。
そのような、あたかも絵巻物か曼荼羅のような描き方が、ボッティチェリにとって、或いはルネサンス初期の絵画においては、破綻なく可能だったのである。
死後に描かれたものではなく、生前のシモネッタの面影を伝えるボッティチェリの作品はないのだろうか――。そう思って調べてゆくと、ひとつの作品に出会った。
『美しきシモネッタ』――。東京の丸紅ギャラリーが、1969年に購入して以来、同美術館最大の宝物として、大切にしている作品である。
公式に発表されている制作年は、「推定1469年~1475年の間」とあり、これが正しければ、シモネッタ15歳から21歳にかけての姿を写していることになる。結婚してヴェスプッチ夫人となる前後から死の前年にかけて、ということだ。
日本にある唯一のボッティチェリ作品であるこの絵が、世界的にも他に類を見ない、シモネッタ生前の姿を描いたものだとしたら、貴重な上にも貴重な作品となる。丸紅ギャラリーでは、2022年12月から翌年の1月まで、『美しきシモネッタ』1品での特別企画展を催したが、この作品の貴重さを思えば、その扱いも充分に頷ける。
作品は、右手から眺めたシモネッタの横顔である。『ヴィーナスの誕生』でも見られた巻きつくような金髪。額の下方に細い弓型の線を引く眉。まっすぐに開かれた澄んだ瞳。整った鼻梁。小ぶりで可愛らしい唇。ほっそりとした三日月型の顎……。どこを見ても、無駄のない、すっきりとした美が輝いている。
真横から描く肖像画は、この時代によく見られたスタイルだが、ボッティチェリはシモネッタの死後も、このスタイルの肖像画で彼女の面影を追い続けた。
『若き女性の肖像画(シモネッタ)』(ベルリン絵画館)――。一般的には、1480年制作とされるが、時には1480年代の半ばとされることもある。左側から見た、丸紅ギャラリーのものとは逆向きの絵になるが、誰の目にも、同じ女性であることは明らかであろう。
丸紅所蔵の絵と同じく、赤い衣装に身を包んではいるが、よく見ると、同じ服ではない。また、左右反対の横顔という対比だけでなく、表情にも微妙な差がある。丸紅ギャラリーの生前の姿に比べると、こちらはいくぶん成熟が感じられ、またそれ以上に、表情が険しくなっているように思われる。
おっとりとした令嬢の印象が強かった生前の絵と異なり、この絵では、運命に対峙し、おのれの道を模索するような意志の力を感じる。うねるような金髪の髪も、こちらの絵では、より長く、複雑に絡み合い、かつ末端にはほつれも見られるなど、奔放さが窺える。
編まれていたり、締め上げられていたりする一方で、その縛り(束縛)を突き破ろうとする自由への強い意志が、乱れ髪となって表されているのではないだろうか。つまりそれは、親の言うなりにヴェスプッチ夫人となったものの、女性としての思いは、ジュリアーノ・デ・メディチに向けて否応なく惹かれていったと、そのような彼女の胸の内を表しているように思えてならないのである。
横顔ではない、顔全体がわかるシモネッタの絵をもっと見たい……。そう思って捜すと、次の作品に出会った。
『ヴィーナスとマルス』(1483頃 ロンドン・ナショナルギャラリー)――。軍神マルスは鎧を脱ぎ、下腹部を布で覆うのみで横たわり、忘我の、いささかしどけない姿をさらして、深い眠りのさなかにある。愛の女神のヴィーナスは、薄物の白い衣装を着て、睡眠中のマルスを眺めやる。二人の周囲には、マルスの剣や兜などの武具を用いて、いたずら小僧(半人半獣のサテュロス)たちが戯れている。
愛は武器に勝利するというテーマを描いているかと思われるが、このヴィーナスがシモネッタだと言われる。やさしく、穏やかな表情の美神で、ベルリン絵画館の横顔のような険しさはない。
この絵のように、単独の人物像を描いた肖像画だけではなく、『ヴィーナスの誕生』や『プリマヴェーラ』と同様、テーマ性のある絵画作品においても、シモネッタがたびたび現れる。軍神をとろけさせるほどの官能の女神を描くとなれば、おのずとシモネッタのイメージが重なってしまうのだろう。
ただ、一方では、ヴィーナスと言いマルスと言い、妙に白っぽいのが気になるのも事実だ。透き通るような白さには、血の気をなくしたような静けさがある。
マルスのモデルは、シモネッタの愛人、ジュリアーノ・デ・メディチだとされるが、ジュリアーノ本人は、1478年に暗殺されている。
この絵のマルスは、深い眠りのなかにあるが、右手の子供(サテュロス)がほら貝で耳に風を吹き込もうとしても、起き上がる気配がない。二度と起き上がらないのかもしれない。
一般的には、この絵は知り合いの結婚にあたって贈り物として描かれたと推測されているが、それにしては、幸福感の横溢する感じがない。どこか死の影を引きずっているように感じるのは私だけであろうか……。
そう考えた時、かの『プリマヴェーラ』のフローラの姿が、理念上は春爛漫の象徴であるはずが、満面に湛えてしかるべき笑みや輝きよりも、少々くたびれたような、屈折した影を抱えたように見えることが、改めて思い出されてくる。
ボッティチェリの描くシモネッタは、決して単純ではない。美しさのなかにも、時に、言い知れぬ影を抱えているのだ。
私が最も好きなシモネッタの肖像画は、フランクフルトのシュテーデル美術館が所蔵する『女性理想像(『若い女性の肖像画』、『ニンフとしてのシモネッタ』とも)』(1480年~1485年)という絵だ。
匂い立つような美しさではあるが、なまな感情を漉きこしたように、ひどく落ち着きのある、清楚な感じすら与える美神である。世間知らずの若さとは違い、世を知り、人生が必然的に伴う困難や苦しさをも知った上で、達観したような、通過した者、突き抜けた者のみの放つ、恭しい気品に溢れている。
このような美神の絵を描き続けたボッティチェリとシモネッタの関係は、実際にはどうだったのだろうか……。
実は二人は恋仲だったのだと、19世紀の英国の美術評論家ジョン・ラスキンは主張した。長らく美術界では無視されてきたボッティチェリの復権に力を尽くしたラスキンは、この画家の描いたすべての美しい女性はシモネッタがモデルだと語り、画家とモデルとの間のロマンティックな関係を示唆してやまなかった。ボッティチェリが生涯結婚しなかったのも、推定の根拠とされた。
だが、現代の研究からすると、恋仲云々は、否定的な意見が多い。とはいえ、その場限りの画家とモデルの関係を超えていることは確かだ。美の絶対的なイコンとして、画家の胸中にずっと生き続けたことは間違いなかろう。しかも、つぶさに絵を見ていくと、女性としてのシモネッタが抱えたであろう時々の思いに、寄り添おうとしている感じを受ける。よき理解者でありたいと願ったからだろうか。
先に、ボッティチェリにとってシモネッタを描くことは、蘇りの儀式なのだろうと論じた。自身の絵を通して、黄泉の国から蘇生させることで、シモネッタの美と、その胸に宿した人としての思いを、永遠にこの世に訴えたかったかに見える。
そんなことを考えているうちに、ひとつの絵を思い出した。ルネ・マグリットの『レディ・メイドの花束』(1957年 大阪中之島美術館)――。後ろ向きの山高帽の紳士が、背中に『プリマヴェーラ』のフローラを抱えている。個性の見えにくい、何の変哲もなく見える男の胸に、実は永遠の美の女神が生きている。
マグリットがボッティチェリとシモネッタのことを想起しながらこの絵を描いた訳ではなかろうが、私の目には、ボッティチェリという画家の生き方は、マグリットのこの絵のように、自身の背中に――、おのれの生の屋台骨に、シモネッタをしかと刻んで生きたように思える。
或いはまた、谷崎潤一郎の小説か昔の任侠映画のような譬えにはなってしまうが、背中に施した刺青に、観音像のような絶対美の女性像を彫り入れ、生きる限りの「同伴者」として、ともに生きたということだったろう。
ボッティチェリとシモネッタ――。ルネサンス初期のフィレンツェを舞台に繰り広げられた画家とモデルの世にも不思議な物語は、まだ完全には紐解かれぬまま、宝石のような美の証だけを残して、私たちのイマジネーションを刺激し続けるのである。