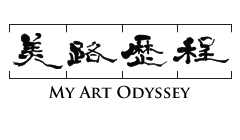

2024年秋、ウィーンの美術史美術館で、鳴り物入りの大型企画展が開かれた。「Rembrandt―Hoogstraten(レンブラント~フーグストラーテン)」――。オランダが生んだ巨匠レンブラント(1606~1669)と、その弟子で、後にウィーンに移り住んだこともあるフーグストラーテン(1627~1678 ホーホストラーテンとも)の作品をフィーチャーした特別展である。
展覧会のポスターに使われたのが、ここに紹介する『額縁の中の少女』(1641 ワルシャワ ロイヤル・キャッスル・コレクション)で、今回の出展作中、最も熱い注目を集める作品となっている。
正面から描いた少女像。しかも、ひと目見たなり忘れがたい印象を残す、とびきりの美少女だ。絵の中の女性に恋をしてしまうようなことは、男なら覚えがあるかもしれないが、この少女もそうした資格を充分に備えている。「レンブラントのモナリザ」とのたいそうなニックネームをもつのも頷ける。
だが、ふと不思議さに気づく。自画像を含め、数多くの肖像画を残したレンブラントだが、少女像は他にあったろうか――? 調べてみれば、ないわけではない、しかし、珍しい。
人生の浮沈を画布にも重ねた、円熟味を身上とするレンブラントである。いたいけな少年少女よりも、年齢とともに滲み出る人間の深い内面を描き出さんとしたかに見える画家である。老人の顔に刻まれた皺のひとつひとつに、苦渋を描出し得るほどに、人生の観照を極めた巨匠なのである。少女像の画家として、一般のイメージが薄いのもしかたあるまい。
この絵が長く、レンブラントの真作かどうか、評価が定まらなかったことも、影響しているかもしれない。真贋論争のかまびすしいレンブラント作品だが、本作に関しては、2004年から06年にかけての調査で、晴れて公に真作とされている。
この絵が描かれた1641年と言えば、オランダ絵画黄金期の代表作として知られた、『夜警』が描かれる1年前ということになる。まさに脂の乗った時期の作である。なるほど、頭巾のような大きな帽子の下の、恥じらいながらも豊かな内面を溢れさせる少女の活き活きとした表情といい、薄闇を背景に浮かぶ光の当て方、ユダヤ人女性のものとされる紅いベルベットの衣装の質感やディテールなど、すべてが充実し、レンブラントらしさに満ちている。
だが、正直驚かされるのは、そして画題が少女であること以上の摩訶不思議な気分に襲われるのは、少女の手が額縁に置かれ、指先が額からこちらにはみ出ていることである。額縁の中に収まる絵画であることを超えて、あたかも生身の肉体をもつ生きる少女が、額縁の向こうからこちらに挨拶をしてきたような、そんな生々しさに満ちている。
この仕掛けがあるからこそ、少女は、モナリザに比肩されるほどの、強烈な魅力を発することになった。見る者を虜にしてしまう、魔力を得たのである。美術史の用語で言えば、これは「トロンプルイユ(だまし絵)」の技法になるだろう。そのことを承知の上で、なお、レンブラントにトロンプルイユの絵があったことに驚かざるを得ない。めったにない少女像を描いたこと以上に、衝撃を覚える。
それだけ、絵画の可能性にかける巨匠の意欲が貪欲かつ旺盛であったことの証ではあろうが、もうひとつには、弟子のフーグストラーテンとの関係も影響しているらしい。というのも、この弟子はトロンプルイユへの関心が高く、その手の作品をいくつか残しているからだ。
ウィーンの美術史美術館での特別展では、これまで顧みられなかったそうした流れも、明らかにしてくれそうである。目からうろこの、新しい側面にスポットが当てられると、主催者のPRも意気軒高だ。少女に手招きされたような気がして、思いがウィーンに飛ぶのを如何ともしがたい。
実は、この絵は日本に来たことがある。2010年、東京富士美術館で開かれた「ポーランドの至宝 レンブラントと珠玉の王室コレクション」展の出品作として、ワルシャワから運ばれた。
悲しいかな、その折には見逃してしまった私なのである。後悔先に立たず。ああ、円安もものかは、少女に会いに、ウィーンまで出かけるべきやいないなや……。