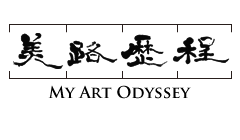

コロナが拡がって以降、海外旅行の不可能な状態が続いていたが、ようやく回復の兆しが見えてきた。美術好きには、世界のどこよりもこの地を訪れたく思う人も多い筈だ。花の都・パリ――。
パリの街は、多くの画家たちに様々な画題を提供してきた。広場や路地裏、カフェに劇場など、描かれた場所は枚挙にいとまがないが、この人ほど、街そのものを、しかもブールヴァ―ルと呼ばれる大通りの、行き交う馬車や車、人々なども含めた四辺のたたずまいを、丸ごと描いた画家はいないだろう。
エドゥアール・コルテス(1882~1969)。祖父も父もスペインの画家という血筋を継ぐが、エドゥアール自身はフランスで生まれ育った。パリの華やぎとその輝きにとりわけ敏感なのは、もとは外国の家系に生を受けたことと、関係があるかもしれない。
それにしても、数多くのパリの街を描いたものだ。都市の息吹を伝える多くの場所を、様々な季節と時間、天候のなかに描き、「パリの絵の詩人」と称されたが、私の好みから言うと、春夏よりは秋冬の、晴れよりは曇天の、雨上がりの夕方から夜にかけてが最も詩情に富んでいる。
雨上がりの道は濡れて、影がにじみ、黄昏の光が反射して波のように揺れる。道を行くのは、一頭立ての馬車、そして三頭の馬が引く、乗合馬車(オムニバス。仏語ではオムニビュス)。広小路の両側に続く街路樹は、色づき、あるいは既に葉を落とし始めているが、まだ生気を留めている。
歩道には、様々な用件を抱えて行き交う人々。その奥に続く店からは、ウィンドウ越しに、煌々とした店内の灯りが漏れている。その暖色系の光も、歩道に反射して、波うつ揺らぎの帯をつくる。
日が落ち、足元や襟筋から寒さの忍び込む頃合いであるのに、絵の世界はあたたかい。街全体が家庭そのもののような、心を和ませる安らぎとぬくもりに満ちている。
パリには何度か足を運んでいるが、さりとてコルテスの絵の風景がどの道筋か、一見にして判定できるほどの馴染みはない。だがそれでいて、かつて間違いなくそこを訪ねたことがあるような、その場に自分もたたずみ、絵の一景に身を寄せていたような、不思議な既視感がある。
通行人のなかには、しばしば母親に手を引かれた子供の姿が現れる。おそらくは、コルテス自身の幼少時の記憶なのであろう。絵を鑑賞する者は、そこに幼き自分の姿を重ねる。コルテスの絵が抱えるノスタルジアは、人々の胸にこだまのような反射を繰り返しながら、時を超えた大きな生の流れに誘い込む。
2018年に、大阪の国立国際美術館で「プーシキン美術館展」が開催された際、来館者を対象に、展示作品の風景画コンテストのアンケートをとってみたところ、モネの『白い水連』に続いて2位の座を射止めたのが、コルテスの『夜のパリ』という絵だった。「無名画家」の栄冠として新聞記事にもなった。コルテスは決して無名などではなく、記事での扱いには異議があるが、見学者の心の琴線に確実に触れるものがあったという証には違いない。
正直を言うと、コロナ前には、コルテスの絵にさほどの関心がなかった。しかし、自由な往来も人付き合いもままならぬ閉塞感にあえぐなかで、コルテスの真価に気がついた。サティのジムノペティでも聴きながらその絵に触れていると、失われることのない、そして決して失われてはならない大切なもの――都市と人間のライフといったものが、静かに、しかし朽ちることのない輝きを放つのである。
コルテスは1969年まで生きた。インタビュー嫌いで知られたが、ある時、何故現代のパリを描かないのかと問われて、1940年よりも以前の街しか描くことはないと言い切った。ナチスドイツがフランスに侵攻し、パリを占領した年である。
穏やかなコルテスの絵の奥にひそむ氷のような厳しさに触れて、身の縮む思いがした。