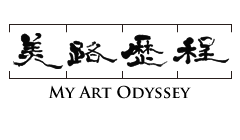

ロンドンの文教地区チェルシーを歩くと、19世紀の様々な文人墨客の旧居に出会う。カーライルの旧居は博物館になって久しいが、その少し先、テムズ河畔に面してロセッティの暮らした家がある。ともに、1901年、ロンドン留学中の夏目漱石が散策で寄った場所である。
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(1828~1882)は詩人にして画家、19世紀の英国美術界に旋風を巻き起こしたラファエル前派の創始者のひとりだった。名前が英国風でないのは、イタリア系移民の子だったからだ。
ラファエル前派は、王立アカデミーに代表されるオーソドックスな美に反旗を翻し、ルネサンスの大家であるラファエル以前への回帰を
『プロセルピナ』は1871年に着手され、少なくとも8つの版が描かれた。最も有名な1874年版はテート・ブリテンが、最後の1882年版(遺作)は、バーミンガム美術館が所蔵する。
プロセルピナ(ギリシャ名はペルセポネ)はローマ神話に登場する女神。ユピテルとケレースの娘で、春の女神にして冥府の女王という真反対の性格を有する。
その由来というと――。冥府の王プルートーがプロセルピナを誘拐し、冥府にて妻とする。母は嘆き、何とか連れ戻そうとするが、冥府でザクロの実を食べてしまったプロセルピナは、冥府の物を口にした者は冥府に住むべしとの掟から、完全に地上に戻ることが許されず、1年の半分を冥府で、残り半分を地上で暮らすことになる。地上に戻った時は春だったので、春をもたらす農耕の女神ともなった。
ロセッティの描いたプロセルピナは、食べかけのザクロの実を手にしていることから、冥府での姿と知れる。後方に射す地上の光に憧れながらも、冥府に閉じ込められた身の上を嘆くしかない。美しさの中にも深い憂いを湛えた悲劇の女神なのである。
この絵にはモデルがあった。ジェーン・モリス(1839~1914)。馬丁の娘としてオックスフォードに生まれ、極貧の中に育った。1857年、ロセッティは芝居小屋でジェーンを見かけ、その美貌に打たれ、モデルにと望んだ。
請われるままにロセッティのモデルをつとめたジェーンだったが、1859年には工芸デザイナーでアーツ・アンド・クラフツ運動の実践者、ウィリアム・モリスと結婚する。ジェーンにモリスへの愛はなかったが、貧困から抜け出る手段として嫁いだという。モリスは、フランス語、イタリア語、ピアノ演奏などをジェーンに習得させ、上流婦人の仲間入りができるよう教育を施した(ミュージカル『マイ・フェア・レディ』の元となったジョージ・バーナード・ショーの戯曲『ピグマリオン』は、モリス夫妻をモデルにしたと言われている)。
だが、愛なき結婚生活に倦んだジェーンと、彼女を慕ってやまないロセッティとの間に、やがて恋の焔が燃え盛る。1865年にはふたりは愛し合う仲となり、1871年にはグロースターシャ―(県)にあるケルムスコット・マナーの館で、ひと夏をともに過ごした。不思議なことに、モリスは妻の恋を認めていて、ひと夏のランデヴーも夫公認の所業であったと言われる。
ジェーンはロセッティのミューズとなり、詩にインスピレーションを与え、いくつもの絵画作品のモデルとなった。ロセッティは恋多き男で、ただの浮気者のように言われることもあるが、ジェーンへの思いは真剣だったようだ。
『プロセルピナ』には、籠の鳥のように囲われたジェーンを救出したいとするロセッティの願望が裏打ちされている。この絵に込めた彼の思いの深さは、8回も作品を手がけたことからも知れるだろう。
その最終版の作品を完成させた年に、ロセッティは身も心も燃え尽きるかのように果てた。まさに、命をかけた恋だったのである。
さて、漱石は美術好きで、英国留学中にラファエル前派の絵画に親しんだ。帰国して6年後に書いた『それから』という小説があるが、友人である平岡の妻・三千代を愛し、奪い取ることになる主人公・長井代助の姿は、私の目には、どこかロセッティの道ならぬ恋を引きずっているように思えてならない。