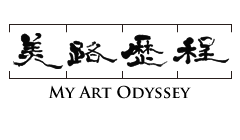
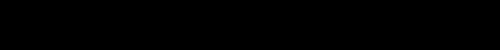
「ラファエル前派」とは、19世紀中葉の英国に於いて、ロセッティ、ハント、ミレイによって始められた新美術運動のグループである。英語では、「Pre-Raphaelite Brotherhood」――、そのまま訳せば「プレ・ラファエル兄弟社」となろうか。注意を要するのは、「Brotherhood」というくくりである。「〇〇派」ではなく、「結社」なのである。
結社における人間関係は、それが政治的、宗教的なものであれ、美術運動に関するものであれ、どうしても濃密に沸騰する。よって、その中の男女恋愛模様も、あたかも孤島に囲われた閉鎖集団のように、互いに接近してもつれ合うことになる。
それが、美を創造する画家同士である場合、愛の対象となる異性の存在がしばしば創作の泉となるだけに、個々の感情は作品と不可分に噴き上がり、美術品として世に残される。
ラファエル前派の創始者のひとり、ジョン・エヴァレット・ミレイ(1829~1896)に、『滝』(1853 デラウェア美術館)という作品がある。タイトルでは「滝」とあるが、「渓谷」「渓流」といった雰囲気の絵で、ごつごつとした岩々の間を縫って流れる早瀬の轟音が聞こえてきそうだ。
激しい水の動きとは対照的に、ひっそりと水辺の岩に腰をかけるつつましやかな女性……。ラファエル前派の支持者だった美術評論家・ジョン・ラスキンの夫人、エフィー・グレイである。
1853年、ミレイはラスキン夫妻とスコットランド旅行に出かけ、エフィーを恋するようになる。エフィーも、ミレイに好感を抱いた。
しかし、『滝』の中のエフィーは、少しも陽気な表情を見せない。憂いを沈めた面持ちである。それもその筈、エフィーは1848年に結婚した夫ラスキンとの間に、一度も性生活がなかったのだった。ミレイは愛なき夫婦関係に堪え続けねばならないエフィーに同情するあまり、恋に発展してしまった。
結局、この時のスコットランドへの旅がきっかけとなって、エフィーはラスキンとの離婚を決意する。だが当時、妻の側から離縁を申し出るのは並大抵の事ではなかった。裁判になり、エフィーは医者の診断を受け「未通」を証明してみせなければならなかった。
結局、ラスキンは性的不能者と判断され、正式に離婚が認められた。エフィーは、離婚の法的手続きが済むや、1855年にミレイと再婚している。8人の子宝に恵まれた。その後、ミレイは英国画壇を代表する大家に成長する。
ミレイがエフィーを描いた絵としては、『滝』と同じく、1853年のスコットランドの旅で描いた『ジダキリスを髪に飾ったエフィー・グレイ』(ワイトウィック・マナー所蔵)が有名である。この絵のエフィーも、目を伏せて、何かに堪えるように針仕事に打ち込んでおり、地味に徹している。ただ一点、髪にジダキリスの赤紫の花を挿しているのが、彼女の生命(いのち)の輝きとなっている。
何もない荒蕪地にたったひとつ咲いたようなその生命の花を、ミレイはじっと見つめている。モデルと画家の間に、その一点を通してあたたかい心が通い合う。控えめながら、これはやはり、愛の絵なのである。
50年ほどにも及んだミレイの長い画業の中で、最も世に知られた作品と言えば、『オフィーリア』(1851~52 テート・ブリテン)であろう。
王子ハムレットとの恋に破れ、精神を病んで、川を流れて行くオフィーリア。心清らなるが故に、宮廷内権力闘争の犠牲者とならざるを得なかった美しい乙女が、はかなき人生の最後を、川面に浮き沈みしつつ、歌を口ずんで死に向かって行くさまが、何とも印象的だ。
この作品で、悲劇のヒロインのモデルをつとめたのは、後にロセッティの妻となったエリザベス・シダルであった。
ミレイは川辺の自然の風景を先にスケッチし、その後から、エリザベスに頼んで、アトリエに設えた水槽に白い服を着たまま横たわってもらったのだという。ずぶ濡れのエリザベスは、お陰で風邪を引くことになった。
エリザベスがモデルとして初めてロセッティに会ったのは、1849年のことと伝わる。惹かれ合い、愛し合う仲となるが、ロセッティはなかなか結婚には踏みきらない。それでいて、エリザベスに他の画家のモデルをつとめぬよう諭したりもした。
一方では、他の女性との浮名も耳に入ってくる。心に不安を抱えたエリザベスは、やがて心身ともに衰弱して行く。
ロセッティは恋多き人だった。ともにラファエル前派を立ち上げた創始者メンバーのひとり、ウィリアム・ホルマン・ハントの婚約者だったモデルのアニー・ミラーを口説き落としたこともある。ハントは怒り、婚約を破棄(1859)。無論、ロセッティとも関係も悪化した。(ハントがアニーをモデルに描いた絵としては、『良心の目覚め』《1853 テート・ブリテン》が有名である。)
ロセッティが重い腰を上げるようにエリザベスと結婚したのは、ハントが婚約を破棄した翌年の1860年である。この時、エリザベスの病状はかなり進んでいたと言われる。
エリザベスとの結婚は長続きしなかった。衰弱を重ねたエリザベスは、アヘンチンキの過度の服用により、1862年に世を去ってしまう。まだ32歳の若さ――、ほとんど自殺に近い死であった。
ロセッティはさすがに心を痛め、その悔悟から、エリザベスを悼む絵を描いた。『ベアタ・ベアトリクス』(1863頃 テート・ブリテン所蔵)がそれである。
『神曲』で知られた中世イタリアの大詩人ダンテはベアトリーチェ(英国ではベアトリクス)を愛したが、彼女は病のために早世したとされる。その故事に重ねるように、ロセッティはエリザベスへのレクイエムとなる絵を完成させたのだった。
女性が目を閉じているのは、今まさに死によって天上世界へと移行しようとする、その瞬間を描いたからだという。女性像の手もとで赤い鳩が白いケシの花をくわえているのは、死の象徴であると同時に、ケシがアヘンのもとになるからだ。エリザベスがアヘンチンキの過剰摂取により死んだ事実を踏まえているのである。
ロセッティが多情であったことは疑いようもないが、エリザベスと、モリスの妻ジェーンのふたりの女性だけは、格違いとでもいうか、画家としての人生に決定的な楔を打ち込まれることとなった。
ロセッティが芝居小屋で初めてジェーンを見かけた時、実は、ラファエル前派の仲間だったエドワード・バーン=ジョーンズ(1833~98)も一緒だった。ロセッティ同様ジェーンの美貌に打たれ、モデルになるよう勧めたという。
その前年、1856年に、バーン=ジョーンズは画家を目指して勉強中だったジョージアナ・マクドナルドと婚約。1860年には結婚にこぎつけた。
子供もできて順調に見えた夫婦関係だったが、やがてバーン=ジョーンズは、モデルのマリア・ザンバコと恋に落ち、家を出る。
マリアは、裕福なギリシャ系商人の娘としてロンドンに生まれ、1860年に医師のザンバコと結婚してフランスに渡ったがうまく行かず、結婚6年にしてロンドンに戻った。やがてモデルとなり、ラファエル前派の画家たちにインスピレーションを与える美神のひとりとなる。
バーン=ジョーンズがマリアをモデルに描き、その人生にも大きな影響を与えた運命の作品がある。『キューピットとプシュケ(マリア・ザンバコ)(マリア・ザンバコの寓意的肖像)』(1870 クレメンス・セルス美術館)――。
1866年、この作品の依頼をマリアの母がバーン=ジョーンズにもちかけたことで、彼はマリアと出会い、作品を制作する過程で愛を深めたという。
だが3年後、マリアは、ロンドンのリトル・ヴェニスとして知られたリージェンツ運河で、公衆を前に派手な自殺未遂を起こす。
この事件がきっかけとなって、バーン=ジョーンズとの愛に終止符が打たれた。バーン=ジョーンズは妻のジョージアナのもとに戻るしかなかった。
マリアとの関係が破局した後も、バーン=ジョーンズは作品の上ではなおもマリアのイメージを追い続ける。もっとも、恋が破綻して以降は、誘惑者、魔女的なイメージでマリアを描くことが多くなる。
『欺かれたマーリン』(1877 レディ・リヴァー美術館)は、そのようなコンテクストでマリアが描かれた絵になる。
マーリンはアーサー王伝説に登場する魔法使いだが、魔法を教えた女性から、サンザシの木に閉じ込められてしまう。女性が頭上に蛇を抱く冠を頂いているのは、邪な意志を表す。
いびつな恋は、歓喜の高揚の渦中にある間は相手を天使とも感じさせるが、ひとたび関係が崩れると、邪悪な魔女にも変貌させる。
それでも、マリアという女性は、バーン=ジョーンズにとって、汲めども尽きない芸術的霊感の源として、永遠の輝きに満ちていたものらしい。
さてバーン=ジョーンズがマリアに熱を上げ、家を空けていた間、当然ながら、妻のジョージアナにとっては苦しい日々が続いた。
その苦しみに寄り添うように、彼女のよき友となった男性がいた。ウィリアム・モリスである。自身の妻であるジェーンの心はロセッティに向いており、離婚はしないものの、モリスが孤独を募らせていたことは間違いない。
似た立場の者同士、モリスとジョージアナは惹かれ合い、親密さを増して行く。モリスはジョージアナにバーン=ジョーンズと離婚してもらい、自分と一緒になってほしいと望んだというが、ジョージアナはそれを拒否、モリスとの間柄も精神的な友愛にとどめた。ジョージアナとモリスの親交は、モリスの死まで続いたという。
モリスは基本的には工芸デザイナーであり、アーツ・アンド・クラフツ運動を率いた人だったが、その彼に、珍しく絵画を描いた作品がある。
『王妃グウィネヴィア』(1858 テート・ブリテン)――。アーサー王の妃でありながら、円卓の騎士のランスロットに惹かれてしまう悲劇の王妃である。
モリスがジェーンと結婚したのは1859年だが、この絵は結婚の前年に完成させたことになる。モリスが残した唯一の油彩作品だと言われている。モデルはもちろん、ジェーンであった。
自身の妻となるジェーンが、やがてロセッティに惹かれて行くのを予感しているかのような内容であることに、驚かざるを得ない。絵を通して、モリスという人の抱えた孤独が透けて見えてくる気がする。
バーン=ジョーンズには、中年になった妻を描いた『ジョージアナ・バーン=ジョーンズの肖像』という作品がある(1883 個人蔵)。
この時、バーン=ジョーンズは50歳。ジョージアナは43歳になる。画面後方には、二人の間に生まれたマーガレットとフィリップの姿が見える。
波乱を乗り越えた女性の叡知が気品とともに漂うが、隈の深いその目元には、苦労の跡がありありと感じられる。描き手のバーン=ジョーンズ本人が、そのことに、誰よりも自覚的であったに違いない。
さて、ラファエル前派というのが結社名であることを冒頭に述べた。互いの人間関係が緊密で、男女の恋愛模様は互いに絡み合う。モデルは画家の愛人や妻になり、その妻は他の画家との恋に落ちる、といった具合に……。
ラファエル前派の画家たちが、神話や伝説の世界に親炙したことは前にも述べたが、その中で、格別な地位を占めたのが、アーサー王伝説だった。とりわけ円卓の騎士ランスロットが王妃グウィネヴィアと恋に落ち、それがもとで宮廷から追放される話は、芸術家たちのインスピレーションをいたく刺激した。
ラファエル前派の画家たちの恋模様を見てゆくと、この伝説の騎士に自らの恋を重ねたのではないかと勘繰りたくなってくる。
他人の妻である女性に、家庭に縛られて身動きの取れない籠の鳥のような悲劇性を感じ、おのれの手でその呪縛からの解放を勝ち取ろうとする騎士道精神が、道ならぬ恋を貫く情熱の支柱となっている。それはどこか、ヴィクトリア朝イギリスの旧弊や因習、社会を律する道徳への反抗とつながっている。
しかし、一方では自分らもまた、まぎれもないヴィクトリア朝時代の男として、女性を抑えつけようとし、忍従を強いることになる。
頭の固い封建的な亭主と解放の騎士が別々に存在するならば話は簡単なのだが、ややこしいことに、同じ一人の男の中に両者が共存しているのだ。
それは、ラファエル以前に回帰することで新しさを開こうとした彼らの絵画そのものの内包する二面性でもあった。
ヴィクトリア朝の偽善を告発し、旧弊を打破するかの如き革新性の旗を振りながら、いつしか野獣の角をもぎ取られ、社会の規範に搦めとられ、沈んで行く……。
ラファエル前派の幾多の美神たちは、このような精神的土壌に胚胎し、迷宮での地獄めぐりを重ねたのだった。憂いは沈潜し、心の底に払いようのない澱を重ねた。
キャンバスの中に、永遠の美をとどめながらも、ラファエル前派の美神たちは誰一人として、満面の笑みはおろか、明るく爽やかな微笑みを浮かべた者がいない。
颯爽と現れたかに見えた解放の騎士が、抑圧的な固陋の権力者にしかすぎないことを知ってしまった女性の嘆きのゆえである。