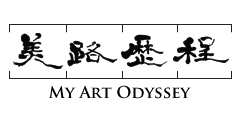
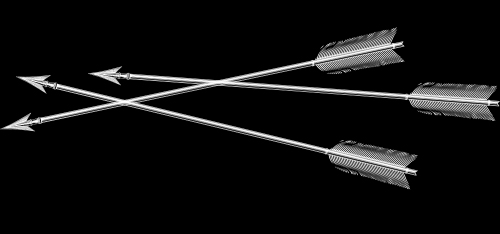
洗礼者聖ヨハネをあれほどの美男に描いたのは、ダ・ヴィンチの独壇場であったろう。だが一般の宗教絵画に現れた美男の系譜で言うと、別に大御所がいる。殉教で知られる聖セバスチャンがその人だ。
その名を耳にしてすぐにぴんと来ない人でも、数ある殉教者のなか、腰巻一丁の裸身にいくつもの矢を穿たれて佇み、かの三島由紀夫がそのポーズを真似て篠山紀信に写真を撮らせたと聞けば、あああれかとイメージが湧くのではないだろうか。
聖セバスチャン(セバスティアヌス)――。3世紀、ディオクレティヌアス帝治世下のローマで軍人だった人で、親衛隊長をつとめたという。しかし、当時は国から禁じられていたキリスト教をひそかに信仰しており、やがてこれが露見して、皇帝より死刑の命令が下され、木に括りつけられた上で多数の矢を射かけれられた。死んだと思って放置されたが、実はまだ息があったのを、イレーネという女性が介抱して、奇跡的に命をとりとめる。
本復したセバスチャンは再びディオクレティヌアス帝の前に姿を現し、キリスト教信仰の正しさを説く。帝の怒りに触れたセバスチャンは、今度は棍棒で歐打され、撲殺されてしまった……というのが、殉教のあらましである。
聖セバスチャンがまず着目されたのは、中世のペスト流行の折、多くの矢を射られながらも死ななかったという点が、病気退散の守護神として崇められたからであった(ウイルスという概念のなかった当時、病はアポロンが仕掛けた矢にあたるものと考えられた)。中世に描かれた像を見ると、美男でも何でもない。むくつけきオヤジだったりする。
それがギリシャ・ローマの復興を目指したルネサンス期に入ると、爆発的な人気を呼ぶ。殉教者でありつつ、裸身を公にさらすことのできる稀有なる存在なので、画家たちはその裸身に惹かれるように、こぞって聖セバスチャン像を描いた。その過程で、殉教者としてのオーラをより輝かしく見せるため、肉体は美化され、美男にまつりあげられた。
個々の作品を見よう。14世紀、まだゴシックから抜けきれない時代の画家、ジョヴァンニ・デル・ビオンドによる『聖セバスチャンの殉教』は、祭壇画として、無数の矢を受けた姿で描かれた(1380頃 ドゥオーモ付属美術館)。疫病の守護神としての性格が強く、その肉体は美化を免れている。そもそもこれほど矢がたくさん突き刺さっていていれば、、美しき肉体を描くどころではあるまい。
約百年の時を経て、フィレンツェの若き画家、サンドロ・ボッティチェリがこの殉教者を描いている。『聖セバスティアヌス』(1474)――。時代的には、ルネサンスにおける聖セバスチャン隆盛の走りであると見てよいだろう。
矢の数はぐっと減って、その分、男性の肉体がぐっと表現の中心に引きあげられた。健康的な美しい肉体である。胸の張り具合から浮き上がる肋骨を経て臍へと至る流れ、そして長い脚、木の切り株に載せられた左右の足首に至るまで、すっきりとした男性美に溢れ、均整のとれた心地よいリズムが脈打つ。リアリティを外れない程度の理想美がすがすがしい。
愁いを含んだ表情もいい。時代に先んじてキリスト教を信じた先駆者であり、皇帝、そして社会の理解を得られなかった孤高の人なのである。どこか、静かな諦観が漂う。そこに、美しさが宿る。
ボッティチェリが描いた男性ヌードと言えば、『ヴィーナスとマルス』(1486頃)が有名だ。しかしこれは、画面の右半分、2分の1を占めるにすぎない。よって、男性ヌードというより、男女の和合のイメージが強い(結婚の祝いに贈られたとも言われる)。
絵画全体としての円熟は進んだが、10年あまり前の作になる『聖セバスティアヌス』での男性ヌードのストレートぶりが心を打つ。20代後半、若き日のボッティチェリによる傑作と評したい。
ボッティチェリと一緒にシステナ礼拝堂の天井画を手がけたと言われるペルジーノ(ピエトロ・ヴァンウッチ)が、1495年に描いたとされる『聖セバスティアヌス』を見よう。
一見して、肌の色が白い。巻き毛の金髪と相まって、柔和で優美な印象を際立たせている。ボッティチェリの作はまだしも軍人らしい男の肉体美に溢れていたが、ペルジーノの筆ではたおやかさが強調され、とても炎天下で訓練を積んだり野戦に出陣したりする逞しき軍人には見えない。
突き刺さった矢は2本にまで減らされ、その分、輝くような白い肌の肉体がぎりぎりまで露出されている。腰巻がほんのわずかに局部を覆うだけで、いくら何でもちょっと下げすぎじゃない! と言いたくなるほどだ。上を向くのは、天上を仰いでいるわけだが、その表情は恍惚として、否応なく官能性を高めることになる。
驚くべきことに、この絵より2年前にペルジーノが描いた聖母子像に、聖セバスチャンがそっくりなポーズで加わっている。
『聖母子と洗礼者ヨハネ、聖セバスティヌアス』(1493)――。間違い探しをするように、ふたつの絵を目を皿にして注視すると、矢の当たっている位置が微妙に異なり、表情に微妙な差がありはするものの、基本的なポーズは同じである。
中央の聖母マリアと幼児イエスを挟んで、左側に立つのは聖ヨハネで、ここでは荒野に暮した行者として、色黒に描かれている。右手で幼子を指しているのは、この子こそが未来の救世主だとの暗示である。
背景から人物の並びまで、シンメトリーを尽くした構図にあって、聖ヨハネとイエスは互いに視線を交わし合い、聖母マリアは聖セバスチャンの左腕に突き刺さった矢傷を見ているようである。
それにしても、聖母子を挟んで、聖ヨハネと聖セバスチャンが守護神として左右を固めたというのは、本稿にとっては極めて刺激的だ。ダ・ヴィンチが描いた聖ヨハネが、官能的なエロスに満ちた美男であったことを先に見たが、それより20年ほど前に、聖ヨハネと聖セバスチャンが同じ土俵に並べられ、しかも対の相手となる聖セバスチャンは著しく美形化を授けられているのである。
何がしか、ダ・ヴィンチが生涯最後にたどり着いた史上最強(?!)の美しい男の絵へと至る、美の潮流を見る気にさせられるではないか!
男性殉教者の優美なる女性化という点になると、この人のこの絵も外せない。聖母子の画家と呼ばれたラファエロ・サンティの描いた『聖セバスティアヌス』(1500~1501)――。
ラファエロはペルジーノの弟子として画業を開始した。この絵を完成させた時には、まだ17歳から18歳という若さなので、この絵をペルジーノとの共作ではないかと見る向きもある。しかし、柔らかな筆致で、性差を超えたような優美さを描き出したところは、まぎれもなくラファエロの天才であろう。
この絵がいかに通常の聖セバスチャンの絵と違っているか、それは誰の目にも明らかな通り、裸身を晒していない点である。右手に矢を持っているので、かろうじてその者が誰であるかが知れる。
殉教のイメージも、肉体の男性美も、ここには無縁である。軍人にすら見えない。純朴の澄んだ精神の持ち主である若者、その清純さがおのずと静けさのなかにも光輝を放っていると、そういう絵である。
圧倒的少数派ながら、それまでに服を着た聖セバスチャンが皆無であったわけではない。ラファエロの師であったペルジーノにも、若い頃、ローマの衛兵のようなきらびやかな衣裳を着た聖セバスチャンを描いたことがある。(『パドヴァの聖アントニウスと聖セバスティアヌス』(1476~78))
これは、教会にしろ貴族にしろ、絵の発注主によっては、裸身を大胆に晒した聖セバスチャンを好まぬ向きもあったからではないかと思われる。別に男の裸など見たいわけではなく、病気退散のお守り風に、聖セバスチャンの絵を欲する人々は間違いなく存在したのである。
それは、教会の意向とも合致するものだった。聖セバスチャンを描く主流が、殉教の栄光を際立たたせようとするあまり、どんどん裸身描写をエスカレートさせて行くさまに、16世紀後半には、教会が裸体をもって聖セバスチャンを描くことを禁じたことすらあったのである。
ラファエロが裸でない聖セバスチャンを描いたのは、はたして発注主の意向だったのか、画家自身の自発的意匠によるのか、そこはわからない。
ひょっとすると――と思われるのが、ダ・ヴィンチの弟子であったジョヴァンニ・アントニオ・ポルトラッフィオが描いた『聖セバスティアヌスの姿をした若者像』(1495頃 プーシキン美術館蔵)に刺激を受けたのではないかという疑念である。
ポルトラッフィオの作品は、ダ・ヴィンチ工房で、美少年のサライをモデルに描いたのではないかと推測されている。とするならば、ダ・ヴィンチの『洗礼者聖ヨハネ』ともニアミスすることになる。
金髪の美少年で、少女のように愛くるしい微笑……。矢が添えられているから聖セバスチャンだとわかるが、タイトルの通り、その恰好をした美少年を描いたという方が正しい。殉教者を讃える宗教性は何もないと言ってよいだろう。
ラファエロはダ・ヴィンチの研究もしていたという。ならばもし、その工房にいたポルトラッフィオの手になる着衣の聖セバスチャンを見ていたなら、それに負けない、裸身でない聖セバスチャンを描こうと意欲を燃やした可能性はあるだろう。
裸身でいることが当たり前とされた聖人の姿を、裸を晒さずに描くという逆説的なハードルの高さは、若き天才画家からすれば、大いに挑みがいのあるものだったかもしれない。
教会が禁じても、聖セバスチャンの「過激化」は収まらなかった。何しろ、描く側からすれば、天下晴れて男性裸身を描くことができる数少ない素材なのである。
聖セバスチャンを描くということは、美しき男性ヌードを描くことそのものとなり、画家たちは互いに妍を競い合うようになる。そして17世紀前半、ついに聖セバスチャンの黄金期が訪れる。官能的な美の極致としての男性の裸身像が、いくつもの名花を咲かせるのである。
二コラ・レニエ(1588頃~1667)は、フランドルに生まれ、イタリアで活躍した画家である。イタリアでは、ニッコロ・レニエリと名乗った。
複数の聖セバスチャン像をものしたが、ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館が所蔵する『聖セバスティアヌス』(1625頃)はとりわけ、色男ぶりが際立つ作品である。
カラヴァッジオの追随者らしく、白く輝く裸身を闇に浮かび上がらせ、ポーズも、ただ木に括りつけられて立つという慣習と違い、腰を折った姿で、上向く眼差しが見る者に訴えかけるよう工夫されている。
白く輝くその肉体は、よく見ればなかなかに男性的なのだが、官能美に溢れ、水も滴るいい男っぷりは、そちらの趣味のない私も思わずうっとりさせられるほどだ。
ボローニャ生まれの画家、グイド・レーニ(1575~1642)も何点もの聖セバスチャン像を残しているが、そのなかでも、ジェノヴァのストラーダ・ヌオーヴォ美術館が所蔵する『聖セバスティアヌス』(1615、16頃)は、彼の作品中最も世に知られたものとなった。のみならず、純粋な意味での美術を超えて、いつしか性風俗的な社会現象としてアイコン化もした。
聖セバスチャンを描く決まり事として矢は体に突き刺さっているものの、苦悶の様子などは見られない。殉教の悲劇も、声高なところがない。そこにあるのは、永遠の若さに輝く男性ヌードの美そのものである。
三島由紀夫は『仮面の告白』のなかで、主人公の口を借りて、13歳のときに、画集の中のこの絵を見て恍惚となり、自慰行為に及んで初めて射精したと告白している。レニエの絵を語って、三島は次のように表現している。
「それが殉教図であろうことは私にも察せられた。しかしルネサンス末流の耽美的な折衷派の画家がえがいたこのセバスチャン殉教図は、むしろ異教の香りの高いものであった。何故ならこのアンティノウスにも
その白い比いない裸体は、薄暮の背景の前に置かれて輝やいていた。身自ら親衛兵として弓を引き
レニエのこの絵は、かつてオスカー・ワイルドが最も美しい絵画だとして賞讃した。ワイルドはヴィクトリア時代の英国にあって、作家・劇作家として社交界の花形であったが、男色の罪により監獄に収監され、その後は祖国を追われるようにフランスに渡って客死した。
そのような影響もあって、いつしかレニエのこの絵は、作者本人の思惑を超えて、ゲイのアイコンと化して行った。
今回、聖セバスチャンを書くにあたって、世界の美術関連の英語サイトを当たってみたのだが、驚くべきことに、この絵の解説に、三島が『仮面の告白』で書いた射精体験のエピソードが添えられているケースがいくつか見受けられた。
三島はこの絵と同様のポーズをとって、自分自身の裸身を篠山紀信に撮影させてもいるので、そのヴィジュアル的影響力も加わり、「聖セバスチャンの殉教」と不可分の神話的存在になったかのようである。
キリスト教から生まれた聖セバスチャンの殉教伝説が、ルネサンスを経て、美術界に拡散し、その果てに日本にまで伝播した。そして今や、日本から新たな神話を付加しながら、世界へと還元されて行く。
美しき男の系譜が、官能性をひたすら高めた結果、ゲイのシンボルのようになってしまったのは、ひとつの宿命であったろうか……。
やがて近代に入ると、絵画自体が大きく変化する。レニエのような手法で、美が追及されることもなくなった。レニエの聖セバスチャンは、皮肉なことに、ゲイのアイコン化することで、かろうじて芸術的命運を保ち、蘇りもしたのである。
ダ・ヴィンチが『洗礼者ヨハネ』で目指した両性具有的な全き美も、その後継者たちが聖セバスチャンを借りて追随してきた美の系譜も、ひたすら山をのぼりつめた挙句に、美そのものが、意匠のおよそ異なる羽を求めて、よその山へと移ってしまうのである。
それはそれで、美の殉教者のたどった、必至の「殉教」だったのかもしれない。
異なる潮に漕ぎ出した新たな聖セバスチャンの系譜については、次回、第45回の奥で、その流れを追ってみたいと思う。