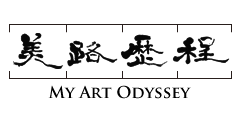

表に引き続き、タヒチに渡る前のゴーギャンについて書く。タヒチ以降の作品イメージがあまりにも顕著である分、タヒチ以前の作品については、どこか「前座」のように軽く見る傾向があるかと思うが、個人的には、この「ゴーギャン前のゴーギャン」がひどく面白い。
印象派の画風を思想がないと批判したゴーギャンが、思想的にいかなる苦悩を体験し、それを形や色に込め、その果てにタヒチへ向かうことになるのか、葛藤を重ねた心の軌跡に興味を引かれてならないのだ。
あらゆることに挑戦的であったゴーギャンの芸術活動のうち、とりあえず絵画に絞って(彼は彫刻や陶芸もよくした)、自画像、人物画、静物画、風景画と、4つのジャンルから見てゆこう。
ゴーギャンはその自意識の強さを象徴するように、自画像をよくした画家であった。タヒチに渡る前にも後にも、自画像はあるが、今回はここに挙げる自画像を措いて話を進めることなどできるはずもない。
『黄色いキリストのある自画像』(1890~91)――背景の左手には、『黄色いキリスト』(1889)の絵が、右手には『グロテスクな顔をした壺』(1889)というオブジェが配されている。
壺は、ゴーギャン自身の顔をかたどったものと言われ、時には『グロテスクな頭の形をしたゴーギャンの像』のタイトルで呼ばれる場合もある。『黄色いキリスト』の絵の方は、オリジナルの絵からすると、左右が逆に描かれている。
この自画像に描かれたゴーギャン自身の姿は、いかにも我の強そうな、言い出したら後には退かないといった、ふてぶてしいほどの気骨に満ちているが、ひと癖もふた癖もありそうな、そのひとつふたつを象徴するように『黄色いキリスト』と『グロテスクな顔をした壺』が置かれているのだ。
制作時期が近いこともあり、この3点は互いに響きあいつつ、大きな輪のなかに生きているといえそうだ。大きな意味での自画像的波長を共有している。
自分とは何者か。自分は何を思い、何を目的に生きているのか。この先、自分はどのような道を切り開いていけばよいのか……、そういった自分探しの命題に――、しかも、自分が世の中を
同時期に描かれた、もうひとつの自画像がある。『光輪のある自画像(戯画的自画像)』(1889)――。頭上に、聖人にだけ許されてきた光輪(円光)を添えている点、明らかに自分をキリストに比している。しかし、一方では、その容貌たるや、怪しげな酒場に巣食うペテン師か賭博師のようで、ワルの気配をプンプンさせている。
ここでも、ゴーギャンは露悪的なほどに自己の宿業を徹底して暴き出しつつ、荊の道を行くしかない孤独な自分を、聖者を見る眼差しで見つめている。
顕著なのは赤と黄色の色使いだ。『黄色いキリスト』から続く、黄色の氾濫である。ダジャレを言うようだが、黄色の反乱なのかもしれない。
自画像、或いは自己凝視や自己問答と結びついた大胆な黄色は、懐疑や反発、反抗といったトーンを高めながら、タヒチへと流れ込むのだ。
続いて、人物画を見よう。
『黄色いキリスト』の絵に、磔のイエスだけでなく、ブルターニュの民族衣装を着た土地の婦人たちが描かれていたことは前に見た通りだが、ゴーギャンのブルターニュ贔屓には、フランス内異域と呼ぶべきその風土に生きる人々の暮らしぶりが軸をなしていたことは疑いようもない。
民族衣装に身を包んだ現地の女性たちが登場する絵は多いが、そのなかでも、1888年に描かれた『説教のあとの幻影』は、ゴーギャンの思想形成という観点から見ても、重要な作品になるだろう。
画面手前の右端に顔半分だけを見せる司祭から、旧約聖書の『創世記』第32章に登場する天使と闘うヤコブの話を聞いた娘たちが、心のなかにその幻影を見る。
『黄色いキリスト』において、キリスト磔刑のすぐ下にブルターニュの婦人たちがいたのも、やはり、素朴な彼女らの思いの中に結ばれたキリストの受難の悲劇を、絵画として形に表したのであった。つまり、宗教上の主題が、人の心や思いを通して絵画表現に具象化するという点、ふたつの絵はそっくりなのである。
『説教のあとの幻影』では、女性らのボンネットの白と、土に塗られた赤、そして天使の羽の黄色と、色使いも印象的である。直截で、迷いがなく、力強い。
ブルターニュはレスリングでも知られた土地だが、ヤコブと天使の組み合いが、レスリングのそれに近似しているのは意識的なあしらいであろう。その形も、間違いなく、ブルターニュの婦人たちの心に浮かぶ自然な像なのである。
なお、現実と幻影の境界線のように画面の斜めに横切る木の幹には、明らかに広重らの浮世絵の影響があるだろう。格闘するヤコブと天使の姿にも、北斎漫画の力士図との近似が指摘されている。
ブルターニュでは、ゴーギャンの眼差しはしばしば子供たちにも向けられていた。これが、なかなかにいい。ゴーギャンの多様な画業のなかでも、ひとつのカテゴリーとして挙げたいほどの充実ぶりを示している。
『ブルターニュの3人の少女の輪舞』(1888)では、民族衣装に身をつつんだ少女たちが、草原で軽やかな舞を見せる。干し草の大地が黄色く塗られているのが、一連のブルターニュでのゴーギャンの色彩感覚を窺わせる。踊る少女らの脇にいる子犬も愛らしい。
だが、私個人の好みで言えば、1889年にやはりブルターニュで描かれた『海辺に立つブルターニュの少女たち』がゴーギャンの子供絵の真髄であるように思う。
パリの華やぎの対極に生きる土臭い少女たち。ブルターニュの民族衣装を身に着けてはいても、祭りの時に着る白いボンネットの晴れ着は着ていない。普段着の、つましいなりである。足も裸足だ。
私はこの絵を見ていると、東北を舞台にした往年の人気ドラマ『おしん』の少女時代を思い浮かべる。そういう、貧しい鄙の少女に寄せるゴーギャンの同情や共感が、この絵の骨をなしている。
海を背景にしている点、少女たちのこれからの運命にまで思いが至る。どのような人生行路に船出して行くのか……。
少女たちの胸の思いを受け取り、解き放つ海が、ほどなくしてゴーギャン自身を船出させることになる。タヒチで描いた黄色い肌の女たちと、このブルターニュの少女たちは、大西洋のこちらとあちらで、向き合っていると言えよう。
なお、このゴーギャンが子供を描いた作品の白眉とも言うべき『海辺に立つブルターニュの少女たち』は、嬉しいことに、日本の国立西洋美術館が所蔵している。
表現というものに極めて貪欲な芸術家であったゴーギャンは、静物画も手掛けている。
『ジャグとカップのある静物画』は、まだゴーギャンが株式仲介人の正業をもちつつ、いわば日曜画家的に絵を描いていた1880年に描かれた作品である。ジャグは陶器、カップは金属製で、ともにゴーギャンの家に古くからあった道具だという。
無機質な、いかにも「物」然とした素材を前に、ゴーギャンはじっと見つめる。その眼差しは、セザンヌ風に、光の加減や、フォルムと色彩の対比や融合による視覚の変容や発展を見据えるのではなく、「物」自体のもつ意味や人との関わりといった個性や本質をとらえようとするものである。
ジャグとカップは、いつからそこにあるのか、もとは別々のところで作られたものがいかなる運命によってともにテーブルに置かれるに至ったのか、そして家人たちのどのような思いとともに使われてきたのか……等々、「物」との対話によって哲学を深めて行く。
『美路歴程』第38回でロココの異端児・シャルダンをとりあげた際、奥で紹介した作品のなかに、銅製の給水機を描いた静物画があったが、ゴーギャンの眼差しはセザンヌよりもこのシャルダンの方にずっと近い。シャルダンも「物」に静かな眼差しを注ぎつつ、その背後にあるものについて思いを馳せる人だった。その思いが、穏やかで慈しみに溢れた世界を紡ぎだしていた。
ゴーギャンの場合、「物」への慈しみというよりは、徹底した問いかけが基本であるかと思う。より直截であり、かつ思弁的、哲学的である。
そういうゴーギャンの静物画の極致ともいえる成熟を見せた作品が、『黄色いキリスト』と同じく、1889年に描かれている。『ハムのある静物』――。実は私は、あらゆる静物画のうち、インパクトの強さから言えば、ゴーギャンのこの絵をぴか一であると思っている。
レストランやバールの店内に置かれた生ハムであろう。ワゴンの上の皿に載せられてはいるのだが、まるで宙に浮くような不思議な存在感を放つ。しかも、ハムである以上、もとは豚のもも肉になるが、まるで野獣の頭部がそのままそこにでんと置かれた感じで、表情豊かというか、今にも言葉を発してきそうな案配なのである。
「お前さんも、あっしをこれから食いなさるんだね」――そんな声が聞こえてくる。「わかるかい、あっしがここに来るまでにどういう運命をたどってきたか?」とか、「不平も言わずに生きていたものを、ある日いきなり追い立てられて、問答無用で殺されたんだ。命を奪われる苦痛を、あんた、考えたことはあるかい?」等々、ハムの饒舌はやみそうにない。
黒い鎖のチェーンは束縛の象徴であろうか。ハムに添えられたグラスの中の赤ワインは、今はハムとなったこの獣の生き血のような気がする。背景の壁のオレンジ色も、そしてハムの皿の背景の壁が、落剝したのか、汚れの染みを加えられたのか、灰色に濁っているのも、すさんだ、処刑の跡のような感を強くする。そういう描き方、描かれ方を通して、絵に向き合う者は、否応なく省察や観想の世界に引きずり込まれる。
静物画に於いても、ゴーギャンは印象派の流儀からは大きく踏み出し、独自の哲学的な境地を開いた。タヒチ前のゴーギャンは、「前座」であるどころか、充分にゴーギャンらしさを発揮しているのだ。
最後に、風景画について見て行こう。
フランスからもタヒチ島からも、遠く離れた日本ではあるが、ゴーギャンの重要な風景画の1点が、東京に存在する。
新宿の損保美術館が所蔵する『アリスカンの並木道、アルル』(1888)――。
東郷青児のコレクションでも知られるこの美術館は、印象派からポスト印象派を代表するセザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンの3巨匠の作品を1点ずつ所蔵し、宝物としている。セザンヌは『りんごとナプキン』、ゴッホは『ひまわり』と、それぞれ作家の顔ともいうべき代表的イメージが描かれた作品だが、それらに並ぶゴーギャンは、タヒチの絵ではなく、ゴーギャンがゴッホと共同生活をしていた時代に、アルルで描かれた風景画である。
秋の絵だ。赤く黄色く、木々は色づき、落ち葉で道は赤く染まる。樹の下には、いつからそこにあるのか、古代墓地の墓がある。誰ひとり、姿を見せる者はいない。
白昼の不気味なほどの静けさの中、生と死が微妙に重なり合い、歴史的時間と日々を生きる人生の時間とが奇妙に交錯する。静かな時間のくつろぎや安らぎよりも、どこか死の誘惑すらもがちらつく。赤い道は、心の中に噴き出る血なのであろうか……。
ゴッホとの共同生活は、うまく行かなかった。衝突があり、最終的にはゴッホの耳切り事件に発展してしまう。そういう危機は、この絵にも見て取れる。冬を前にした最後の輝きの中にある道は、人生行路を象徴するかのようである。落ち着いた秋のたたずまいや風情よりも、人生に行きづまった苦悩や傷心が濃く滲む。
アルルでの不安と挫折、傷心から、ゴーギャンはブルターニュへと移った。異域での安息は、次なる出発点となる。殉教者の覚悟でいよいよタヒチに赴いて以降は、まさにゴーギャンならではの芸術が爆発する。
ところで、ブルターニュを描いた風景画のうち、タヒチまで持ち込み、死ぬまで傍らに置いていたという曰くつきの1点がある。
『雪のブルターニュ村』(1894?)――。1893年、タヒチからいったんフランスに里帰りした折に描き始めた作品で、タヒチ前というわけではないが、ブルターニュを描いている点、またタヒチ再訪に際しても手放さず、現地でも折々手を加えていたという意味において、重要な作品となる。
タヒチからの一時帰国の折、ゴーギャンはタヒチで描いた作品を抱えてパリに乗り込み、そこで作品を売る計画であったが、思うように絵は売れなかった。
当時の一般的なフランス人、西洋人の好みに合うものではなかったのである。傷心のゴーギャンが向かった先は、またしてもブルターニュであった。
4月にブルターニュを訪れ、そのまま滞在して、11月に引き上げている。本格的な冬になる前にはブルターニュを離れているので、この雪景色が実景を写したものかどうかは、よくわからない。
それにしても、雪知らずの南洋の島で、雪の絵を描き続けたゴーギャンという人も面白い。タヒチまでその絵を持ち込んだのも、未完ゆえに持参したのではなく、もっと深いところでこの雪に覆われたブルターニュの絵が必要だったからではなかったろうか……?
こうして見ると、ゴーギャンには、タヒチをもくるんでしまうブルターニュが存在することに気づく。世に知られたタヒチでの傑作のひとつに、『我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか』というまことに哲学的なタイトルの作品がある。描かれた世界は、まことにタヒチならではのものだが、作品のテーマとなった問いは、タヒチ以前からずっとゴーギャンの胸中にこだましていたものだった。
タヒチ以前の作品は、「ゴーギャン前のゴーギャン」どころではなく、哲学する画家・ゴーギャンにとって、王道の果実そのものであった。ゴーギャンのブルターニュは、プレ・タヒチとしての前座に留まるようなものではなく、永遠のブルターニュとして、それ自体が不滅の価値をもつものだったのである。