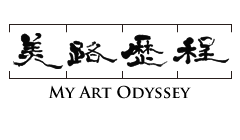

アンリ・ルソーは25点ほどの密林(ジャングル)の絵を残した。描いた作品の数で言うと26点になるが、1点は散佚しているため、現在のところ、25点の密林画があるというわけだ。初めて密林画に手を染めたのは1891年だったが、殆どの密林画の制作は、1904年頃から死の年の1910年にかけてに集中している。
ルソーは遅咲きの画家で、そもそもが正規の美術教育を受けず、税関吏として勤務を続けながら、「日曜画家」として独学で画業を発展させた。
1893年に勤めを辞め、以後は画業一本鎗となるのだが、最後の作品が密林画の集大成となる『夢』であったことに象徴されるように、画業が向かい、絵筆とともに歩む道には、鬱蒼として茂る密林=ジャングルが沿っていたのである。
まだ熱帯の密林に関心が向かう前、ごく初期(といっても画家は既に40代だが)の絵にも、後の密林への発展の芽を思わせるものがある。
『カーニヴァルの夜』(1886 フィラデルフィア美術館蔵)には枯れ木の林が描かれる。カーニヴァルはだいたいが2月になるので、まだ木々は芽を吹いていない。祝祭の装いの男女が、満月の光を浴び、海の夜光虫よろしく発光したかのように白く輝いている。男女の背後に息をひそめるのが裸木の林である。
静謐で、幻想的……。早くもルソーらしさが横溢する。熱帯のジャングルではなくても、林が描かれている点が、興味深い。カーニヴァルが終われば春が来て、これらの裸木にも青々と緑の新芽が吹く。その変貌、転生を予感させる濃密な気配が画面に脈打つ。
滴るような満月の光が、神秘の妙薬のように、転生の予兆を魔法めかせる。魔法がその術の加減を今少し強めれば、緑の林は熱帯のジャングルにさえ転じるであろう。
さて、ではルソーが最初に描いたジャングルの絵『熱帯嵐の中のトラ』(1891 ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵)を見よう。嵐の密林に身をひそめ、獲物に狙いをつけ、今にも飛びかからんとするトラである。
稲妻が光り、木や草は雨に濡れ、強風になびく。晩年の密林画に比べると、ずいぶん動的な世界を扱っている。サロン展と違い、審査を経ずに出品できるアンデパンダン展に出した際のオリジナル・タイトルは、『Surpris!(驚いた!)』であったという。
その評判たるや、子供の絵のようだ、稚拙だと、さんざんな言われようだった。が、唯一、フェリックス・ヴァロットンのみは積極的な評価を下した。
「獲物を狙っている彼のトラは必見の作品だ。これは絵画のアルファでありオメガだ(始めと終わりだ)。困惑させられもするが、大変な能力と子供のような素朴さを前に、深い確信が掲げられ、問われている」――。
しかし結局、ルソーはこの後、7年間、ジャングルの絵に手を染めなかった。次に密林が描かれたのは『生きるための闘争』(1898)に於いてであったが、やはり評判はさっぱりで、しかも、この作品は今では消失してしまっていて、精細な内容を確認することはできない。
現在確認できるルソーの密林画としては、次作は1904年に描かれた『トラに襲われる兵士』(バーンズ・コレクション蔵)になる。白い服を着た2人の黒人兵士(斥候兵)が、ジャングルでトラに襲われる様子が描かれた。背景の密林はルソーらしい濃密な幻想性を秘めているが、そこで繰り広げられている出来事としては動的で、しかも淡々と描かれてはいるものの、事の性格は残酷で酸鼻を極める。
この後、ルソーは引き続きジャングルのトラの絵を数点描いている。しかしやがては、密林での動物の主役は、ライオンに移行して行く。
実は、ルソーがジャングルの絵を「自粛」していた期間に、彼はライオンを描き始めていた。しかも、彼の描いたライオンのなかでも、とびきり素晴らしい、印象的なライオンの絵を……。
1897年の作になる『眠るジプシー女』(ニューヨーク近代美術館蔵)――。ジャングルとは対極になる、一木一草もはえぬ緑なき世界が舞台だ。
不思議な場所である。一見、砂漠のように見えながら、手前の土地と背景の山々との間に、湖のような広大な水が横たわっている。水さえなければ、月世界のようですらある。肝心なのは、いずれにせよ、パリの日常とは此岸と彼岸ほどにかけ離れた非現実の夢の世界である。その意味からすれば、ジャングルも砂漠も変わらない。
横たわるのはアフリカ出身らしきロマの女。黒い肌、オリエンタルな衣裳。そして、イタリアのマンドリン……少なくとも、ヨーロッパ、アジア、アフリカが、この絵の中に交差する。
そこに悠然とたち現れた百獣の王・ライオン。いかにも堂々とした姿である。
ルソー自身がこの絵について語った言葉がある。
「さすらいのマンドリン弾きの黒人女が疲れきって、水を入れた壺のかたわらに眠っている。ライオンが通りかかり、女の匂いを嗅ぐが、食いつこうとはしない。それは月光の影響であろう。とても詩的だ」――。
ルソーは、この絵を故郷の町・ラバルに寄贈しようとしたが、断られたという。現代の目からすれば、幻想的な上にすぐれて詩的であって、シュールレアリスムの先駆けとなったようにも見えるまぎれもない傑作だが、いかなる流派にも属さぬ独自のスタイルが、当時は理解してもらえなかったのだろう。
意味ありげに配された女やライオンは、何かを象徴しているようにも見える。さまざまな読み込みが可能になろう。
黒人女は芸術を志す者の象徴で、地球上のどこに行こうと定まる場所もなく、放浪を重ねるばかりだが、アートという自身の夢のなかでは、ライオンという王者によって守護される――と、私なりに解釈を施してはみたが、さて、的を射ているかどうか……。
何にせよ、すべては遍満とそそぐ月光のもとでの出来事である。
ジャングルとライオンが結びついたルソーの絵が――しかも晩年に集約的に描かれたその作品群のなかではいたって初期に描かれた作品が、ここ日本にある。
1904年の作になる『ライオンのいるジャングル』(ポーラ美術館)――。
遠くを窺うようなライオンが密林のなかに描かれる。画面からははみ出ているが、右手にいる獲物に狙いを定めているのだろう。1891年に描いた最初の密林画、『熱帯嵐の中のトラ』と、その点では似ている。
ルソーにとってのジャングルとは、ただ色鮮やかな植物が繁茂し、珍しい動物たちがそこに生息するというだけの場所ではなかった。匂うがごとき濃密なジャングルを舞台に、動物たちはまさに食うか食われるかの熾烈な闘いを繰り返しているのである。ルソーは、その生と死の偽りなきドラマに魅せられたように、猛獣が獲物を襲う場面を、画面中央に置いて、いくつもの作品で描いて見せた。
その代表作とも言えるのが、1905年に描かれた『飢えたライオン』(バイエラー財団蔵)である。200×301センチもの大作になる。
密林は、ルソーならではの艶を競い合うような緑の饗宴である。生命力に満ちた豊穣さの真中で、ライオンがカモシカに襲いかかる。
ライオンとカモシカの組み合わせと襲撃の形態は、パリの博物館での剥製の展示からとったという。しかし、それはあくまでスケッチなりデッサンのためであって、なぜそのような素材を密林の中心に置くのかという内的動機はまた別のところにある。現に、この絵の後、いくつものライオンによる襲撃シーンを描いて飽くことのなかったルソーなのだ。
よく見ると、この絵には、中央のライオンとカモシカだけではなく、いろいろな動物が描きこまれているのに気づく。右手にはヒョウがいて、おこぼれでもあずかろうというように、様子を窺っている。中央にはフクロウ。口にはすでに赤い肉片がくわえられている。少し左の先には、やはり赤い肉片をくわえた鳥がひそみ、さらに左に行くと、茂みに埋もれながら猿のような生き物もいる。
カモシカを襲うライオンを囲んで、様々な生物が息をひそめている。まるで、生け贄の儀式を見守る司祭たちのように……。
完全なる弱肉強食が、自然界の摂理である。聖なる残酷さとでも言おうか、都市(文明社会)の理屈など通じない、冷厳な世界なのである。それが、嘘偽りのない、生命の宇宙の真実なのだ。
ルソーがジャングルに幻視するものは、決して、ファンタジックな甘い陶酔ではない。幻想の彼岸は、夢とはいえ峻厳なリアリズムに貫かれている。
ひょっとすると、これは彼の家族の死が関係しているのかもしれない。子供たちを次々と喪い、妻も早くに世を去った。続いて娶った後妻も1903年には他界している。そういう彼自身の不幸が、一方では彼岸に紡ぐ夢を必要としながら、彼岸に於いても此岸と同じく、死の影を背負わせることになったのだろうか。
いや、そうではなくて、密林における動物たちの生と死のドラマは、植物と対比して見るべきものなのかもしれない。ルソーの植物はジャングルにあって、緑が青々とし、遍満たる生命の大海と化しているのに対し、獣たちはまさに獣であるがゆえに、食うか食われるかの闘争から逃れられない。
植物は爛々と輝きながらもどこまでも静謐で、動物たちは屠り屠られ、血を流すのである。
しかしやがて、ルソーの密林にも平安が訪れる。『眠るジプシー女』に湛えられていた神秘の安らぎが、密林にも流れる。その代表作となるのは、1907年に描かれた『蛇使いの女』だ。
ジャングルの水辺で笛を吹く女。満月の夜のシルエット像だが、裸身のようである。笛にいざなわれ身を起こし、くねらせる蛇。水鳥や樹林の枝に羽を休める鳥もいる。密林の木や草は豊かに茂り、原色の花も咲いている。それらが、あまねく降りそそぐ月光のもと、笛の音につつまれて、静寂のなかに息をひそめている。
植物と動物がここでは静かに調和し合い、動物同士の闘争もない。すべてが密林の甘い香りに
笛の音の魔法をかけられた幻想の風景は、阿片でも吸って目を閉じた、その瞼の底に残る映像はかくもあらんかと思わせる。かぐわしくも、淫靡な夢がつむぐ、現実を逃れた忘我の桃源郷なのである。
ところで、殆ど知られていないが、実はルソーは、絵画のみならず、音楽もよくした人だった。歌曲やヴァイオリン、オーケストラのための曲などを作曲した。亡くなった最初の妻を偲んでつくられた「クレマンスに捧げるワルツ」という曲もある。
となると、音楽が彼の絵に時折登場するのも、理解が及ぶ。『眠るジプシー女』がマンドリンを抱えていたのも、『蛇使いの女』が笛を吹いているのも、楽の妙音を知った人の手になる、きわめて意識的な所業だったのだ。
亡き妻を偲ぶワルツを作曲したのと、絵筆をとって緑溢れるジャングルに幻の夢をつむぐのとは、心理として通底しているはずだ。
『蛇使いの女』の絵によって、ルソーのジャングルは、密林での動物たちの血なまぐさい闘争の悪夢を離れた。やがて、夢魔は幻想の果実を熟し、芳醇の貴腐ワインのような甘美な安らぎを生み出した。
死の年に描かれた『夢』は、実人生の対極に、年を重ねはぐくみ続けてきた夢のたゆたいの、総決算となるものだった。密林画の集大成であるとともに、夢の帰着点ともなるものだった。
『夢』の画面中央奥で笛(ここでは縦笛)を吹く女は、『眠るジプシー女』から、『蛇使いの女』を経て、この絵に立ち現れている。黒い姿ながら、腰巻の原色の縞模様は、ジプシー女のオリエント風の衣装と通じ合う。
この絵での新たな要素は、ヌードで登場した白人女性であろう。しかも、パリの家にあるべきソファまで併せて移された。
裸体の女性は、ルソーの語った若き日のポーランドの恋人という言葉を信じ、青春のシンボルであると見てもよい。生ある限り、永遠に回帰すべき生命の象徴と見てもよかろう。
今、都会とジャングルの垣根さえも越えて、おしなべて命ある者は、植物も動物も人間も、この生命溢れる密林に集い、パラダイス的な温床にて生の調べをともにする。
ここまで考えが行き着いた時、私の目に、この絵がどこか
密林に夢をつむぐことで、ルソーは、東洋と西洋の壁すらも越え、はるかに時代に先駆けて、地球人としての生命の共鳴・共感を謳っていたのだろう。