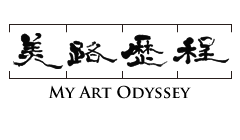

冬のヨーロッパを彩る
キリストの復活を祝う
美術史美術館は何度か訪ねたが、『謝肉祭と四旬節の争い』は、趣向の奇抜さや尽くし絵としての徹底ぶりには驚嘆しても、その意味について深く考えることがなかった。画面の左側が謝肉祭で右側が四旬節、その両者の代表が騎馬戦さながらに
本来は同時にはあり得ない、対立する時間と世相が左右に並べられ、反目し合う。画面の中央下、左側の謝肉祭代表は酒樽に跨り、頭上にはパイを載せ、槍先には子豚の丸焼きを串焼きにして刺している。彼に従うのは仮面仮装の人たち。中には楽器を持つ者もいる。
対する右側の四旬節代表は、枯れ木のように虚ろな表情の老婆で、長いしゃもじの先に2匹の魚を掲げ、密蜂の巣を頭にかぶる。修道士と修道女が老婆の乗る台車を引き、後にはカタカタ鳴らしを手にした子供たちが続く。
この木片は、四旬節の間は鳴らすことを控えた鐘に代わって、ミサの開始を告げたとも言われる。音は出しても、馥郁とした響きや、メロディーやハーモニーの華やぎには無縁というわけだ。
画面の中央部から上部を見ると、左の謝肉祭側では旅籠の前に芝居集団が繰り出し、賑わう人々からのお布施を目当てに体の不自由な物乞いたちも集まっている。右側には教会があって、祈りの後で街に出て施しをする人々がいる。棺に納めた死体を運びこむ人もいれば、肉食の代わりにと忙しく魚を捌く市場の女たちもいる。
この対決を、当時欧州中を巻き込んだカトリックとプロテスタントの争いとする見方もある。また、放恣な欲望の発散である謝肉祭を「悪魔の1週間」と難ずる声があったことから、この絵にもそうした批判があると説く人もいる。
だがブリューゲルのユニークさは、謝肉祭と四旬節、どちらの側にもつかず、おしなべて人間の愚かさを凝視するところにある。右へ倣い左に順じと、主体性を欠いた受け身の生き方しかできない人間というものを嘆いているのだ。
実は、主体性のなさが覆い尽くすこの絵の中に、唯一、主体性をもって生きる例外者がいる。しかも、その例外者こそがこの饒舌な尽くし絵の臍であり、そこから作品全体を見渡してこそ、絵に込めた作者の意図を掴むことができる。私は今回、このことに初めて気づき愕然とした。
核となるのは、画面中央、道化に案内されながら
この者を「egotist」の象徴とする英文の解説に出会った。エゴイストではない、エゴティスト。エゴイストは私利私欲に走るただの我儘だが、エゴティストはきちんと身の周りを見据えた上で、明確な意志を持ち、自身の生き方を貫く。必ずしも自己に有利に働こうとするのではなく、他者のため、公のためにおのれを貫徹する道もあり得る。ブリューゲルは2つの時の争いを戯画的に描きつつ、流されず浮足立たない、確固たる生き方を提示してみせたのだった。
と、ここまで読み込めた時、再び愕然とする思いが襲った。これは現在のコロナ禍に於けるゴタゴタを、時の彼方から見据えたような作品ではないのか。対立や非寛容の諍いが世を覆い、地に足のついた生を見失っているかに見える21世紀の人類への警鐘なのではないか――?
550年もの時を超え、ブリューゲルの絵が説く真実。不滅の洞察力の鋭さ、深さに、ただ圧倒されるばかりだ。