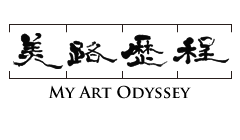

1559年前後、ブリューゲルは立て続けに「尽くし絵」を製作した。ひとつの町を鳥の目のように俯瞰しながら、テーマに即したあらゆる人々の営みを悉く描き込む。
1559年に描かれたのが『謝肉祭と四旬節の争い』と『ネーデルラントの諺』――。翌1560年に描かれたのが『子供の遊戯』――。ほぼ同時期に描かれたこれらの尽くし絵は、ブリューゲルの初期を代表する傑作であり、その実、ブリューゲルはこの3部作によって、画家としての個性を確立した。今日私たちが知るブリューゲルらしさは、まさにこれらの尽くし絵3部作から始まったのである。
その意味では、「ブリューゲル開眼」となった3部作が、ただ一様に人々の営みを鳥瞰図のなかに描き尽くすという手法上の試みだけでなく、作品が抱える精神性から言っても、何がしかの共通意識、創造を支えた理念があるはずである。
まずは、『ネーデルラントの諺』から見て行こう。タイトルから明らかなように、諺尽くしの絵――。110を超す諺で埋め尽くされているという。
「猫の首に鈴をつける」という、イソップ童話を淵源とする日本人にも馴染みのある諺が描かれているのは、猫好きならずとも嬉しいところ。また、「自分の金を水に捨てる」男が描かれているのも、「金をドブに捨てる」という譬えが一般化している私たちからひどく近い。
しかし、そういう一見して意味を悟ることができるような、或いは現代日本でもそのまま通じるような諺はむしろ例外的で、やはり解説があってこそ、ひとつひとつの具象イメージのからくりも理解可能になる。
ここで、逐一、諺とイメージとの対比を述べる余裕はないが、画家の名と「ネーデルラントの諺」で引けば、日本語のウィキペディアでも80の諺が、英語で「Bruegel」と「Netherlandish Proverbs」または「Dutch Proverbs」などと引けば、英語版ウィキでは126もの諺が、絵の部分イメージとともに引用、紹介されている。
画面中央の下方、赤いドレスの妙齢の女性が後ろ姿の初老の男性に青い外套を着せているが、この男女は「夫に青い外套を着せる」との諺を描いたもので、要はこの女性が夫を騙し、不貞を働いていることを意味するのだという(青色には欺瞞、裏切りの寓意がある)。女性の出で立ち、表情などが印象的であるからであろうか、この絵はもともと『青い外套』というタイトルで呼ばれていた。
こういう諺の絵解きは、無論、それとして興味深いが、ただその面白さだけでこの絵に接していると、ブリューゲルの本質を見逃すことにもなりかねない。この絵は単なる諺紹介のイラストではないのだ。
ブリューゲルが諺尽くしの絵に込めた意図は何であったのか――、そこが見えないと、この絵の理解は面白パズルの域を脱せられない。
先にこの絵のオリジナル・タイトルについて述べたが、実は『ネーデルラントの諺』という一般化したタイトルの他に、いくつかの別称があり、そちらの方にこの絵に向き合う鍵がある気がする。
別称のひとつ、英語タイトルにはなるが、『The topsy turvy world』というものがある。「topsy turvy」は、「逆さまの」とか「はちゃめちゃな」といった意味。つまりは、「逆さまな世界」とか「はちゃめちゃワールド」といったタイトルになる。
ネーデルラント(オランダ)には、「逆さまな世界」という諺があり、「あるべき姿と反対のことが起きている」、つまりは秩序の反転を意味するというが、ずばりそのイメージがこの絵の中に描きこまれている。
画面左端の家の2階の窓から身を乗り出した赤い服の男の下方に、逆さまに吊るされた青い地球儀がそれだ。ご丁寧にも、男は下半身を剝き出しにして、尻から糞を垂れている。これは「世界の上に糞をする」との諺を踏まえていて、「世の中のすべてを軽蔑している」との意味である。
まことに世界は逆さまの糞まみれ、偽善がのさばり、善と悪はしばしば入れ替わって、カオスの体をなす。諺を借りて世界を描くブリューゲルの眼差しは、相当にシニカルだと言わざるを得ない。
実はこの絵には、4つの地球儀が描かれている。
逆さに吊るされた地球儀に加え、もうひとつは、赤い服を着た不貞の妻の視線の先に立つ、赤と白のマントをまとい、役者か何かのような出で立ちで立つ色男の左手の指先に、地球儀が乗っている。「彼は親指の上で世界を回している」との諺を踏まえ、「人を意のままに操る」の意味があるという。
いまひとつは、この色男の左足の先、そして右手の指さす先に、半透明の地球儀が横倒しにされ、その中に上半身を突っ込む男が描かれている。これは、「世に出たければ身をかがまねばならない」との諺で、要は、「成功を望むなら嫌なことにも甘んぜよ」との意味になる。
ためになる教訓とも聞こえるが、半身を突っ込んだ球体が半透明で、丸見えであるところからすると、この男の自己犠牲も純な心からではなく、見返りを期待してやまない生臭い欲望が透けて見えるということなのだろう。目を剝いた男の表情も、野心満々、いかにも欲の皮が突っ張った感じである。
そして最後に、先の色男の上方、老婆がすがるキリスト風の宗教者然とした髯男が、椅子に腰かけた膝の上に、青い地球儀を抱えている。これは、「神に亜麻の髯をつける」という諺で、「信仰心を隠れ蓑に人を騙す」ことを表すという。
都合4つの地球儀が、この絵の中の適所に配され、糸で結ぶように絵の抱える世界観を縫いあげる。それは、糞をかけられる逆さまの地球儀に端的に現れていたように、「topsy turvy」な歪んだ世界である。ハチャメチャで、しっちゃかめっちゃかな狂った世の中である。
個々の諺の絵解きだけに心を奪われていると見えて来にくい、ブリューゲルの真意がまさにそこにある。あらゆる諺を視覚化しつつ、ブリューゲルは世界の歪みを徹底して描き尽くしたのである。
1560年に描かれた『子供の遊戯』を見よう。これも、尽くし絵である。総勢250人ほどの子供たちが、80種類を超す遊戯に興じている。ひとつの町が子供たちに占領されてしまったようだ。
「輪転がし」や「馬跳び」、「竹馬」など、日本人にも子供の頃の実体験として記憶が残る遊びもあるにはあるが、「洗礼ごっこ」であるとか、「結婚式ごっこ」など、大人の真似事のような、説明を聞いてようやく納得できる類いのものもある。
『ネーデルラントの諺』のなかにもいくつか例があったが、ここでもスカトロジーが強烈なアクセントを放つ。
画面中央下方、まさしく主役級の一等地を与えられて、円盤形にとぐろを巻く「それ」に棒を突っ込み、ぐるぐる引っ搔き回す女児がいる。「それ」の正体はおそらくは道端に落ちた牛糞なのであろうが、そのようなものさえ遊戯の対象としてしまう、貪欲というか、留まるところを知らない旺盛な子供の遊び心なのである。彼女はその後、その棒をどこに向けるのだろうか……?
ブリューゲルの『子供の遊戯』を見るたびに、私は日本のある古歌を思い出す。
「遊びをせんとや生まれけん……ただ狂え」――。12世紀末にまとめられた『梁塵秘抄』に収められた歌である。すさまじいばかりの遊びのエネルギーを顧みて、「ただ狂え」と、『梁塵秘抄』は童心の解放、爆発を謳いあげたが、ブリューゲルのこの絵でも、あたかも町全体が満開の花に埋め尽くされたように、フル稼働した童心が跳梁跋扈して憚らない。
優雅な花の満開というよりは、いささか過剰すぎるほどの力を漲らせた狂い咲きの感もある。童心と聞いて、ほのぼのとした慈愛と微笑をもって接するには、画面に溢れ返る子供の遊戯は圧倒的で、迷走、暴走しかねないほどに、爆発的なエネルギーに満ちている。
ここで注意すべきは、絵画の中央奥、広場に面してでんと構える建物が、市庁舎か町役場といった官庁と思しき建物だということである。つまりは、町の秩序を司る場所なのである。今やその建物から広場、奥の道まで、悉く一帯が子供の遊戯に占領されてしまい、あたかも幕末の「ええじゃないか」のような騒動、騒乱に襲われているのだ。
ここまで理解すると、やはりこの絵も、ブリューゲル一流の「topsy turvy」な絵画であることがわかる。大人たち――しかつめらしい顔をした町の代表者や役人たちが政務の牙城とする場所が、子供たちの反乱に呑みこまれてしまったのである。
大人と子供が逆転した、逆さまの白昼夢こそが、『子供の遊戯』の確信的テーマなのである。
最後に、再び『謝肉祭と四旬節の争い』の絵に戻ろう。尽くし絵3部作の1点である。
この夥しい人数の人々が、時節の精神と宗教的情熱によって対立し、それぞれに狂奔するなか、唯一、画面中央のエゴティストの夫婦者だけが、世の趨勢に逆らい、昼と夜を逆転させながら、真に地に足のついた生を貫く……。
『ネーデルラントの諺』、『子供の遊戯』と、2つの尽くし絵の精神を探ってきた上で見つめ直すと、ますます、この絵のもつ反俗精神に衝撃を覚える。
2つの時節――或いはそれらが象徴するカソリックとプロテスタントの対立、諍いのどちらかの側につくのではなく、両者ともに突き放して、世の習い、流行りに浮かれ騒ぐ愚かさを喝破して見せたのである。ブリューゲルの抱えていた独立不羈の精神の逞しさ、尊さに、脱帽させられる思いがする。
時節の病に染まらず、おのれの生を貫くエゴティストの生き方に思いを馳せていた私の胸に、ある俳句が浮んできた。
「
ブリューゲルが描いた、謝肉祭と四旬節の時節を貫いて生きるエゴティストの姿は、虚子の俳句がとらえ、川端がさらにそこから発想を飛翔させたような、生半可な人生観照からは決して導き出されない、人生の奥義に至る真実への窓口となるものだった。
白昼に燈火をともして道を行くエゴティストは、やはり「topsy turvy」な、逆さまの世界の住人だったが、逆さまのなかにこそ真実がひそむことを、身をもって示していたのである。
ブリューゲルは後年、農民の暮らしや田園をテーマに多くの絵を描いたので、しばしば農民画家のように言われ、自然に生きる素朴な暮らしぶりを讃えてやまなかったように語られがちだが、私はいささか違う視点をもっている。
ブリューゲルらしさが初めて発揮された絵画創造の出発点において、逆さま世界3部作を描いて見せたことの意味は実に大きい。ブリューゲルらしさとは、まずはこの逆さま覗きを土台として積み上げられて行くのである。
尽くし絵3部作で逆さま世界を描いてから約10年後、ブリューゲルは早すぎる死を迎えた。まだ40代半ばだったという。墓碑銘には、ラテン語で「人生の半ばに死す」と刻まれた。
不思議な言い伝えがある。ブリューゲルは最期の時、逆立ちをして、倒立するブリュッセルの町を望み、「よい眺めだ」と口にして、死んだというのである。
死ぬ間際の人間が、はたして倒立などできるのか、懐疑的にならざるを得ない部分はあるが、それが幻想の生んだ伝説だったにしても、ブリューゲルの生涯をくくるのに、「逆さま」でまとめたかった人々の思いはわかる気がする。
物事を、世界を、逆さに見ることによってようやく近づくことのできる真実があることを、ブリューゲルは熟知していた。
その人がもし本当に、人生の最後に、この世を逆さに見て、満ち足りた思いを得たとしたなら、倒立する世界像の先に、ようやくにして真実の光を手にしたものだったのかもしれない。