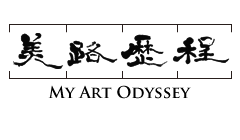

うっかりスープ皿を割ってしまった。食器洗いの途中で手が滑り、床に落としたのだ。高価なものでもなく、日用品ではあったが、20年近く使い慣れたものだったので、ひどく哀しい気がした。哀しみが自分の予想以上に強いので、さてはこれもコロナ鬱が影響しているかもしれないと思った。ささいなことでも、慣れ親しんだ世界の崩壊と喪失が、いつも以上にこたえるのである。
うち萎れた気分が続くなか、この人の静物画を見ることで落着きを得た。ジャン・シメオン・シャルダン(1699〜1779)――。
18世紀フランスの、貴族社会の華やぎが一世風靡したロココの時代に、素朴な静物画に独自の境地を切り開いた画家である。
シャルダンの静物画の特徴は、画面に満ちる静謐さと、対象となる物への慈しみの眼差しにある。生きとし生けるものと言うと、いささか仏教的な響きにも聞こえるが、動物や草花、虫に至るまで、すべての命あるものと同様の眼差しで、容器や道具に愛情が注がれている。
パリのルーブルにも傑作は多いが、私が個人的に最も気に入っているのが、アメリカ、ワシントンDCにあるフィリップス・コレクション所蔵の『プラムを盛った鉢と桃』(1728年頃)だ。中国渡りの磁器と思しき水差し、多くのプラムを盛った陶器の鉢、そして水差しの横に1個だけ置かれた桃などが、褐色に塗り込まれた背景の手前に光を受けて浮かびあがる。
静かな絵だ。さりげない画題ながら、いつまで見ていても飽きない。心が穏やかになごんで、調和の世界にいざなわれる。絵がとらえるのは眼前に繰り広げられる今の像であろうが、描写の奥に深い時間の流れがたゆたう気がする。プラムや桃だけでなく、水差しや鉢にまで、命あるものの輝きが宿る。それはあたかも、人生の同伴者に注ぐ、あたたかくもやさしい眼差しなのである……。
静物画の歴史は、実はそれほど古くはない。絵画のジャンルとして定着したのは、17世紀のオランダであると言われる。
花瓶に挿した色鮮やかな花――その画面にはしばしば蝶や虫が描きこまれ、枯れて萎れ色褪せた花の残滓も添えられた。極端な場合、頭蓋骨までが登場した。ヴァニタスという、生あるもの必ず死を迎えるという宗教的な寓意であった。
一方では、魚市場に並べられた大小様々な魚類や甲殻類を、その生臭そうな肌のぬめりまで生き生きとリアリズムの極致で描写した。これなどは、スピノザによるレンズの発見と無関係ではないだろう。
そういうオランダ静物画の影響を、シャルダンも受けている。この絵の場合も、画面左下に、褪色したプラムや種が描きこまれたのは、伝統に従ったのである。花や蝶が描かれた水差しを選んだのも、同じ趣旨であろう。
だが、絵が湛える静謐でふくよかな味わいは、シャルダン独自の世界である。オランダ絵画のリアリズム一辺倒や寓意を突き抜けて、暮らしのなかにしみじみとした美を見出している。その美の発見は、ささやかであっても、時代を超えた真摯な輝きに包まれた。
その後の静物画の歴史を見ると、19世紀後半に活躍したセザンヌという革命児にノックダウンを食らったようになる。リンゴを並べて、光の明暗や周囲のマテリアルとの相関性などから、視覚の歪みを描き出し、キュビズムへの足がかりを築いた。対象を突き放し、前後左右、あらゆる角度から徹底して見ることを至上命題としたセザンヌにとって、物はオブジェであって、研究室の科学者のような眼差しには、人生の同伴者であるとか、愛の対象とかいった要素はない。
その後の静物画は、あたかもセザンヌの強烈なパンチに昏倒してしまったごとくに、その影響から免れない。だが、オランダ絵画とセザンヌの間に、シャルダンという、もう一人の天才がいたことを忘れてはならない。当たり前の暮らしが脅かされる時、人生の同伴としての静物を命あるもののように慈しみ、やさしい眼差しで見つめたシャルダンのしなやかな感性は、宝のように貴重である。
近代絵画の雄としてのセザンヌの天才を認めつつも、私が今、それ以前のシャルダンの静物画に惹かれてならないのは、当たり前の暮らしと、そこに宿る美の価値に気づかされた、コロナ時代の逆説的な収穫なのかもしれない。