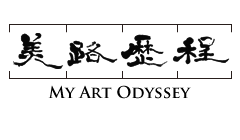

華美に満ちたロココの時代にあって、奢侈な風俗に流れず、素朴な静物画を描き続けた異端児、ジャン・シメオン・シャルダン(1699~1779)――。
物を慈しみ、愛を以て見つめるその画風は、時に驚くほど現代的なトーンを帯びることがある。
『銅製の給水器』(1733 ルーブル美術館蔵)――。でんと画面中央に置かれた無機質の給水器が、一見、素っ気ないくらいに直截に、物としての揺るぎない絶対性をもって、いかにもオブジェ然として描かれているのは、何か時を超えた奇跡を見るような思いに駆られる。
静物画というと、花瓶であったり、果物であったり、色も形もそれなりに「華」のあるものが対象となるように考えられがちだが、そういう月並みな常識を見事に粉砕してくれる。
私はかつてルーブル美術館でシャルダンのこの絵に出会った時、比較的小さな絵(縦28・5センチ、横23センチ)でもあることから、まずは色気のないシンプルな絵だなというほどの印象で素通りしてしまい、いくつか他の絵を見た後に、妙に心に引っかかって、その場に戻ってじっくり鑑賞したことを覚えている。
オブジェとしての即物的なとらえ方が、20世紀美術を先取りしたようにも思え、それでいて、近代美術にありがちな主張のあざとさからは遠い。あくまでも穏やかな、静謐な世界に息をしているのだ。
我ここにありと、日常性のなか、物は惜しみなくその姿を見せてくれるが、卑近さを楯に周囲から屹立して、反発の壁の内に立て籠もることはない。
ひしゃくや洗い桶、水壺など、給水器とともに働く同類たちが勢ぞろいするように並ぶのは、この絵が奏でる調和の調べの象徴でもあろう。
シャルダンの静物画は、ロココの時代にあって、貴族階級からも愛されたというが、こうした調和があればこそだったろう。ロココの異端児ではあっても、彼は誰からも愛されない時代の孤児ではなかった。
いや、その実、シャルダンのもっている独自性は、決して彼個人で完結するものではなく、時代や国を超えて、響き合うひろがりをもつ。
シャルダンの静物画をつぶさに見て行くと、この人の物を見つめる眼差しは、柳宗悦が提唱した民芸運動の美意識に近いのではないかと思うようになった。民芸の作り手は基本的に
シャルダンもしかり。民芸的な美を扱いつつ、彼自身はアルチザンではなく、芸術家の魂をもって描き、生きたのだった。
2019年、坂本繁二郎の没後50年の回顧展を見に行った時に、牛や馬の絵で有名なこの画家が、いくつもの静物画を描いていることを知った。そのなかの『モートル図』(1956)という作品を見た時にも、私はシャルダンの『銅製の給水器』を思い出した。
「モートル」とはモーターのことで、安川電機から制作依頼を受けて描いたものだったという。現代生活で使われる電機製品を、明るい家庭、乃至は作業現場の風景として広告風に描くことはいくらでも可能だったろうが、さすがに坂本はそうしたありきたりの愚には陥らず、モーターをでんと置き、単独の主役で描いて見せたのだった。
無機質なオブジェのマテリアルに注がれる真摯な眼差しが、物の絶対性を前に頭を垂れるような、謙虚な心映えを見せている。
シャルダン精神が飛び火したように思った。
シャルダンの『プラムを盛った鉢と桃』について書いた本章の表のなかで、私はこの画家の物に向き合う姿勢を語って、生きとし生けるもの、すべての命あるものと同様の眼差しで、容器や道具に愛情が注がれていると書いた。
逆に言うと、物を愛と慈しみの眼差しで見ることのできた画家は、
とりわけ、下働きをする女性(女中)たちの仕事中の絵を多く描いた。そういうシャルダンの労働者階級の女性を描いた絵のなかに、静物と人物をつなぐ、恰好の作品がある。
『給水器から水を受ける女』(『給水器の前の女』とも。1732~40 バーンズ・コレクション蔵)――。
一見して明らかなように、『銅製の給水器』で単独の主役をつとめた給水器が、ここでは実際の労働現場で女性によって使われる様子が描かれている。彼女が手にしている水壺やその下に置かれた水桶も、給水器とともに静物画で描かれていたものだ。
静物画では背景をモノトーンの壁だけでまとめていたが、暮らしのなかの労働の場を舞台とするこちらの絵では、女性との対比で、給水器の大きさも使用意図もよくわかる。金盥や洗い桶、箒、薪など、給水器の仲間たちも、より多くの物、道具が加えられ、巧みにコンポジットされて、女中の仕事ぶりを多角的に描き出している。
女性の年恰好は正確には不明だが、年寄りではなく、比較的若い女性のようだ。給水器の蛇口に添えられた彼女の右手はごつごつとして、その生の実相を窺わせる。腰を100度ほどにも鋭角的に折る姿勢は、働く農民を描いた19世紀の画家・ミレーにも影響を与えたとも言われる(『落穂拾い』など)。
私が注目したいのは、右側の奥の部屋でも、やはり下働きの女性が箒をもって仕事をしており、しかもこちらの女性は女の子を連れていることだ。空間的にひろがりや重層性が出るのはもちろんのこと、この絵が、給水器の前の女性だけを描こうとしたのではなく、「女中」という、ルイ15世の治世下、ロココ社会の底辺に暮らし、華麗や奢侈の裏側に生きる女性たちの実態に目を向けたものであることがわかる。
フランス革命まではまだ半世紀あまりの時の経過が必要になるが、そこに流れ込んで行く潮流は、明らかにここに見てとれる。
とはいえ、シャルダンの筆致は、静物を描く時と同じく、少しも猛々しくない。風俗を描いて、風俗を超えたところで、画家の慈愛の目が光っている。その点は、この絵が一見して明らかなほどのオランダ、フランドル絵画の影響下に生まれながら、それら北方の先輩格とは異なるシャルダン独自の風貌となる。
シャルダンの働く女性たちを描いた作品のなかでもつとに世に知られた『買い物帰りの女中』(1739 ルーブル美術館蔵)でも、こうした特徴――、多重構造の空間性や女中たちを描く階級性といった視点は等しく貫かれている。しかも、嬉しいことに(!)、奥の部屋では若い女中とともに、かの銅製の給水器が半身ほど姿を見せている。
こうなると、給水器は物(道具)ではあるものの、どこかキャラクター化して、女中たちを見守る神的存在にも見えてくる。
そこまで理解が及ぶと、『銅製の給水器』で描かれた単独の給水器が、単なる物を描いた静物画ということを超えて、
物を見つめるシャルダンの真摯な眼差しが、静謐を極めて時に神々しさにまで達するのは、そのような秘密を有していたからなのだろう。
生命なき物に対し、生命ある存在の代表格は人間であった。加えて、シャルダンにとって、もうひとつ、生命の象徴のように、画布の上に愛らしい姿を見せてくれる生き物がいた。猫である。
『洗濯女』(『洗濯をする小間使い』とも。1733 ストックホルム国立美術館蔵)――。
画面中央には、木の桶を使って、洗濯をする女性がいる。その脇には、シャボン玉を吹く男の子が描かれる。シャボン玉は、人生のはかなさを象徴するヴァニタスの意であると説かれるが、古い宗教性よりも、ここでは、労働現場に我が子を同伴せざるを得ない、働く若いママさん女中たちの実態が重要視されている。
奥の部屋では、別の女中が洗濯物を干している。表と奥の二重構造が「洗濯」でつながれて、女中たちの共同作業が、統一したテーマ性をもって描かれる。もちろん、これらの女性たちが洗っているのは、自分らのものではなく、ご主人様一家の使うシーツや衣類などである。
さて、そういう画面の右側の床上に、ちょこんと三毛猫が座り込んでいる。おそらく、猫がその場に飼われている具体的な理由は、ネズミ除けなのであろうが、あたかも女中たちの人生の同伴者のように、その場に姿を現しているのである。
手前の洗濯女は、洗い物の作業中に、何かに気づいて顔をあげたように見える。猫もまた、じっとした態勢ながら、何かの気配を窺い、視線をその先に集中させている。女と猫と、同じものに注目していると見てよいだろう。
ネズミが動き、物音をたてでもしたのだろうか、女と猫が息を合わせ、活き活きとした緊張感が走る。一方では、シャボン玉に興じる男の子や、奥の部屋で洗い物を干す女は、動きに気づかず、日常的時間に平常のリズムを刻んでいる。
動と静が交差する、日常のなかの瞬間的なドラマを、シャルダンは見逃していない。静謐の筆のなかに
猫が登場するシャルダンの絵のうち、最も有名なものが、初期の代表作となる『アカエイ』(『アカエイと猫と台所道具』とも。1728 ルーブル美術館蔵)だ。
ここでは、生と死が同時に画面上に載せられ、その対立が劇的なまでの緊張感を生んでいる。
アカエイは海中から引き上げられ、既に生命は断たれている。だが恨めしそうなその表情は、驕れる死の恐怖を象徴するかのように強い存在感を放つ。それに対し、手前に置かれた
シャルダンはこの他にも、いくつかの猫絵を残しているが、いずれも、力を溜めこみ、いざ動かんとする跳躍直前の姿で描かれている。生と死の葛藤のドラマに於いて、猫は生の象徴として登場させられているのだ。
静物画の先駆者的画家として、美術史に名を留めるシャルダン――。その彼が、同時に猫絵画家としても大きな足跡を残したことは、決して偶然ではないだろう。生命あるものと生命なきものと、その両者に愛の眼差しを注ぎ得る人だったからこそ、可能な道だったのである。
絵画史上、猫は伝統的に、不貞や淫欲、騒擾や不実といった禍々しいイメージを負わされて登場させられることが多かったが、シャルダンはそういう因習にもとらわれていない。
彼にとって猫は猫、人間と共生し、ともにこの世を懸命に生きる、生命力に溢れた魅力ある存在だったのである。
シャルダンは長寿の人で、80年もの生涯に恵まれた。だが晩年、著しく視力が衰えた(油彩に使う鉛の影響だったとされる)。
油絵を描くことはもはや難しくなったが、最晩年、パステルを使い、新たな境地を開く。自画像であった。70代に入って以降、13点の自画像を残したと言われる。
そのうち、最もよく知られた作品が、『日除けをつけた自画像』(『日除けを被る自画像』とも。1775 ルーブル美術館蔵)である。70代半ば、老境に達した芸術家を、みずからが虚飾を排した眼差しで見つめている。
眼鏡をかけ、頭にはボンネットを載せている。日除けの帽子をかぶっているが、そのせいか、農夫か養蜂家のように見えなくもない。飾らぬ素朴な人柄が窺える。
しかし同時に、ひどく生真面目な、不屈の精神をも感じさせる。時代の気分に逆らってまでも、おのれの画業を積みあげてきた、芸術家の意志の力が漲っている。
その力は、まだなお衰えず、現在から未来へも向いている。
『画架の前の自画像』(『イーゼルの前の自画像』とも。ルーブル美術館蔵)という、亡くなる年の1779年に描かれたと推定される自画像もある。いよいよの最晩年の姿を、画家自身が見つめ、絵にした。
この時、シャルダン80歳――。精悍さという点では、75歳の自画像に比べ、落ちているだろう。いくぶん痩せもした。つる(テンプル)のない鼻眼鏡をつけ、白いボンネットにはブルーのリボン状の帯を結んでいる。
オランダ絵画の影響を受けたシャルダンには、多数の自画像で知られたかの国の巨匠、レンブラントから得たものも多かった。
自己を見つめる真摯な眼差しは、いかにもレンブラント譲りであろう。しかし、レンブラントが暗く、重く、人生の厳しさ、苦しさを見つめたのに対し、シャルダンはどこか明るく、
物に注がれ、女中たちに注がれ、猫に注がれてきた慈しみの眼差しが、今は老熟した自身に注がれている。
最後の自画像と推定されるこの作品が、イーゼルを前に、赤い筆記具(パステル鉛筆?)を手にした絵であることが、なんとも微笑ましく、シャルダンその人らしい。長い絵画人生そのものが、そこに結晶している。
画家の不滅の魂は、この世からあの世に、ひょいとこのまま、どぶ板でもまたぐように、移行してしまうのではないかとさえ思わせる。
画布に注がれていた眼差しをふとこちらに向けたその表情も、いわくありげだ。絶筆であることを知れば、何がしかのラスト・メッセージを聞くような思いにとらわれる。
その表情の語る言葉は、私には、四角四面の標準語よりも、響きの柔らかな関西弁で聞く方がふさわしいような気がする。
「えらい年食うてしもうたけど、まだまだ若いもんには負けられしまへんで。絵描きは、死ぬまで絵描き……いや、死んでも絵描きでっしゃろ。ほんま、人生いくつになっても、おもろいもんですわ」――。