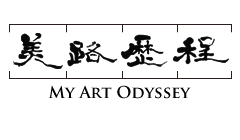

小学校6年生の時のことだったと記憶する。小遣い銭を溜め、初めてLPレコードを買った。ベートーヴェン作曲、交響曲第6番「田園」―。アンドレ・クリュイタンスがベルリン・フィルを指揮したものだったが、数ある名曲の中からどうして「田園」を求めたのか、またカラヤンのようなスター指揮者ではなく、なぜ地味目のクリュイタンスのレコードを選んだのか、もはや記憶は曖昧だが、今もはっきりと覚えているのは、レコードのジャケットに使われていた絵である。
その絵は、西洋の農民たちの宴を描いたものだった。私はどの時代、どの国の何という画家によって描かれたのか、少しの知識もないまま、その絵に魅せられた。そして「田園」のレコードをかけるたびに、しげしげと絵を眺めた。私にとっては、その絵が(写真ではあったが)名画というものとの本格的な出会いとなった。
その絵が、16世紀のフランドルの画家、ピーテル・ブリューゲルが描いた「農民の婚宴」という作品であることを知ったのは、だいぶ後になってからである。今にして思えば、ベートーヴェンの「田園」は森や野の豊かな自然こそが主眼となるもので、農民の暮しの一景を描いたブリューゲルの絵がレコード・ジャケットとしてふさわしいかどうか、かなり疑問だ。曲を象徴するイメージを泰西名画からとるなら、コローやコンスタブルの描く風景画のほうがよほどふさわしい。
いや、ベートーヴェンと合う合わないを、今さら論議しても始まらない。肝心な点は、レコードをきっかけに、私が繰り返しその絵を眺めるようになったことだ。少年のつたない感想ながら、私は民画風の味わいに親しみを覚えた。素朴な農民の暮らしをあたたかな眼差しで描いた、ほのぼのとした絵に感じた。だがそれでいて、絵の発する強靭な何かに惹きつけられてならなかった。無論、その引力の正体は、とても少年の頭で言葉にできるものではなかったが…。
写真ではない、この絵の本物に出会ったのは、20年あまりの歳月がたってからだった。初めて訪ねた冬のウィーンで、旧王宮やモーツァルトの銅像を見たその足で、美術史美術館を訪ねた。ハプスブルク家のコレクションをベースにした膨大な収蔵品のなかに、一連のブリューゲル作品が収められていることを知り、大いに驚いた。
ブリューゲルの力作が並ぶ中に、「農民の婚宴」もあった。少年の頃に繰り返し眺めた絵だけに、初めて見る気がしなかった。だがやがて、新鮮な感動がひたひたと胸を浸し始めた。大ぶりの画面からは、構図や色彩、筆づかいに至るまで、圧倒的な力感をもって迫ってくるものがあった。リアリズムに徹した筆の雄勁ぶりは、ほのぼのとした農民画という安穏な落ち着きどころを遥かに突き抜け、人生の根源に迫るおごそかな精神のさら地に導いてやまなかった。
今では、研究者が語るこの絵に潜まされた寓意や教訓についても、知識として承知はしている。皿を舐めるように料理に食らいつく子や客人は、飽食、過食を戒めるものだという。テーブルの隅で語り合う領主と修道士もまた、宴の贅沢を批判しているのだそうだ。だが私には、ブリューゲルの絵筆がそうした戒めを説く道具に収まるとは到底思えない。農民を描きつつ、農民を謳歌するのではないのと同じく、彼の目は善悪の垣根の彼方から、人生の本質、真実の核心へと、一心に注がれている。
「農民の婚宴」は、中央の奥、緑色の天幕の下に座る新婦が中心核となる絵である。平凡な農家の娘であろう、しかし娘にとっては人生一度の晴れの舞台なのだ。この先、農夫の妻となり、やがては母となって、さして変化のない人生を、農作業や家事や子育てなど、休む間もない労働に追われてすごすことになる。祝いの席に集う村人たちは、この時とばかりにご馳走や酒に手を伸ばす。楽師でさえ、配られる料理に気をとられて演奏を中座する。それでも、この日のヒロインは頬を赤く染めながら、束の間、常ならぬ主役の座に尻を温める。
そうした新婦と農民たちの人生模様を、ブリューゲルはしかと見つめる。情に溺れず、着かず離れずの姿勢を貫いて、人生の一景を凝視するのである。その揺るぎない、たじろがぬ確かな視座が、ブリューゲルという画家の真骨頂だと感じる。
小学6年の私が感じた絵が発する強靭な何かとは、このたじろがぬ眼差しであったろう。初めての出会いから半世紀近い歳月がたち、その後の数次にわたる邂逅を経て、私にとってのブリューゲルは、単なる美的愛好を超えた精神領域での不動の存在と化している。