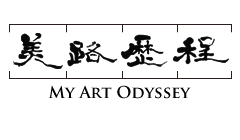

ウィーンの美術史美術館のブリューゲルの部屋に足を踏み入れた者なら、誰しもが一連の作品群から発せられる独特の気に息を呑み、豊饒にして濃厚な世界を前に、必ずや深い想念にいざなわれることになろう。それほどに傑作揃いということだが、ブリューゲルという画家を見極める上でこれ以上のコレクションはないばかりか、人間にとって芸術とは何か、その本質を考える貴重な舞台を提供してくれている。
「農民の婚宴」同様、農民の暮らしを見つめ、時にアイロニカルな眼差しを含めて描いた「農民の踊り」―。ネーデルランドの先輩画家ボスの流れを汲んだ「尽くし」の画法が横溢する「子どもの遊戯」と「謝肉祭と四旬節の喧嘩」―。旧約聖書の創世記に登場する伝説の塔を描き、人間の不和を嘆いて見せたメッセージ性の濃い「バベルの塔」―。そして、連作月暦画として2カ月ごとの風景を描いた「暗い日」「牛群の帰り」と「雪中の狩人」―。
初めて訪ねた折り、私の目は懐かしき「農民の婚宴」にしばし留まることになったが、やがて多様な作品群を巡る中で、ひとつの絵に収斂されていった。少年の日の「田園」交響楽をきっかけにした邂逅に継いで、ウィーン訪問がブリューゲルとの2度目の強烈な出会いを授けたのである。「雪中の狩人」と題されたその絵に、私は吸い込まれるように惹きつけられた。しばらくは、そこから動けなかった。
言うまでもなく、それは冬の風景を描いた絵である。一見すると、世界はすべて雪と氷に覆われ、何もかもが凍てついてしまったような気にさせられる。だが、そこでも人の暮らしは続いている。狩人たちは犬を率いて雪の野を行く。ただ、獲物を狙って意気揚々と出猟するようには見えず、狩りに出ては見たものの、空しく家路を引き返す徒労感の滲む後ろ姿のように感じる。旅籠であろうか、看板のかかる家屋の前でも、火を焚きながら野外での仕事が続いている。寒さに堪えつつ、生きるがための労働である。
遠くにも働く人が見える。だが、遠景ではそれ以上に、氷結した池の上で遊び興じる人たちの姿が目立つ。息も凍るような厳寒の中、人の営みは確かに続いているのだ。ただ、ブリューゲルの描き方は、どこか影法師でも見るように、郷愁の中に息をひそめる。圧倒的な冬の支配下に、人は何とか命をつなぐばかりなのである。あたかも、冬の木々が葉を落とし裸木となっても、その内部に命をたくわえ、春の芽吹きをじっと待つかのように…。
ウィーンで出会った「雪中の狩人」に、その後、更なる、そして強烈な出会いが重なった。ソビエト・ロシアに生きた映画監督タルコフスキーの傑作「惑星ソラリス」―。ポーランドの作家、スタニスワフ・レムのSF小説をもとに、1972年に撮られた映画で、日本でも1977年には公開されたが、私が見たのはタルコフスキーの死後、1990年代になってからだった。
謎の海に覆われた惑星ソラリスを探索中の宇宙ステーションに障害が生じ、科学者のクリスが派遣される。宇宙ステーションに到着したクリスの前に、10年前に自殺した妻のハリーが現れる。ソラリスの海は、人の記憶からイメージを再生させ、物質化して送り込んでくるのだ。埋めがたい時を埋めるように、ふたりはステーション内で蜜月の共にすごす。以後、物語はSF的設定を借りながら、良心の呵責や愛の葛藤など、人間の内面世界を深く掘り下げていく。
この宇宙ステーションの図書室の壁に、5点のブリューゲルの絵が飾られている。「暗い日」「穀物の収穫」「バベルの塔」「イカルスの墜落のある風景」、そして「雪中の狩人」―。とりわけ「雪中の狩人」については、蘇生したハリーがしみじみと眺め、絵の部分アップがいくつも重ねられる。かつてそこに生きたロシアの冬を懐かしむように見えなくもないが、絵に注がれるハリーの眼差しは単なるノスタルジアを越え、遥かに深いものを追うように見える。
些末な事実を指摘すれば、雪に覆われる景色であっても、絵の教会は尖塔を抱くフランドルのものであって、ネギ坊主の丸屋根を戴くロシア正教会のものではない。だが、そのような小差をあげつらうことが恥ずかしくなるほどに、絵はおしなべて世における人のありようを、正確に剔抉して描き出す。ソラリスの海に囲まれる中でブリューゲルの絵に対峙することは、懐旧という次元で言うなら、地球という星の記憶を確かめ、生きることの根源的な意味を改めて問うことに他ならないのだ。
圧巻は、ブリューゲルの絵を前にしたふたりの浮遊シーンだ。生きることに傷ついた者同士、しかもかつては相手を傷つけ相手に傷ついた当事者同士だったふたりが、今は赦し合い、失った愛を取り戻そうとする。と、天井のシャンデリアが揺れ、音をたてる。宇宙空間ならではの無重力に襲われたのだ。体がふわりと浮き、ふたりは抱き合って空中を浮遊する。背景にはブリューゲルの絵。流れる音楽は、バッハのコラール「主よ、我は汝の名を呼ぶ」のメロディー。何度も見ても、このシーンになると、涙が止まらない。それはあまりにもタルコフスキー的な芸術美の極致なのだが、同時に、ブリューゲルの本質を語ってあまりあるオマージュでもあるのだ。
1975年につくられたタルコフスキーの映画「鏡」でも、明らかに「雪中の狩人」が下敷きになったと思われる場面が登場する。自伝的色彩が濃い、私小説風なイメージをモザイクのように綴ったこの作品では、ブリューゲルの絵画そのものはショットとして登場しないものの、絵の構図を意識し、また絵の世界を自家薬篭中のものにした上で、フィルム上におのれ流儀に「再構成」している。
第2次世界大戦下のソ連―。雪景色の中、子どもたちを相手に軍事教練が行われる。少年の日の主人公と同じ班に、教官の言うことを聞かない反逆児がいた。国家イデオロギーを忠実に奉じる歴戦の勇士が、赤軍予備軍たる子どもたちに射撃訓練をほどこす。しかし、国家や時代が吐く言葉の内にひそむ不実や虚偽を、問題の少年は知り抜いている。事あるごとに教官に逆らい、たったひとり反抗を続ける。大人や他の子どもたちは騙せても、その少年だけは真実に目をつぶるわけにはいかないのだ。
少年は社会の矛盾を一身に引き受け、何度となく泣き腫らしたような顔で、世の習いになびくことを拒み、乾いた唇をかむ。まるでキリストの少年版のようですらある。その孤独な少年が、雪に覆われた丘にたたずむ。ゆるやかな白い斜面が彼方へと下り、川原らしい雪原へとひろがる。明らかに、ブリューゲルの「雪中の狩人」を意識した構図だ。
ここでタルコフスキーは驚くべき強引な演出に出る。なんと、丘の上に立たせた少年の頭に、冬枯れの木から舞い降りてきた烏(カササギ?)をとまらせようとするのだ。もちろん、ブリューゲルの絵で銀世界の中の黒点のように登場していた烏のイメージである。今ならばデジタル技術で合成が可能な表現だが、当時はすべて実写で撮影せざるをえない。おそらくは少年のかぶる帽子にエサを載せて、舞い降りる烏を撮ろうとしたのだろう。だが、烏は思うように少年の頭にとまってくれない。頭の上にしばし留まってもくれない。何度かNGを繰り返し、挙句の果てに鳥を少年の頭に載せた独立したショットをフィルムにおさめ、編集でつなぐことにした。
ただし、枝から烏が降りてきた過程が流れとして撮れているわけではないので、編集でつなげば、同ポジ同サイズではあっても、絵飛びがして、かたんと画面が揺れる。通常の編集では許されない破格にして外道なのだが、そうした欠陥は百も承知の上で、タルコフスキーはブリューゲルと呼吸を合わせようとする。まるで、見る者に「雪中の狩人」を想起してもらわねばならないとでも宣言するかのように…。
タルコフスキーがブリューゲルと息を合わせ、その絵に重ねたかったものは、反抗の少年の孤独ばかりではなかったろう。母の記憶を軸にしたこの映画が描く、20世紀という理不尽と狂気の時代に生きざるを得なかったすべての人々の生が、ブリューゲルにこだましているのだ。人間の尊厳や自由が踏みにじられたソビエト社会―、それは季節に譬えればまぎれもない冬の時代なのだが、苦渋と絶望の中にかろうじて命をつないだ人々の生の重みが、ブリューゲルに共鳴しているのである。
その生の手ごたえを、喜怒哀楽などというありきたりの言葉が蓮っ葉に感じられるほどの次元で凝視する。その深く厳しい眼差しは、ペシミズムの感傷には遠いが、ニヒリズムの冷酷さとも違う。木々や自然が、季節の移ろいを超えて確かな生の営みを積み重ねるように、どこか、生を包みこむような大きな力に裏打ちされている。それはおそらく、悟達の哲学者が抱く高次元の愛というものだろう。敢て言うなら、木を尊び慈しむ、まさにその眼差しで人間を見すえているのだ。
ブリューゲルには、もっとあからさまにメッセージ性を全面に押し出した絵もある。かの「バベルの塔」は言うに及ばず、処刑の場のすぐ近くで踊り興じる人たちがいる「絞首台の上のカササギ」や、繁栄する港湾都市にあって、はしばみの実を与えられる代わりに鎖でつながれてしまった「2匹の猿」など、絵に込められた批判や風刺の毒は一目瞭然である。寓意をなぞった絵も多い。ウィーンの「謝肉祭と四旬節の喧嘩」もそうだが、寓意を描くのに、イメージの限りを尽くして画面いっぱいに横溢させた作品も、いかにもブリューゲルである。寓意はしばしばイマジネーションの翼を得て、幻想画の赴きさえも生じる。
もちろん、絵に潜まされた当時の格言など、研究を積んだ学者の絵解きによらなければ、寓意の理解が難しい場合もある。だが、私に言わせれば、それらの絵はむしろブリューゲルとしては「わかりやすい」絵である。寓意をなぞるだけなら、言葉によって解説可能なのだ。しかもそこで語られる言葉は、私たちが職場や家庭といった生活の場で語る日常の言語から著しく外れることはない。
だがブリューゲルには、寓意にじかに依らず、寓意を超えて描かれた作品群がある。連作月暦画はその典型だが、寓意性が薄められている分、なかなかに言葉にするのが難しい。「雪中の狩人」はそうしたブリューゲルの頂点に立つ作品であろうが、ここでは、ブリューゲルの絵画言語は日常とは異なる地平線から発せられているように思う。つまり、私たちが商売の算段をしたり、政治を論じたり、旅行の相談をしたりするような次元とはおよそ異なるところで、世の中や人生というものを見つめ、その本質に迫っているのだ。そこに問われたものは、人が人である限り、時代を貫いて魂に響くものである。いずれの作品でも、自然が大きな位置を占めているのは留意すべきであろう。人の生きる場として、自然を含む、自然が包む大きな世界(宇宙)が想起され、観照されているのである。
少年の日の私が出会った「農民の婚宴」は、納屋の中の人間集団だけを描いたものながら、寓意をしのばせつつも、そこから飛翔し、「雪中の狩人」的な次元へと半歩を踏み出した作品だった。素朴な結婚式の花嫁も、呑み食らい浮かれ騒ぐ農民たちも、大きな宇宙の摂理の中に束の間の晴れの時をすごしていたのである。
慎重を期して、私はここまで「宗教」という言葉を避けてきた。特定の宗派に片寄りたくはないし、ましてやご利益追求の信心など、ここではおよそ無縁のものだからだ。だがブリューゲルの絵を突き詰めて行くと、真の意味での「宗教者」のような眼差しに行きつかざるを得ない気がする。私にそのようなブリューゲルへの眼差しを開かせてくれたのは、タルコフスキーだった。宗教の否定されたソビエト・ロシアで、ひたすら心の問題にこだわり続けた彼にとって、ブリューゲルは永遠の師となる芸術家だったに違いない。
科学文明が進み、一見すると「宗教」などにもはや出番がないかに見える21世紀の今日、ブリューゲルが、巷に溢れる「言葉」ではとらえきれない人間の心の闇を見すえつつ、いっそうの光明を放つように思うのは、決して私ひとりではないだろう。