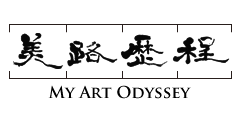

イギリスに暮した頃、よく古典物のペーパーバック(文庫本)を買った。「積ん読」になってしまったものも多いが、それなりに数をそろえてみると、殆どの本が文字ばかりの中、時としてところどころに挿絵が挟みこまれているものがあることに気づき、面白く思った。その絵が、ちょっと尋常でない。今風にありふれていない。時代がかってはいるが、なかなかに個性的で、印象は強烈だ。
実はそれらの挿絵は、作家の生存中に本が出た際、たいそう人気を博し、あまりの人気から物語と切っても切れないイメージにまで発展して、百年以上の後に文庫化されるにあたっても、そのまま当時の挿絵が使われたものである。まさに不滅の物語に不滅のアートといったところだろうか。

そのような代表的存在に、ルイス・キャロル作の『不思議な国のアリス』(1865年)と『鏡の国のアリス』(1871年)のシリーズがある。挿絵はジョン・テニエルの手になる。テニエルは当時大変な人気を博した風刺漫画雑誌「パンチ」の看板画家だった。
テニエルはアリスの物語の挿絵を描くにあたって、基本的には「パンチ」でつちかったカリカチュア(戯画化)の手法を用いた。それゆえか、テニエルのアリスは今風な意味からは決して可愛らしいとは言いがたい。が、妙に心に残る。単なる「よい子」の枠におさまりきらぬ摩訶不思議な存在感を発する。「おとな子供」のような印象すら受ける。ちびっこでありながら、充分に「ファム・ファタル」なのだ。
肝心なのは、アリスの物語が夢物語という点である。夢というものは、現実に依拠しているようでいて、後から考えれば得てして奇妙キテレツ、荒唐無稽なものだ。現実の間尺を超えているからこそ、夢のつむぐイメージは斬新にして珍奇、妖しくも生き生きと輝く。そのような現実世界を超えた幻想物語の主人公として見れば、テニエルのアリス像はやはり的を得た聖女像だ。特にさまざまな場面で登場する動物たちや他のグロテスクなキャラクターたちとの相性は抜群である。
このユニークな挿絵が生まれるには、もともとルイスがテニエルに依頼したという経緯がある。テニエルの挿絵によって、無名作家だったルイスの物語はベストセラーになった。すると面白いことに、今度はルイスの物語自体に、画家を惹きつける魔力のようなものが生まれた。1907年にテニエルとの専属契約が切れてアリスの物語は他の画家たちにも門戸開放となるが、その後もさまざまな画家たちによって独自のアリス像が生み出され続けている。アートが物語に命を与え、その物語が新たなアートに命を与えるのだ。

19世紀英国を代表する国民作家のディケンズもまた、挿絵との蜜月を謳歌した作家だった。大部の長編小説を次々に発表した巨艦主義のディケンズだが、そのうち『デイヴィッド・コパフィールド』と『二都物語』を、私は挿絵付きのペーパーバックで読んだ。大長編を英語で読みきる持久力を維持できたのは、小説の面白さだけでなく、次に挿絵が登場するのを楽しみに読み継いだおかげでもあった。この2作の挿絵は、長年にわたってディケンズの挿絵を描いてきたハブロー・ナイト・ブラウン(通称フィズ)の手になるもので、物語とぴたりと息の合ったさまはさすがというしかない。
イギリスのクリスマスの顔ともいうべきディケンズの中編小説に『クリスマス・キャロル』があるが、ジョン・リーチによるこの挿絵も捨てがたい。わけても「フェジウィッグ家の舞踏会」の絵は、ほのぼのとしたペーソスがノスタルジックな情感を醸して胸に響く。クリスマス・イブの夜の宴における人々の陽気なはしゃぎぶりの中に、どこか人恋しさや世のはかなさまでが漂う。今でも愛蔵版の『クリスマス・キャロル』が世に出ると、しばしばこの絵が表紙に使われるのも頷ける。
アリスもディケンズも、今では挿絵がアートとして単独に印刷され、愛好家たちによって飾られている。物語と離れて壁にかけられても、無論、それは物語の記憶を留めている。座右の書として、いつも手に届くところに置いておくのも、愛する本に対するひとつのスタイルであろう。だが、書から抜け出て飾られた絵を眺めながら、本との愛しい思い出を好きなだけ反芻するのも、物語とアートのマリア―ジュとして、望ましき幸福な姿のように思える。
