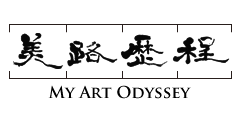

秋の日の午後、東京駒場の日本近代文学館で幸福なひと時をすごした。熟れ行く季節の穏やかな陽射しが射し込む閲覧室に座をしめた私の前には、この文学館が複製した漱石の『吾輩は猫である』(以下『猫』と略す)の初版本が置かれていた。
一応は漱石に関する本(『吾輩はロンドンである』『スコットランドの漱石』)も出している身であれば、『猫』は過去に数回は読み通している。初版本についても、大学時代に研究室で手にしたはずなのだが、当時は充分な知識も眼力も備わっていなかったために、宝物を見てもその本当の価値に気づかなかった。
ロンドン留学から帰国して2年後の1905年、漱石が38歳にして作家デビューを果たすことになった長編小説である。風刺や諧謔に満ち、猫から見た人間世界の浅ましさや欲深さ、おかしさや哀れさなどが横溢した内容だが、その文学性だけに目を奪われていると、漱石が仕掛けたいまひとつの意図、この作品がもつもうひとつの価値は見抜けない。それはずばり、小説作品に付与された装幀や挿絵という美の体裁、意匠なのである。
連載第2回の本文で、英国の小説本における物語とアートのマリア―ジュについて述べたが、漱石という人は2年間の英国体験を通して、当時の日本人の誰よりもこの魅力を知悉していた。
「倫敦に住み暮らしたる二年は尤(もっと)も不愉快の二年なり」(『文学論』)――あまりにも有名な漱石の言だが、近代の牙城のようなロンドンに馴染めず、個を押しつぶす圧倒的な産業と文明の力に辟易した一方で、漱石は書物における美のありようの王道をきっちりと身につけて帰国した。やがて『ホトトギス』に連載して好評を博した処女作の『猫』が1冊の本にまとまるという時、漱石の頭には英国で見聞した物語とアートのマリア―ジュの妙が明確に意識されていた。
表紙画やカットデザインを含めた装幀を橋口五葉に託し、各章の物語中に挟みこむ挿絵を中村不折と浅井忠に依頼したが、専門の画家にお任せするなどというレベルではなく、自らイニシアティブをとって、『猫』の製本化にあたり総合プロデューサーの役割を果たしたのだった。
日本の文学土壌に新たな地平線を拓こうという意欲が『猫』を生んだことは間違いないが、同時に、漱石はこの国の書の概念をアートによって塗り替えようとする革新的な意志を秘めていたものと思われる。
さて、『吾輩は猫である』初版本の表紙や扉などに使われた橋口五葉のデザイン画である。これが不思議な雰囲気を湛えた極めて独自の世界を構築している。ちょっとアールヌーボーのようなニュアンスで、漱石がロンドンで馴染んだラファエル前派の赴きも有する。
猫の物語だがら猫が多出するのは当然として、そんじょそこらの三毛でも野良でもない。茶の間や三和土(たたき)、庭先や縁側など、こじんまりとまとまりつつもどこか陰鬱で漬物臭い日本の風土を超越して、まるで古代王朝のファラオの如き、あるいはまたアテネのアゴラ広場の哲学者の如くに泰然として、時と空間を超えた存在感を発している。
その意味では、『不思議な国のアリス』の挿絵にも通じるところがある。ファム・ファタルならぬシャ・ファタル(宿命の猫)として、堂々たる貫録をそなえているのだ。
橋口には西洋体験がなかった。しかも、『猫』のデザインを手がけることになった1905年と言えば、まだ24歳の若さで、東京美術学校を卒業したばかりだった。在学中から『ホトトギス』の挿絵を描き、また漱石が英国留学前に奉職していた熊本の第五高等学校に兄が学ぶなど、それなりの縁はあったにせよ、何とも大胆な抜擢である。
総合プロデューサーとして、漱石はやかましく注文をつけたに違いない。漱石がロンドンから持ち帰った英語の書籍類は400冊とも500冊とも言われるが、そうした本や雑誌を橋本に見せながら、自分の望む意匠を熱っぽく語ったのだろう。とりわけ、ロンドンで親しみ、帰国後も購読を続けた美術工芸誌『The STUDIO An Illustrated Magazine of Fine & Applied Art』からの影響は顕著である。漱石の期待に橋口の若い感性が見事に応えて、世界の息が通う新しい美の造形に成功した。
私が唸らされたのは、上中下と3編あるうちの上編のカバー表紙になった絵で、ファラオの如くに堂々とした猫の座像の手元に、雛人形か何かのように人物が小さく並び、ある者は猫の手に半身を握られているという構図のものである。人物は苦沙弥や迷亭、寒月といった物語の主要登場人物たちだが、ここでは猫と人間が大きさを逆転し、ガリヴァ―的発想が生かされている。猫の視線から人間界を見つめるという『猫』の趣向がさらに拡大発展させられて、奇想天外なSF的構図の中に物語の本質を雄弁に語っている。
こうなるともう、お釈迦様の掌の上であくせくするしかなかった孫悟空というか、「世の中はすべて舞台、人は皆ただの演じ手」と喝破したシェークスピア(『お気に召すまま』)というか、古今の宗教や哲学に匹敵するほどの高みに飛躍している。恐るべし、漱石&橋口!である。
なお、橋口は『猫』以降も漱石本にはなくてはならぬ存在として、多くの著書で装幀を担当している。
『猫』の挿絵に関して、もともとの漱石の意中の画家は浅井忠であったという。漱石よりも11歳年上になり、漱石のロンドン留学と同時期にフランスに留学し、パリで会ったこともあるこのヴェテラン画家に、漱石は信頼を寄せていたのである。
しかし、浅井が多忙を極めたため、上編に関しては浅井の弟子筋にあたり、やはりフランス留学から帰国して間もない中村不折に白羽の矢が立てられた。漱石よりもひとつ年上で、かつて日清戦争に際して正岡子規とともに画家として従軍した経験をもつ。
この不折の起用が、実に成功している。上編だけで5点の挿絵を描いたが、俳味の漂う軽妙なトーンながら、月並みを脱している。
第1章で初めに登場した挿絵は、苦沙弥家の下女か子供と思しき人物が「吾輩」の尻尾をつかんで追い立てる姿である。下女か子供と曖昧な表現になったのは、この絵が小説本文と微妙に違うからだ。家に上がりこもうとする猫を、そのたびに首筋をつかんで追い払ったのは下女のおさんだが、尻尾をつかんだとは書かれていない。子供のわがままぶりを、「時には人を(「吾輩」のこと)逆さにしたり」と記してはいるが、挿絵の方は逆さ吊りではない。
そういうディテールの食い違いを見せつつも、これはいかにも『猫』の物語世界の幕開けを視覚化した素晴らしい絵だ。私がつくづく感心するのは、この人間に虐待される猫の絵を、障子ごしのシルエットで描いた点だ。漱石の文章には、影絵を必要とする要素は登場していない。つまり、これは不折が独自に物語に賦したイメージに他ならない。
第3章でも三味線を弾く猫がシルエットで登場させられていて、これはかなり意識的な意匠であると知られる。遊里を描く江戸の浮世絵にも障子ごしのシルエットの趣向は存在したが、その駘蕩とした気分を借りながら、ここでは太平楽を裏側から覗くようなワサビをきかせている。
また、第2章では「吾輩」のガールフレンドだったメス猫・三毛の葬式の挿絵が登場するが、「南無猫誉信女南無阿弥陀仏」と回向する僧侶以下3人の画中の人物は、みな後姿で敢て表情が見えるのを避けており、顔が描き込まれる以上に強い印象を与えている。画調はユーモラスで明るいが、表情の虚ろさは衝撃ですらある。どこかシュールレアリスムっぽいのである。
猫像のシルエットと、この顔なしの人物画は、創造の根っこの部分において通底している。中村不折が『猫』という文学作品をどのようにとらえていたのか、何がしかを浮き彫りにしている。それはつまり、太平の逸民のような主人公たちが繰り広げる延々と続くかに見える「与太話」の中に、世の中の、社会の、時代の「陰画」を見ているということなのだ。
これはすごいことである。挿絵が、物語作品の本質をずばりと突いている。単にある場面の情景をヴィジュアルに説明するだけでなく、物語の外から、あるいは内側から、その世界を視覚化して「描写」しているのである。
『猫』の上編が単行本として上梓された時、漱石はまだ『ホトトギス』に『猫』の中後半を連載中だったが、上編の初版はわずか20日で売り切れてしまった。人気のすさまじさが窺えるが、挿絵の果たした役割は大きいと、漱石は感謝の手紙を不折に送っている。
『猫』という作品を生むことになった漱石の胸には、西洋体験者として日本社会に抱かざるをえなかった違和感が炎のように燃えたぎっていた。不折もまたフランスから帰国したばかりで、ロシアとの戦争を遂行中でもあった当時の日本に含むところがあったのだろう。『猫』における物語とアートのマリア―ジュの底には、軋みたてるような「異」が共鳴を響かせていたのである。
中、下編の挿絵は、もともと漱石の意中の人であった浅井忠が担当した。合せて6点の挿絵を描いている。
中村不折が敷いたレールに載って、浅井は猫と苦沙弥一家の暮らしを軽妙洒脱に描く。3人の子どもたちが飯をほおばる食卓の風景など、実に愉快だ。『猫』における浅井の絵は、全体におかしみに溢れ、人間世界のすったもんだの騒動を、少し離れた所からあたたかな眼差しで見ている。絵は構図といい筆づかいといい、安定感があり、確かなものである。
ただ、不折が絵に忍ばせた陰画にあたる部分は、明らかに後退している。影絵芝居のようなシルエットも、奇妙なのっぺらぼうも、浅井の絵には登場しない。その意味では、毒がない。酸いも甘いも噛み分けた老名人の落語を聞くかのように、すべてが笑いの中に濾過された心地よさがある。
浅井忠の名人芸に感心しつつ、私の胸にはどこか、中村不折に最後までやらせてみたかったという思いも残る。「吾輩」の死に至るまでの中後半、どのような陰画をしかけてきただろうかと、興味が尽きない。
巨匠にまかせたからでもあるまいが、総合プロデューサーとしての漱石の力が、後半になって幾分弱まっているように感じるのは私だけであろうか。特に下編のラスト、物語全体の終結部でもあるわけだが、「吾輩」の死を招くことになる猫がビールを飲む場面が、橋口による絵が冒頭の扉対向画に載り、また本文中で浅井の挿絵が現れてと、同じ体裁の絵がダブルで掲載されたのは理解に苦しむ。
酔狂による猫の死を描くに、両画家に競合させたかったわけでもあるまいに、売れっ子作家となってしまった漱石に充分な調整の時間がなかったのだろうか。アートフルな『猫』初版本における、わずかな瑕瑾のように見える。
漱石という作家は、たいそう美術を愛する人であった。日本の近代文学の中でも、彼ほど作品中に多くの美術作品を登場させた作家はいない。2013年には、漱石の代表的作品のテキストをもとに実際の美術作品を集めた「夏目漱石の美術世界展」という展覧会が開かれ、評判を呼んだほどである(東京藝術大学美術館ほか)。
私は漱石を敬愛する者だが、だからといって、自宅に漱石の胸像を置き、日夜恭しく拝するような趣味はない。それでも、『猫』の表紙絵や口絵、挿絵で部屋を飾りたいくらいの気持ちは持ち合わせている。
かつてイギリスで訪ねた家で、ディケンズの本の挿絵のリプリント版ばかりを飾った部屋があり、心躍ったことがあったが、狭い我が家ながら、どこかの部屋のせめてひとつの壁くらいは、『猫』で埋めてみたい気がする。
現在書店に並ぶ『猫』の文庫本では、角川文庫が今も初版の挿絵を載せている(すべてではないが)。絵のサイズが小さく、印刷も鮮明でない欠点はあるものの、橋本五葉や中村不折、浅井忠といった人たちの作品を加味した『猫』は、やはり手にとるのが実に楽しい。
その愉悦の記憶を、本のページから部屋の壁に移して、空間性の中に楽しむ醍醐味を、いつかは我がものにしたいと念じている。さすれば、少しは我が文才もかの文豪に近づきもしようかしらん……? おっといけない、たちまち「吾輩」の猫殿からきつい雷が落ちてきた。
「ニャアニャアニャア、ニャニャニャーニャ、ニャア!(そんな訳ないだろうが、この唐変木!)」――くわばら、くわばら。