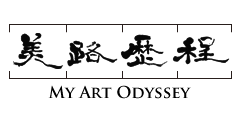

ルーブルは語るにしかず、オルセーもよい、ポンピドーも面白い。しかし、パリの美術スポットを訪ねるなら、是非ともここにも足を運びたい。ガルニエ宮としても知られるオペラ座――。もとは1875年、ナポレオン3世の第2帝政期に建てられたこの伝統の歌劇場に、巨大なシャガール作品が存在する。
1964年、時の文化相アンドレ・マルローの依頼を受け、シャガールはここに「夢の花束」という新しい天井画を完成させた。歌劇場なのだから、音楽を聴き、オペラやバレエを鑑賞するのもよいが、ここでは特にシャガールの天井画をたっぷりと味わいたい。
いや正直言うと、1989年にバスティーユに新しいオペラ座が誕生して以来、ここでオペラを聴ける機会はまれになってしまった。一石二鳥とは行かなくなったが、その分、公演のない昼に館内見学ができるようになっているので、シャガールを目当てに訪れる人が引きも切らない。天井画は大円とその中心の小円との2重構造になっている。そこに、合せて14のオペラとバレエ作品が寄せ絵のように集合し、シャガール一流の祝祭的イメージに仕上がっている。
大円には、モーツァルト「魔笛」、ムソルグスキー「ボリス・ゴドノフ」、ラベル「ダフニスとクロエ」、ストラヴィンスキー「火の鳥」、ラモー「?(作品不詳)」、ドビュッシー「ペレアスとメリザンド」、ベルリオーズ「ロミオとジュリエット」、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」、チャイコフスキー「白鳥の湖」、アダム「ジゼル」の10点。
内側の小円には、グルック「オルフェオとエウリディーチェ」、ベートーヴェン「フィデリオ」、ヴェルディ「椿姫」、ビゼー「カルメン」の4点。オペラやバレエの作品の間には、エッフェル塔や凱旋門など、パリを象徴するモチーフも描きこまれている。すべてを確認しようとすると、かなり首が痛くなる。
オペラファンとしては、不思議に思うこともある。パリと縁の薄かったヘンデルがないのは、まあ仕方なしとしよう。が、ロッシーニがない。イタリアだけでなくパリでも活躍した作曲家なのだが……。さらに驚くのは、プッチーニがない。「蝶々夫人」はおろか、パリが舞台の「ボエーム」すら存在しないのだ。
こうしたチョイスがシャガール自身によるものかどうか、精細な事情は不明だが、できあがった作品はそのような「欠落」を豪も感じさせることなく、他の誰にも真似のできない、文字通り夢のような雰囲気を醸し出している。さまざまの色彩が調和し合い輝くさまに、恍惚とさせられるばかりだ。
シャガールは音楽、劇場と馴染みの深い画家だった。「魔笛」や「ダフニスとクロエ」、「火の鳥」などの作品は、実際の公演で、舞台装置と衣装デザインを担当したこともある。
パリのオペラ座の天井画が完成した時、シャガールは「天井画は下の舞台で創り出される多くの夢を映し出す鏡であってほしい」と語ったそうである。舞台と響き合うばかりではない。同じ円内のオペラのイメージ同士が響き合い、大きな夢をふくらませているのだ。
私が初めてクラナッハの絵にじかに触れたのは、かれこれ30年近くも前、ウィーンの美術史美術館でのことだった。ヴィーナス像ではなく、「ユーディット」という作品だったが、絵から受ける印象が強烈だったので、忘れ得ぬ出会いとなった。
ユーディット(ユーディト、ユディトとも)は旧約聖書に登場する女性で、祖国の危機に際し、敵将ホロフェルネスを訪ね、美貌を武器に誘惑し、寝所にて首を掻き、国を救った。カラヴァッジオやクリムトなど、幾人もの画家たちが同じテーマで絵を残しているので、生首を左手で押さえ右手で剣を立てた女性がどのような物語を背負うかは承知していたが、特にクラナッハの絵に目を引かれたのは、生首のリアルさも一因ながら、ヒロインの女性が毅然としており、衣装や装身具の美しさとも相まって、貴く、気高い香気を漂わせていたからだった。
みずからが剣を振るう凄惨な場をくぐってきたにもかかわらず、しかも、敵将を油断させるに至るには、実際にはきわどい色じかけもあったはずなのだが、そのような粗暴さや淫らさはつゆほどもない。返り血を浴びているわけでもなければ、衣装がしどけなくはだけているわけでもない。頬をやや紅潮させながら、顔から首筋、肩や胸にかけての肌は白く輝き、きりりと結ばれた唇からは意志の力も感じられて、何とも端正な姿なのである。
美しい。いや、美に酔える絵ではない。いくら女性が光輝に包まれようと、手元には男の生首が置かれている。血の気の退いた蒼ざめた死体の一部である。つい先ほどまでは胴体とつながり、酒を飲んで女の美貌と甘言に酔い、自身も愛の言葉を発し、この先の情事に期待をふくらませていた男の首なのだ。死してなお何かを語りかけるかのようなこの男の生首の存在が、見る者を不安にさせ、美に落ち着かせてはくれない。
クラナッハにはいくつものユーディット像がある。10点を優に超すそれらの作品では、美神を描くに、肌の露出は意識的に避けている。ヴィーナス像では、あれほどになまめかしい裸身を大胆に描いたクラナッハがである。
さらに驚くべき事実がある。クラナッハが盛んにユーディット像を描いたのは、1530年前後を中心とする。それはつまり、ヴィーナス像が立て続けに生まれたのと、同じ時期だということになる。これは単なる偶然として看過はできぬであろう。ヴィーナス像を描くクラナッハの頭の片側には常にユーディット像が存在したということなのだ。無論、その逆も然り。ヴィーナス像とユーディット像とは、車の両輪のような存在だったのである。
そのような意識のもとに、いま一度、ウィーンの「ユーディット」を見る。ホロフェルネスの首は、絵を見ている間にも、どんどん色を失い、死の影を濃くして行くかのようだ。それに反し、ユーディットのほうは、ますます輝いて行く。金色の髪も白い肌も、身にまとう帽子や衣装も含め、生はいや盛るばかりなのだ。
生と死がひとつの画面の中に、対比的に並存している。しかも、正義が不義を討つという正邪、善悪の構造の中に物語が押しこめられた分、その対比、対照のコントラストの際だちようは、鮮やかさを極める。ヴィーナス像が危ういバランスによって一身に両義性を抱えていたことに比べると、この点には差があるが、生と死をひとつの絵の中に刻そうという意欲は、相似形を描くとも言える。
かつ微妙な点は、そのように正義を全うし、その誉れに彩られた救国のヒロインに、ほのかにエロスが漂うことである。少しも裸身を晒すわけではないのに、底深いエロスが、静かに冷ややかに燃えている。死と隣り合わせだからであろうか。女性に注がれるクラナッハの眼差しの鋭さ、深さはやはり尋常でない。
視点を少し変える。クラナッハ作品との出会いの記憶をたどって行くうちに、意外な一点が浮かび上がってきた。宗教改革で知られるマルティン・ルターの肖像画――。
ベレー帽のような黒いかぶりものを頭に載せ、黒の僧服をまとい、意志の強そうな、土臭い逞しさを宿した顔だちのその肖像を、学生時代から歴史関係の本で何度となく見てきたが、まさかその絵の作者が妖艶な裸婦を描いたかのクラナッハであるとは、当時はもちろん、ヴィーナス像の作者として着目して以降も、しばらくは気がつかなかった。
実は、クラナッハはルターと親交をもち、終生変わらぬ敬意を寄せた。おびただしい数のルターの肖像画を描いたのみならず、妻や両親など、家族の肖像もものした。
妻のカタリナ・フォン・ボーラは、もともとカトリックの修道女だったが、26歳の時に修道院を飛び出し、41歳のルターと結婚した。ルター夫人の肖像画は、夫と対になって描かれる。ルター像はほとんどが右手を向いた半身像であるが、夫人像は、夫と向き合うように、必ず左を向く。
女性を描くにひと癖もふた癖もあるクラナッハである。このルター夫人をどのように捉え描いたのか、大いに気になるところだ。私自身は、代表的な作品例として知られる、フィレンツェのウフィツィ美術館所蔵のものを見る機会に恵まれたが、これがなかなかに感動的であった。
宗教者の妻であるから、服装は地味である。ユーディットのような華麗な装いはない。だが、その代りというように、画家はひたすら夫人の人間性を真摯に見つめる。背景もない画風は、どこか近代絵画を先どりしたような感がある。意志の強さ、誠実さ、おのれの信ずる道を行くすがすがしさなど、飾りものとは違う主体的な女性が生き生きと活写されている。エロスこそ遠ざけられているものの、ヴィーナス像にもユーディット像にも共通する凛とした芯の強さが輝いている。
言うまでもなく、ローマ法王を頂点とするカトリックは、聖職者の結婚を認めなかった。当然ながら、ルター夫妻は非難を浴びた。だが、長い間の懊悩を経て、ルターは強いて禁欲を積むことでは神に近づくことができないことを悟っていた。偽善を離れ、むしろ愛欲を自然の摂理と認めたほうが、神の道に生きることを容易にすると信じた。結婚はその信念の実践であり、よき伴侶を得て迷いなく信仰に専心するための跳躍でもあった。肉体を伴う男女の愛は信仰の妨げとなるものではなく、信仰を全うすべきものとされたのである。
ルターはしばしば東の宗教改革者であった親鸞との類似性が指摘される。親鸞は「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」と説いて、すべての衆生が仏法による救済の対象であるとした。おのれの至らなさの自覚が思想の根本的出発点であり、その延長上に、女人も往生が可能だとした。かつ僧侶の妻帯を可とし、みずからも結婚した。
既存の宗教に不満を抱き、革命的実践に身を投じた東西の宗教改革者が、ともに男女の性愛を肯定したことは、いくら強調してもしたらない真理への一大ステップであった。人間の本質を、その赤裸々な実相を、凝視、把握する眼差しと熟慮が、変革をうながす動力をふくらませ、火山のように爆発させたのだ。
そして、ヨーロッパの北側で性愛をめぐる意識や思想上の大転換が行われつつあった時期に、他でもない、ルターと親交の深かったクラナッハが、独自のヴィーナス像を描き続けたのである。宗教改革という地殻変動をうながしたマグマは、画家の体を流れる血潮にも沸き立つ火照りを与え、創作意欲を焚きつけてやまなかったはずである。
一見、まるで関係がないかに見えたクラナッハのルターの肖像画とヴィーナス像は、時代潮流に棹をさすひとつの船に乗っていたのである。
ベルギー王立美術館が所蔵する、蜂蜜泥棒のクピドを伴うヴィーナス像には、画面の右上に、ラテン語による書き込みがある。ラテン語には暗いが幸い英訳が見つかったので、以下私訳してみる。「クピドがミツバチの巣箱から蜂蜜を盗めば、蜂は盗人の指を刺す。同じように、我らが束の間の危うい楽しみを求めようとすれば、楽しみは哀しみにまみれ、我らに苦痛をもたらす」――。
もとはギリシャの詩人テオクリトスの詩「蜂蜜泥棒のクピド」の一節だというが、このオリジナル詩があればこそ絵の構成が定まったわけで、詩句の引用が解説の役目を果たしていることは明白である。
一見、窃盗を戒める教訓のように感じられなくもないが、詩句の後半ははるかに意味深長である。すなわち、この世に危険な快楽が存在することを認めている。刹那的には甘美極まりない悦楽がやがて切なさや空しさと化し、苦痛が押し寄せることになると、純白の裸身を輝かす愛の美神の微笑みに、警句が添えられたのだ。悦楽と苦痛は愛の変容の相関指数だと喝破したのである。
私は先に、ティツィアーノに代表される裸婦像の典型が、しばしば対となるものを備え、かたえとなるものを伴うことを指摘した。かつまた、そうした伝統の王道から見れば脇道にそれたところに花開いたクラナッハのヴィーナス像が、両性具有的に対となるものを一身に抱え込んでいるとも述べた。そうなのだ。クラナッハの愛の美神は、悦楽と苦痛をひとり身に抱えた危うさの中に妖しく発光し、照り輝いていたのである。
そう思って、パソコンの中に美人画の屏風のように並べ立てたヴィーナス像を、改めて熟視する。実を言えば、このような鑑賞法を思いついたのは、クラナッハのヴィーナス像に、直観的に川端康成の『眠れる美女』との均質性を感じ、久しぶりに、この風変わりにして緻密な小説を読んだことが影響している。
『眠れる美女』の主人公の老人は、睡眠薬を飲んでぐっすりと眠らされている裸身の若い女性と、同衾し添い寝をする。もの言わぬ、陶器のような裸身の女性との奇妙な交流に老人は癒され、黄昏ゆく人生のもの淋しさの中、鮮やかに生を実感する。
また、添い寝をする間に、自身の半生に現れては消えて行った女性たちとの記憶が風の訪(と)うように蘇り、その濃密さに陶然とする。老人はそのような夢うつつの体験を5回、6人の女性ともつが、睡眠薬の過度の飲用がたたって添い寝をしていた女性が突如として死んでしまうことで破局が訪れ、終幕となる。
私は『眠れる美女』のこの老人と、いや老人を通してこのような夢魔を紡いだ川端という作家と、妖しきヴィーナス像を描いたクラナッハとに、共通の音楽を聴くような気持ちになる。枯れ野を渡ってくるひとすじの笛の音のような、あるいは、掌から銀の砂がこぼれるにも似て、天から降り落ちてくる金属の乾いた音のような、そうした妙なる音を聴くのである。
どちらの作家も、途方もない虚無の荒野を背後に抱えている気がする。死の淵にあって、カミソリの刃のような鋭さで生を刻している気もする。研ぎ澄まされた芸術家の眼差しが凝視することで、熾火(おきび)のようなわずかな燃えさしが、魔法の酸素を吹きこまれた如くに、あかあかと燃えたつのである。
寡聞にして、川端康成にクラナッハを語った文章があるとは聞いたことがない。東山魁夷を始め、画家との親交も厚かった作家である。生涯、透徹した眼差しで女を描き続けた天才作家に、クラナッハの裸のヴィーナス像を並べ見せながら、尋ねてみたい気がする。
「駒子(『雪国』)はどのヴィーナスです? 太田夫人(『千羽鶴』)は? ひょっとして、これが菊子(『山の音』)? このヴィーナスはどの小説のヒロインでしょう?」――。
ぶしつけな訊き手を、鷹を思わせる鋭く怜悧な目でぎろりと睨みながら、はて川端は何と答えるだろうか。