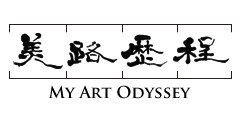

「月日は百代の過客にして」とは『奥の細道』の書き出しであったが、なるほど生きるということ、日々齢を重ねるということは、現在を過去へと送り、何がしかを次々に失うことにほかならない。その意味では誰の人生にも喪失はつきものだが、運命によって、また時代や社会環境、自然災害等によって、喪失は時にある人々に過度に集約的に押し寄せる場合がある。
マルク・シャガールという画家も、複層的な要因や運命によって、度重なる喪失を背負った人だった。まず彼はユダヤ人だった。生まれ育ちは白ロシアの田舎町、ヴィテブスクのゲットーである。祖国喪失者としてのユダヤという出自に加え、ロシア革命で伝統の社会と暮らしは断ち切られ、その後第2次世界大戦でのドイツとの戦争によって故郷の町は破壊されてしまった。彼は革命後にロシアを脱して、留学経験のあるパリに移り、やがてナチスの手を逃れてフランスからアメリカへ渡った。
家族の不慮の死も重なった。ヴィテブスクにいた頃、幼い弟や妹の死は若き日の画家に忘れがたい大きな影を与えた。そして、極め付けとも言える喪失の悲劇は、アメリカに渡って3年後の1944年、ヴィテブスク以来、最愛の伴侶として日々をともにしてきた妻のベラを急病で失ったことだった。駆けつけたニューヨークの病院はカトリック系で、ユダヤ人の入院を拒否したために手当てが遅れ、死去したとも伝えられる。20世紀はこの人の人生に幾たびもの別れを強い、喪失の哀しみを味わわせた。
恥ずかしくも、私は高校生の頃に初めてこの人の絵に触れて以来、しばらくはフランスの画家だと思い込んでいた。「色彩の魔術師」とか「愛と幻想の画家」などという形容も、パリの華やぎこそがふさわしいと信じて疑わなかった。その人の生い立ちがロシアに根を持つことを知ったのは、長く外の世界に対して閉じられてきた初期のシャガール作品を、ペレストロイカを機に公開し始めたモスクワのトレチャコフ美術館から多くの作品が寄せられた、1989年のシャガール展(Bunkmuaザ・ミュージアム他)がきっかけだった。
キュビズムの影響が濃い、そしてユダヤの村の色や匂いに満ちたそれら初期の作品群は、全く新しいシャガール像を開かせてくれた。以後、シャガール作品に接するに自己流の流儀が生まれた。画面のどこかに描かれた、故郷ヴィテブスクの面影を探すのである。丸い屋根を戴く教会を中心に家々がひしめき、人々の営みのぬくもりを湛えた素朴な町並は、気をつけて見れば、ロシアを去って以降の絵にも頻繁に登場する。シャガールと言えば誰もが思い浮かべる鶏や牛、ロバなどの動物やヴァイオリンを弾く楽師なども、故郷の町並みと離れがたく結びついて画面に繰り返し現れるイメージなのだ。
しばらくはヴィテブスク探しが続いた。が、やがて私なりの視点、評価が定まった。それは、シャガールの絵とは喪失者が描く故郷の追想にほかならないということだった。愛し合う恋人たちも故郷の町並みも動物も音楽も、すべては喪失者の夢想の中に刻印された永遠の輝きなのである。逆に言えば、シャガールの筆によって、胸に刻まれた記憶の中の命の輝きが、永遠の像に結晶するのである。
その絵はしばしば「色彩の魔術師」と評されるが、私に言わせれば、シャガール・マジックとは、イタコの口寄せではないが、亡き人、亡き風景、過ぎ去った日々を永遠に枯れることのない輝ける命に蘇らせる、その蘇生復活の術にこそ存在する。ロシア時代に描かれた絵にしても、それは過ぎ去る定めのものを愛おしむ郷愁に裏打ちされている。ベラとの愛の渦中から紡ぎ出された絵のように、盛りや華やぎのさなかにあってさえ、作品はどこか移ろい、果ては滅びの予感をまとっている。すべからく「モータル(mortal=逝く身の)」な命であることを、シャガールはとうに知ってしまったかのようなのだ。
哀しみを秘めながら、しかしシャガールの絵の多くは暗さに沈んでいない。むしろ明るい光の中、歓びに溢れている。シャガール自身が絵を描くことで救済されているのだろう。無論、彼ひとりが救われるわけではない。その作品に触れることで、喪失の痛みを抱える者はその傷を癒し、失われた愛や大切な人の記憶を今一度しかと確かめることが可能になる。
最近ふと思うのだが、喪失者の福音としてのシャガールのしかるべき絵を、東北の被災地に寄贈する人は現れないだろうか。失われた多くの命や風景の記憶を風化させず、永遠の命として愛おしむ力の泉となるに違いないと思うのだが……。