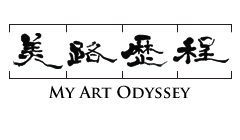

20年ほど前、地中海に浮かぶマジョルカ島を訪ねたことがある。ショパンが「雨だれ」前奏曲を作曲した修道院など、名所を訪ねる過程で、パルマ市郊外のミロのアトリエにも寄った。
ミロ(1893〜1983)がカタルーニャの人であり、バルセロナにミロ美術館があることは承知していたが、マジョルカ島にミロの拠点があるとは知らず、予想外の場所で意外な宝物に出会うような気がした。
広いアトリエにはイーゼルやパレットなどが生前のままに残され、ミロの制作現場を目の当たりにする興奮に駆られたが、眼前の事物に気がとられ、ミロが何故マジョルカ島にやって来たのかという点には、思いが至らなかった。
私が訪問したアトリエは1956年に出来たものだが、ミロがマジョルカ島に拠点を求めたのはそれより早く1940年のことで、20世紀の激動の歴史に翻弄された流浪の果てのことだった。
1936年にスペイン内戦が勃発。フランコ独裁に反対したミロは、バルセロナからパリへ移る。1939年の夏に、ノルマンディーのヴァランジュヴィル=シュル=メールにあった友人の家に滞在、当初は夏だけの予定だったが、英仏の対独宣戦布告により危険を感じ、そのままこの家に留まる。
ところが1940年5月、ドイツ軍の北部フランスへの侵攻が始まり、ミロは故国スペインへ戻ることとし、バルセロナは危険なので、7月に母の故郷のマジョルカ島へと落ちのびた。つまり、ファシズムと戦禍を逃れ、避難した先がマジョルカ島だったのだ。
本人の弁によれば、ミロは生来のペシミストで、鬱を溜めこむタイプだったというが、欧州全体が戦争の暗雲に覆われたこの時期、心は暗く、重かったに違いない。鬱が昂じ、恐怖と絶望の淵に沈みそうになる心模様を救ったのは、ヴァランジュヴィル=シュル=メールで描き始めた『星座シリーズ』の絵画だった。
男や女、様々な動物や鳥、星や天体など、いずれの作品も、この世の森羅万象を記号化し、線と色で構成したような趣である。詩を思わせるイマジネーションに溢れ、画面の奥から音楽が聞こえてきそうな澄明なリリシズムを湛えている。一見、野放図で無秩序に見えるが、よく見ると、生命の統合体として宇宙的な秩序を保つ、調和の世界が構築されている。
ミロはヴァランジュヴィル=シュル=メールで10点を描き、トランクにそれらを詰めてマジョルカ島に渡ってから10点を描き、さらにその後、1941年にバルセロナ近郊のモンロッチに移って3点を描いた。「戦禍を逃れながら、夜や音楽、星を着想源にして23点を描いた」と、後にミロは回想している。
スペインではナチスの支援を受けたフランコ独裁体制が続き、ミロはその間、国内では隠遁者同然に暮らさざるを得なかった。ミロの作品はアメリカで評判をとり、20世紀を代表する芸術家として認識されて行ったが、亡命もせず、スペインの片田舎に留まった画家自身は、時代の閉塞に呻吟しつつ、作品を描くことで生をつないだのである。
さて、この3月から、東京都美術館でミロ展が開催中である。『星座シリーズ』から3点が出展されていると聞き、早速足を運んだ。『星座シリーズ』はすべて紙にグワッシュで描かれ、サイズ的には38×46cmと小ぶりである(だからこそトランクに詰めて逃避行が可能だった)。
今回の3点は皆ヴァランジュヴィル=シュル=メールで描かれたものだが、そのうちの『明けの明星』は、タイトルも含め、特に私の胸を打った。この画面の中にどれだけの生命のモティーフが描きこまれたのかと、記号のような線の模様を、飽かず眺め続けた。
戦禍が迫り、破壊と殺戮の狂気が世界を覆う時代に、ミロは画面の中に確かな生命の宇宙を構築したのである。それは、波のように押し寄せる終末の予感に抗い、世界を再認識し、生命溢れる本然たる世界の回復を試みたものだった。
不思議なことに、ここには悲惨や苦渋は現れず、むしろ希望が、祈りのように美しく結晶している。制作から85年、新たな時代の危機のさなかに、ミロの祈りは、文字通りの「明けの明星」として、輝いてやまない筈である。