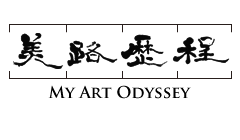

写真で馴染んだ絵に、実際に生で接してその印象の差に驚くといったことは、何度となく経験してきた筈であった。だが久しぶりに、真作の絵に触れて、衝撃を覚えたのである。昨年12月、台湾は嘉義の市立美術館で、陳澄波(1895~1947)の自画像に接した時のことだ。
陳澄波は、日本統治下の台湾に育ち、東京美術学校在学中の1926年に、台湾人として初めて帝展に入選した洋画家である。嘉義は台北から汽車で3時間半ほど南に下った中都会だが、この町で生まれ育った陳は、やがて東京に出、さらには上海にも暮らすなど、旅路を重ねたのだった。
嘉義には彼の生家がなおも残り、市内の公園には、陳澄波の絵のパネルがプロムナードのように飾られていると、その程度の情報だけで出かけたので、実作品にどこで会えるか不明であった。で、ともかくも市立美術館を訪ねた。
すると、「此岸彼郷」と題して、陳澄波と、彼と同時期の台湾人画家で前後して大陸に渡った劉新禄の絵を特集した展示が行われていた。
陳の絵は、8点が飾られていた。上海時代の絵が5点、台湾に戻って嘉義で描かれたものが3点。もっと多くの作品を鑑賞したく思ったが、個人特別展でもやっていない限り、ふらりと訪ねて、これだけの陳澄波作品を目の当たりにできたことを喜ぶべきなのであろう。
風景画が中心のなか、1点、異彩を放つ自画像があった。陳の自画像というと、周りをひまわりで埋めた1928年の自画像がよく知られているが、上海時代に描かれたというこちらの自画像は、自画像(2)と呼ばれている。この作品の前に立つや、私はそこから動けなくなってしまった。
写真では知っていた絵だったが、実際に生で作品を見て息をのむ衝撃を受けたのは、顔を中心に漲る過激なまでの激しさであった。とりわけ、鋭い眼光を放つ大きな両の目から高い鼻梁にかけて、何重にも筆を重ね、色を塗りこんだ厚塗りのさまと、やむにやまれぬといった切羽詰まった熱い情念が運ぶ筆の勢いが、私の目を釘付けにした。
俺は何者なのだ?、俺はどう生きるべきなのか?、俺の絵の道はどこにある?などと、自分自身に問いかけ、突き詰めようとする一途な求道者的態度が、圧倒的な力となって、見る者に迫るのである。
この絵が描かれたのは、1933年頃、上海滞在中であったが、その前の東京体験と、それに次ぐ中国体験によって、台湾生まれの自己のアイデンティティの問題が、輻輳的に、かつ津波のような怒涛の勢いで押し寄せていたのがよくわかる。そうした問題を、陳は能うる限り、画布にぶつけたのだ。画中の彼は冬支度だが、背景に南国・台湾の象徴である
自分は台湾のゴッホになると、陳はしばしばそう語っていたという。私はかつてそれを、画風を超えた絵描きの純粋さの覚悟として受け取ったが、実は、画風そのものも含め、彼はまさに台湾のゴッホだったのである。これは、写真では気づかぬ、生の作品による「発見」であった。
感動で胸を熱くしながら、美術館を出て、徒歩5分ほどの嘉義駅に向かった。日本時代の面影をなおも伝える瀟洒な駅舎だが、悲しみの歴史を秘める。
1947年3月25日、陳澄波は、新たな支配者となった国民党軍によって、嘉義駅前で銃殺された。「2・28事件」と呼ばれる台北で起きた台湾人による抵抗運動が全国に広がり、中国体験をもつ陳が騒動の仲介者になろうと自ら嘉義当局に出向いたところ、即逮捕され、裁判も経ぬまま問答無用で処刑されてしまったのである。無実の罪による虐殺であった。
ゴッホのような突き詰めの道の果てが、そのような死しかありえなかったのだとしたら、あまりにも悲しい。
日が暮れ、駅舎にライトアップの光があてられた。悲劇の記憶を濾過してしまったような美しい風景だが、私の瞼の底には、なおも陳澄波の自画像が焼き付き、過激なまでの一途さがいつまでも揺れていた。