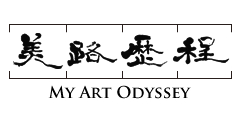

20年ぶりという大掛かりなマティス展が開催中である。パリのポンピドゥー・センターが所蔵する150点もの作品が、東京都美術館に招集された。フォービズム(野獣派)の旗手として知られ、色彩の魔術師と讃えられたアンリ・マティス(1869~1954)の画業が、日本で俯瞰できるのは嬉しい。
近現代美術の宝庫であるポンピドゥー・センターには足を運んだことがあるものの、実をいうと、私がマティスの魅力に目を開かされたのは、それより前、パリとは別の場所であった。ロシアはサンクト・ペテルブルクのエルミタージュ美術館――。北のベニスとも讃えられるこの町の壮麗な美術館を訪ねた折に、『ダンス』(1910)という作品を目にしたのがマティスとの強烈な出会いとなった。それまで頭の中に積み上げてきたルネサンス以来の美術理解がひっくりかえるような衝撃に襲われたのである。
壁画に見まがう大画面(260㎝×391㎝)に、輪になって踊る裸形の男女5人が描かれている。背景は草原を思わせる緑と、空を思わせる青で塗られた。単純化というか、素朴なさまにまずは目を奪われる。文明の成熟とともにまとうことになった余計な衣装をはぎ取り、太古の祖先返りを果たしたかのような、捨てっぷり、剥ぎ取り方の潔さに大いに感心させられた。
それは、複雑な近代社会に委縮し、疲弊した人間を、もう一度リフレッシュさせる人間復興であろうし、太鼓のリズムや楽の音、歌声に、思わず体が動き出す、野性の復権でもあろう。土臭く、たくましい生が、陽光のもとに息を吹き返す。まさに生命の爆発である。
画面を見つめるうちに、ストラヴィンスキーが作曲した「春の祭典」が湧き起ってきた。原始的、異教的な響きに満ちた革新的舞踊音楽は、1913年、ディアギレフ率いるバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)によってパリで初演され、センセーションを巻き起こした。マティスの『ダンス』とはほぼ同時期、20世紀初頭の芸術が抱えたプリミティブ嗜好に裏打ちされている。
フランスで描かれたマティスの作品がロシアにあるのは、帝政末期の大商人シチューキンが、新興美術のコレクションに熱をあげ、パリで美術品を買い漁ってロシアに運んだからだ。『ダンス』は、対となる作品『音楽』ともども、シチューキンのモスクワの邸宅に飾るため、マティスに発注されたという。ロシア革命後は、国に没収された。
ソ連政府によりいったんはモスクワの美術館に収められた『ダンス』を、現地で見た日本人がいる。1921年にイギリスに渡り、23年から10年ほどをフランスに暮らした画商の福島繁太郎である。マティス本人とも親交をもった福島は、『ダンス』の印象を次のように綴っている。
「構図も物の形も色彩も極めて簡単、恐らくマチスのすべての時代を通じて、単純化の最も極端に迄進められた時代の作品であろう。自然の奥行を無視して平面化し、人体の輪郭を線で包み、その中をほとんど明暗のない一色で平塗りに塗り潰している。人体は赤、其の輪郭は黒の太い線、バックはウルトラメールという大胆なコントラストを以って、遠目のきく強烈な効果を出している。 マチスは此の作品に於て、彼の生涯の画業の方向をはっきりと示している。即ち線と色彩、ことに主として色彩をアラベスク(アラビア模様)風に組み合わせ、色彩の豪華なるシンフォニーを作ることである。(『エコール・ド・パリ 1』(1948)――。
後に、特徴的な赤色の用い方から明代陶磁器の「万暦赤絵」のようだとも言われたマティスだが、『ダンス』では、色彩的にはむしろ抑制的である。しかし、少ない色彩のコントラストが放つ鮮やかさは、既にマティスらしさを存分に発揮している。
東京都美術館でのマティス展に来日した作品の中に、『イカロス(版画シリーズ『ジャズ』より)』(1947)という切り絵による作品があった。単純なフォルムの中、踊り手がしなやかに舞い、人間の解放が謳われる……。ふたつの世界大戦を含む40年近い歳月を経て、マティスはなおもマティスなのである。
踊る人の自由な動きとともに、活き活きとした喜びがこみ上げてきた。