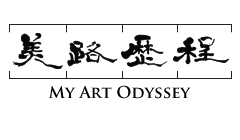

シーレの風景画について、さらに書く。
南ボヘミアのクルマウ(現チェスキー・クルムロフ)が母の故郷にあたり、1910年以降、シーレがたびたび足を運んだことは既に記した。
シーレ自身はこのモルダウ川沿いの古く小さな街に愛着を覚えたが、モデル兼愛人のヴァリーとの放恣な同棲生活、そして少女をアトリエに引っ張り込んでは裸体画を描いていたことなどに住民たちが反発、シーレとヴァリーは追われる者の如くに街を去った。
しかし、シーレのクルマウへの愛着はやまなかった。そこに暮らした当時はもちろん、それ以降も、繰り返しクルマウを描いたのである。小さな町の同じ素材から多くの作品を生み出してくれたお陰で、シーレの風景画について、深く考えさせられることにもなっている。
シーレがクルマウを描くようになった当初の、街に向き合う画家の気持ちが如実に表れているのは、『死せる街(死の街)』と呼ばれる一連の風景画である。1910年から12年にかけて、同一のタイトルで6作品が描かれた。
そのうち、最もよく知られた『死せる街Ⅲ』(1911 レオポルド美術館)を見てみよう。クルマウで描いた風景画のうち、最もメジャーな視角となった、城山(シュロスベルク)から川の向こう岸を俯瞰した眺めである。
Uの字を描く川に囲まれて、黒い水面に浮いたような街。屋根と壁だけでくるむように構成した画面に、人は全く登場しないが、画面上方に洗濯物が干してあるので、かろうじて人々の生活する街であることが知れる。
だが、街区の家々を無理にもキャンバス空間に押し込め、袋詰めにでもしたような、息詰まる窮屈さ、重苦しさが画面を覆う。色彩も極端に抑制されている。裸にされた(nakedな)街の「真空パックとでも言おうか……。
それぞれの家のひしゃげた描き方から、キュビズムとの関連を指摘するのはたやすい。しかし、そういう様式の問題を超えた、鋭い内面的問いかけがある。セザンヌを発展させるように20世紀に産声を上げたキュビズムは、徹底して客観的に見ることが基本だった。対するに、シーレの場合、主観的で、感情や情念がそこに託された。心理的な裏付けと無関係に、シーレの建物描写、風景画は成立しない。
クルマウを「死せる街」として描くのは、ほかでもない、シーレの心の目に、そのように感じられたからだ。石もて追われる身とならざるを得なかったこの街との不幸な運命が、生の記憶を閉じ込め、すべてを石化してしまったかのような抜け殻の死の街をシーレに描かせたのである。
とはいえ、シーレにとってのクルマウは、忌み嫌うだけの負の存在ではなかった。ウィーンの喧騒と偽善を嫌っていたシーレは、近郊の静かな田舎町には愛着を覚えてならなかったのである。
1913年に描かれた『小さな家Ⅲ』(レオポルド美術館)という作品は、クルマウの絵としては初期に属するが、『死せる街』とはかなり趣の異なる仕上がりとなっている。
2023年、年明け早々のビッグ・エギジビションとして話題を呼んだ東京都美術館の「エゴン・シーレ展」でこの絵も来日したので、久しぶりに、現物をこの目でしかと見ることができた。
川は黒々と、川中島のような街を囲むが、息詰まるほどの閉塞感や、色を封印した闇の絶望感は、この絵では鳴りをひそめ、叫びたてることをしない。むしろ、ピンクやグリーンその他、家々の壁を彩る色彩も加わり、箱庭の街を望むような佇まいに、シーレは晩秋の日溜りにそっと身を休めるかの如き憩いを見出しているかのようだ。
もっとも、ここでも櫛比する家々や路地のどこを見ても、人っ子ひとり登場するわけではない。さりとて、核戦争後の廃墟のように、絶対的な無に閉じ込められ、凍結されてしまったというわけでもない。
街のあちこちに噴き出しているはずの活き活きとした動的な営みは、濾過されたように矛を収め、「naked」な姿をさらす。街を取り巻くモルダウ川の、黒く深々とした流れに、長い時間を刻んできた歴史の変遷と、そこに絡まる沙汰のもろもろを沈めて、街は静かな午睡に息をひそめているかのようだ。
絶望一色であった『死せる街』に比べ、この絵のもつ明らかなる和みは、シーレが風景に向き合い、どのような心模様を描くことになったのか、彼の風景画の秘密を教えてくれるように思う。
風景は、シーレの孤独と魂のこだまを交わし合ってくれる存在だった。彼自身の傷心が風景と息を重ね合うことで、絶望を風景に塗りこめてしまうこともあれば、そこから、時にはかすかな希望や夢、憧れなどが、街のたたずまいに、灯りのような色を投じたり、ぬくみや和みをかもし出したりすることもあったのだ。
シーレの風景画は、自画像や裸体画、人物画を描く一方での余技などではなく、シーレが画家シーレであるがための、ひとつの「主戦場」であったに違いないのである。
シーレの父親のアドルフは鉄道員で、駅長まで務めた人物だった。シーレが15歳になる年に父は没したが、生前の仕事の関係で、シーレはオーストリア領内の鉄道フリーパスを所持していたという。この父譲りの「特権」を使って、シーレはウィーン近郊を旅してまわった。
母方の故郷・クルマウ以外にも、シーレが足を向け、そこで風景画をものした土地もあった。ドナウ川沿いの小さな街・シュタインでも、シーレは何点かの風景画を残している。東京都美術館の「エゴン・シーレ展」でも、シュタインを描いた絵が1点出品されていた(「ドナウ河畔の街シュタインⅡ」)。シュタインは、中世の面影を残し、街の周辺にはブドウ畑をかかえ、リースリング・ワインの特産地でもあった。
『ドナウ河畔の街シュタイン 南からの眺め』(1913 ノイエ・ギャラリー・ニューヨーク)は、そのなかの代表作。この1点を仕上げるためシーレは2点の習作を手掛けるなど、入念な取り組みが窺われる。
街の中心となるのは、前後してたつ二つの教会である。それぞれの教会の塔の上部には、鐘であろうか、丸い球体のものが見える。とりわけ、奥の教会の尖塔の先の青い球体は、まるで眼球か何かのように、街を睥睨しているかに見える。
私はこの絵を見た時、咄嗟に、ルドンの描いた、空に浮く眼球の奇想の絵を思い出した。シーレのこの絵では、あからさまな奇想や幻想の姿をとらぬものの、一見したところ、百年も変わらぬ暮らしを続けるかに見える静かな古い街にあって、心象的なヘソを形成している。
教会の鐘が、周囲に響く唯一の音なのであり、街の時を刻み、街人たちの暮らしを
ただ、いつもと違ってというか、このシュタインの街の風景画で顕著なのは、街の背後にひろがるブドウ畑の鮮やかな緑である。そこには、生命力の圧倒的な発露があるわけだが、緑が街を潤すというよりは、丘の上から威圧するように描かれている点に、シーレならではの心理の屈折がある。玄妙なる緑とでもいうか、いささか過剰な緑の横溢によって、貴腐ワインではないが、生が熟しすぎて不安を嵩じさせている。
静かな田舎町を舞台に繰り広げられる生と死の拮抗、葛藤が、シーレの胸とこだまを交わして、濃密な無言劇を演じているのだ。
真夏の白昼の動かぬ空気を刺し通すように、やがて、教会の鐘が鳴る。鐘の音は、街全体に響きわたり、ブドウ畑にこだまし、ドナウの川面に吸い込まれてゆく……。
東京都美術館の「エゴン・シーレ展」では、シーレの風景画についても主要な柱のひとつとして扱っており、クルマウを描いた『小さな街』シリーズからは2点が出品されていた。
先の『小さな街Ⅲ』に続く、『モルダウ河畔のクルマウ (小さい街Ⅳ)』(1914 レオポルド美術館)――。例によっての、川向こうの街の俯瞰図だが、1911年に描かれた『死せる街』に比べると、絶望的な嘆きはだいぶ後退している。
建てこんだ黒い屋根のつらなりと壁や通りの白というベーシックなモノトーンのなかにも、黄色やピンク、青や緑など、いくつもの明るい色が散見される。色彩感は、前年に描かれた『小さな街Ⅲ』よりもさらに明るく、輝かしい。
そのせいか、街のたたずまいは、どこかメルヘン調な赴きを呈する。壁や軒、煙突や窓など、処々に置かれた明るい色の点や面が、あたかも土のうねの端々に咲いた可憐な野の花の如く、或いは、モノトーンのマシーンの隅々に灯るデジタル・ライトの如く、不思議な華やぎを放っている。誰もいない不在の街で、各所に配された色彩から、小鳥のような声が聞こえてくるようにさえ感じる。
一方で、白壁の家々は、紹興酒の産地か、染め物の里か、中国奥地の古い街のように見えてもくる。シーレにも、明らかなオリエント志向があったので、東方への夢を重ねていたと言えなくもない。
相変わらず、人の姿は画面には登場しない。しかし、興味深いことに、この絵では、人の営みは否定されていない。箱庭のような街の家々の奥で、人は今日も今日とて働き、憩い、夢を紡いでいる。食事をし、会話を楽しみ、愛を語らい、性の交わりにも及ぶ……。
その動静の気配を感じながら、シーレは遠くから静かな微笑みを寄せているように思える。ひたすら嫌悪と呪詛をつのらせ、恐怖を叫んでいた『死せる街』のシーレは、ここにはいない。
やはり、シーレのクルマウの絵は面白い。定点観測のように、同じ場所を、年ごとに、何点も描いているので、作品による微妙な差が、若き芸術家の魂のありよう――成長や変化を語ってやまないのだ。
1年に季節があり、冬には枯れた木々の葉が再び春には芽吹くように、シーレのクルマウの絵にも、季節があって、作品ごとに、死と再生を繰り返していたように思えてならない。
そのような思案の上に、最後に今一度、『クルマウ、三日月型の家々 Ⅱ(島の街)』(1915 レオポルド美術館)に立ち返ってみよう。おなじみのクルマウの定点観測の絵だが、一見して、色使いの多様さが目立つ。
川沿いの街路樹もすっかり色づいて、鮮やかな輝きを見せる。川向こうの大地には、うねるような地脈を縫って緑が帯を作る。生命はなかなかに盛んなのである。
この絵が描かれた1915年といえば、シーレは、モデルのヴァリー・ノイツェルと別れて、中産階級の娘のエディットと結婚した年である。或いは、私生活上の決意と転身も、クルマウを望むシーレの心に、それまでとは異なる生命力を与えていたのかもしれない。
だが、それでいて、やはりこの絵は「晩年」の絵だ。
再生を願いつつ、一方ではその虚しさをとうに察知してしまった人の孤独が透けている。クルマウの街区を囲む、モルダウ川の黒々とした水面は、人の胸に湧く小さな夢や願いを知ってか知らでか、滔々と流れゆく。
希望は常に、諦念と
年を重ねるにつれ、シーレの描くクルマウの街は、酸いも甘いも嚙み分け、生に死を溶かし込んだような、独自の高みに達していったのである。