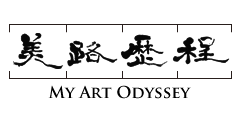

部屋の壁に穿たれた格子窓がある。今、窓外を牛が通る。頭が、角が、四肢が格子窓を過ぎて行く。だが、最後に続くべき尾だけが、いつまでたっても窓に現れない。いったい、どうなっているのか……。
気の早い読者は、マグリットのどの作品だったかと、画集を開き始めたかもしれない。外界に向け開かれた窓や額縁、キャンバスは、マグリット作品にしばしば登場する。窓の前に置かれたキャンバスが背後の風景とぴたりと重なるかのような光景を映していたり(「人間の条件」)、割れ落ちた窓ガラスの破片に風景が残っていたり(「野の鍵」)と、謎かけの重要な演じ手だ。では、窓と牛によって仕掛けられた謎はいったい何なのか……。
実は、今私が提示した牛のイメージはマグリットではなく、禅の問答(公案と呼ばれる)を集めた『無門関』の第38則、「牛過窓櫺(ごかそうれい)」なのである。「五祖曰く、譬えば水怙牛(すいこぎゅう)の窓櫺を過ぎるが如き、頭角四蹄都(すべ)て過ぎ了り、其麼(なに)に因ってか尾巴(びは)過ぐることを得ざる」――と、漢文を書き下せば、このようになる。
「窓櫺」とは格子窓のことだが、敢てひとつとせず、横並びの連格子の窓としたほうが、よりマグリット的かもしれない。4つの額縁で景色を分断した「風景」や、女性のヌードの全身立像を、頭、胸、腰、膝、足と、5つのパーツに分けて額に入れた「永遠の明証」など、分割、分断による仕掛けも、マグリットがヴィジョンを開く鍵として重んじたからだ。
それにしても、「牛過窓櫺」の何とマグリット的であることだろうか。驚いたことに、マグリットは牛ではなく馬を使って、似たシチュエーションを作品にしている。「白紙委任状」――。林の中、木々を縫って馬上の貴婦人が行く。木によって遮られて見えないはずの姿が見え、逆に、遮蔽物もなく見えるはずの部分が、透き通って緑の森になっている。馬の足を見ていると、遠近法すらもこんらがって、目も意識もくらくらしてくる。そうだ、すべての常識は崩れ、白紙にならざるを得ないのだ。常識を白紙にすること――それこそがまさに、禅の公案の基本でもある。

そもそも禅の問答(公案)とは、師が弟子に問いを与え、弟子はそこから悟達への契機をつかむことを目的とする。答えは一様でない。各人が各様に悟りを開くため、一般的な解釈や概念を打ち破り、異なる視点から独自に世界を見ることが求められる。つまりは常識の否定が出発点となる。ここがマグリットと一致する。
「これはパイプではない」と記されたパイプの絵(「イメージの裏切り」)はあまりにも有名だが、常識からすれば、ただのパイプの絵でしかない。だが、そこに強引に言葉を付与されたことで、疑義が生じる。これは本当にパイプなのか。光の加減か何かで、違うものがパイプらしく映っているだけではないのか。ひょっとして、パイプらしい形に仕上げたチョコレートかもしれない……。常識を疑うことから、新たなヴィジョンが生まれる。
やはり禅の公案をまとめた『碧巌録』の第53則「百丈野鴨子(ひゃくじょうやおうず)」も、妙にマグリット的だ。馬祖が弟子の百丈と歩いていると、野鴨が飛び立った。「何だ?」と問う師。「野鴨です」と答える弟子。「どこへ行ったのか?」。「わかりませんが、空を飛んで行くのです」。すると師はいきなり弟子の鼻をつまみ、ひねりあげた。悲鳴を上げる弟子に向かって師の曰く、「飛んで行ってなどいないではないか(野鴨はここにいるではないか)」――。それを聞いて、百丈は悟りを得たという……。
飛び立つ姿を見たと信じていた野鴨だが、実は何を見たのであったか。飛んで行く先もわからぬまま、もっともらしく「見た」と語ることが許されぬのか。あるいは野鴨ははなからここにあって、動いていなかったのか。そもそも、野鴨が飛ぶと見たは自分の心の動きの現れであって、そのことを自覚していなかった自分の無明に、はたと気づかされたものだったか……。
師の言葉をマグリット流に言い換えれば、「あれは野鴨ではない」となろうか。そういえば、羽を広げ飛翔する鳥もまたマグリットの絵に特徴的に登場する。暗鬱とした海原の彼方、重い灰色の空を背景に飛び立つ大きな鳥(「大家族」)は、鳥の形の部分にだけ切り絵のように青空と白い雲が透けている。「百丈野鴨子」と響き合う何がしかを感じないではいられない。

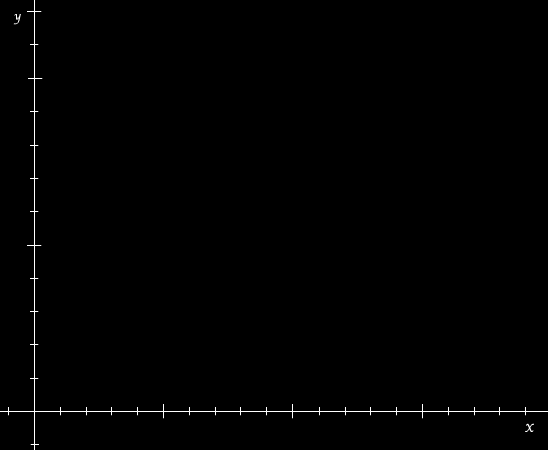

『無門関』の第35則、「倩女離魂(せいじょりこん)」も摩訶不思議な話だ。倩女には相思相愛の男、王宙がいたが、親に結婚を反対されて駆け落ちした。子供もでき、そろそろ許してもらえるかと家に戻れば、そこには自分とうり二つの女が病で寝込んでいた。男と家を出た日から臥せっているという。病に臥せっていた倩女と、駆け落ちした倩女、さてどちらが本物なのか……?
この話を、女は魔物なので仏の道に精進する身には障りとなる、注意すべしと、そのような教戒の次元でとらえてはいけない。遥かに高次元のところで問答が発せられている。恋に生きた女と、影法師のように臥せっていた女と、どちらが本物かと尋ねているのだ。いや、正確に言えばどちらが影法師かさえ不明なのだ。自分は何者か、おのれのアイデンティティーが足元から揺さぶられているのである。
マグリットには人物の後ろ姿を描いた作品も多い。例によって山高帽の紳士が後ろ姿で登場する絵も少なくないが、その中でも「小学校教諭」は、遠い夜の町を背景にして、まさに男がバックショットで立つだけである。タイトルは小学校教師だが、その実、何をやっている男か、知れたものではない。実は大統領かもしれないし、稀代の悪漢かもしれない。いや、そういう「ジキルとハイド」的な二面性が問題なのではなく、平凡な小学校教師にも、そんじょそこらのドラマも顔負けの劇的な恋の物語を秘めているということなのかもしれない。
後ろ姿の女性版もあった。海原を背景にして立つ、腰まで届く長い髪をした裸の女性のバックショット。「夜会服」というタイトルが効いている。社交界のパーティーで皆の視線を集める着飾った夜会服の女と、誰もいない海原を前に素っ裸で立つ女と、まさしく「倩女」的な対立の中に、鋭くアイデンティティーが問われている。
さらに言えば、この絵ではこの裸身の女性を見る者(どうしたって男だ!)の存在も匂わせている。つまりは「倩女」のミステリーに当惑しつつ、そのエロスに惹かれてやまない「王宙」の、そして絵を前にした「私」の男心までが張りついて、三角関数を複雑化している。謎を解く鍵のように、またこんがらがった秩序を統(す)べるように、天空の三日月が清冽な白い光を注いでいる。

私はマグリット絵画を見るひとつの視座として、禅の公案と重ねることを試みてみた。そうすることで、マグリットの仕掛けた謎の大海に、より深く測深鉛をおろすことができると思うからである。また、マグリットの問答が、デジタル的遊戯による電脳快楽のレベルではなく、禅に匹敵するくらいの人生の根本問題として発せられていると信じるからである。
禅問答(公案)の目的は、その逸話や問いによって、それまでの惰性の中では不可視であった真実に覚醒し、悟りを開くことにある。ただ、その悟りは「不立文字(ふりゅうもんじ)」といって、文字では表せないとされる。厳しい修行を通して、各人が心の中に答えを見出すしかないのである。マグリットにも、常識を超えた先の地平線を目指す求道性がある。この世を統べる真理を解く鍵を、これまでにない新たなアプローチで提示しようとする生真面目さである。山高帽の男の後ろ姿など、荒涼とした中を神秘の泉へと歩み行く聖者に見えることすらある。
ところで、諧謔や機智、シニシズムなどの乾いた次元でマグリットの絵画を見ているうちに、いつしか自分でも驚くくらい、絵の発するポエジー(詩情)に打たれていることがある。先にあげた「夜会服」の絵なども、不可思議を扱いながら、どこか静謐な詩情が漂う。今回のマグリット展で、若い日には気づかなかったさまざまな発見があったが、いかにも理知の人に思えたマグリットが時に見せるこの意外な詩情についても、現場でたびたび唸らされるところとなった。
禅に引き寄せて言うなら、マグリットの詩情とは、「不立文字」の悟りの淵にほの光る精神美学なのではあるまいか。マグリットの詩情を語るに最もふさわしい絵は、「光の帝国」であろう。本来は別のものであるはずの昼と夜が同じ空間にともに存在する。その意味ではデペイズマンなのだが、昼夜の組み合わせに少しも不自然さがなく、衝撃よりも調和と静謐な安らぎを醸し出す。すべての迷いや不安は、ここには存在しないかのようだ。
『碧巌録』の第46則は「無寒暑」といい、暑さ寒さのない世界が提起される。寒い時には寒さを殺し(寒さに徹し)、暑い時には暑さを殺せば(暑さに徹すれば)、暑さ寒さのない世界になると説く。夏には暑いとこぼし、冬には寒いと愚痴りがちな怠惰な心を超越し、自在な境地に生きよということなのだろう。暑さ寒さをなくす心持ちと、昼と夜をともに抱える意識とは、相通じ合わないだろうか。相反するものをともに見、ともに心に抱えることができたならば、精神の自由に達し得るであろう。対立や混然を超えて、この世を統べる新たな秩序に行きつくのではなかろうか。
光の帝国の安らかさは、どこか既視感をも湛えている。世界の神話を見ると、創世の頃、この世がまだ昼と夜に分かれていなかったとする例が見られるが、そのような、ひょっとしてあったかもしれない、昼夜という時間の物差しが出来ていなかった太初の光景が、現代の都会の片隅にもひっそりと息づいているのだ。何物にも束縛されない原初的な荒野こそが、複雑な文明の果てに生きる私たちが精神の自由を獲得する新天地ということであろうか。
マグリットの詩情は、絵画だからこそ可能であった。だが、当たり前のこととはいえ、美術は美術だけに成立するわけではない。人々はどこかで美術は美術、文学は文学と、棲み分けしがちだ。マグリットはそうした人々のルーティン化した概念や習慣にも、鋭く異を唱えているのだろう。