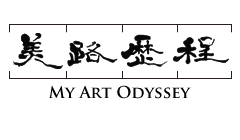

「私の描きたいのはバレリーナではなく、動きと美しい布だ」――。
「私が興味を覚えるのは、動きをとらえることと、美しい衣装を描くことだ」――。
どちらもドガ自身の言葉である。ドガと言えばバレエ、バレリーナの絵と連想が働くほどに、切っても切れない表看板となったわけだが、画家自身の言葉によれば、興味の本質は「動き」と「衣装(チュチュ)」であったという。
このうち、バレエを別として、動きへの関心を示してやまないのは、ドガが残した多くの競馬の絵である。油絵だけでも45点にのぼる。
キャンバスを外に持ち出し、美しい自然と溢れる光の中で描くことを提唱した印象派の中にあって、ドガはバレエやオペラ座の絵に顕著であったように、都会のインドアを舞台に絵を描くことが多かった。野外制作などもってのほかで、絵は必ずアトリエで仕上げられた。田園派でなく、あくまでも都会派だったのでる。
そういうドガにしては、ユニークなアウトドアのテーマとなったのが競馬であった。ただ、屋外ではあっても、田園ではなかった。競馬は近代の成立とともに、都市ブルジョア層の躍進によって人気を集めた娯楽。あくまでも都会生活の花だった。
競馬を描いたドガの作品のうち、私のお気に入りは、オルセー美術館が所蔵する『観覧席前の競走馬』(1866~68頃)――。
この作品が伝えるのは、レースの始まる前の光景。ドガは必ずしも進行中の激しい動きにのみ関心があったわけではない。この絵が身上とするのは、静と動の交わる緊張の瞬間である。
中央奥の馬には、身をよじって騎手を振り落とさんとするかのような激しい動きが見られる。他の馬は押しなべて、これから繰り広げられる疾走を前にした、嵐の前の静けさのような静寂の中にいる。近くにいる馬2頭は、後ろから描かれ、大胆な構図を見せる。競馬を描いたドガの他の絵でも、馬の後ろ姿は少なくない。
細く長い脚の上にあって盛り上がるヒップアップした馬の尻は、生物体としての馬観察のポイントなのであろう。俊敏かつしなやかな動きを生む、瞬発性に富んだ筋肉が、いっぱいに詰まっていそうだ。尻を視点のポイントにしたドガの眼力には、唸らされるばかりである。
そして、尻以上に印象的なのは、乾いた競馬場の土に落ちる影である。大胆な構図もそうであったが、この影の扱いなど、明らかに広重など浮世絵の影響を感じさせる。
ドガは、若い時に古典主義のアングルの指導を受けたこともあり、また印象派の主流であった光そのものを描こうとする試みには距離を置いた。「現代生活の古典画家」と自称したこともある。
しかし、このような絵を見ると、ドガが印象派と呼ばれる理由もわかる気がする。より正しく言えば、ドガがドガでありつつ、印象派のメンバーたちと親和したことが、充分に納得させられるのである。
都市生活者のドガにとって、劇場は都会の華そのものであった。そこでの興味の対象は、決して舞台上で華麗に舞う踊子たちにのみあるわけではなかった。
『オペラ座のオーケストラ』(1870 オルセー美術館)――。画面上部に、チュチュ姿のバレリーナたちの下半身は見えるものの、ドガの関心の主眼がステージ下のオーケストラにあることは明らかである。もっとも、ドガの作品中、チュチュ姿のバレリーナが登場する絵としても、これが最初の作になるとのことである。
ドガがバレリーナたちを盛んに描くようになる前の、1870年という初期の段階で、オーケストラの絵が登場したのは、そのメンバーにドガの知人がいたからでもあった。画面中央で、フレンチ・ファゴット(バスーン)を構えるのは、デジレ・ディオ―というドガの友人である。その左奥にいるチェリストは、やはり友人のルイ=マレー・ピレという男だ。
私は初めてこの絵に出会った時に、不思議な絵だと感じて仕方なかった。構図的に、落ち着いてくれないのである。フレンチ・ファゴット奏者の右、オケの中心的なポジションで背を向けて座る男は、一見、指揮者のように見えなくもないが(位置的にはいかにもそうであろう)、左手がコントラバスにかかっており、その奏者であることが知れる。
オーケストラの編成は、時代により、また楽曲により、異なってはくるものの、指揮者を中央にしつつ、楽器をどう配置するかには「型」がある。だが、ドガのこのオーケストラは、そういう点では滅茶苦茶である。
管楽器であるファゴットと、その左横のフルートが、弦楽器の只中に放り込まれている。弦楽器も、ヴァイオリン(ヴィオラもか)の一群にまぎれて、チェロがぽつんと配されている。コントラバスがこんな中央前列に後ろ向きでいるのも、おかしい。要はこんなオケ編成はありえっこなし! すべてはドガによる勝手なコンポジションなのである。
そういう荒唐無稽を抱えながらも、この絵の奏者たちから立ちのぼる気迫の、潮のぶつかり合うような、微妙かつ複雑な動きは、何とも面白い。
それぞれの楽器の奏でる音が束となってオーケストラの音響となる、その調和の中にも、個性の発揮と互いのせめぎ合いがさざ波を立てる。極端なことを言えば、オケのメンバーはそれぞれが皆、ゴールを目指して走行する競馬馬に等しい。その集団と個性の動的なもみ合いの瞬間を、ドガは見事にとらえている。見れば見るほど、男たちひとりひとりの表情が面白いのだ。
しかも、全員が男たちであり、燕尾服を着込んでいるので、レンブラントがよくした集団肖像画ではないが、ギルドの集団を目の当たりにしているような気にさせられる。
そういう働く男たちの集団性ということになると、次の絵も忘れがたい。『ニューオリンズの事務所の人々(綿花取引所)』(1873 ポー美術館)――。
ドガは1872年から73年にかけての秋冬の4カ月あまりの間、母方の先祖ゆかりの地であるアメリカのニューオリンズに滞在した。この絵は、現地滞在中に描かれたもの。当時のニューオリンズはアメリカ南部を代表する綿花市場を擁し、近代資本主義の揺籃期を迎えていた。
旅の性格が親族訪問的色合いを濃厚に有していたので、この絵にも、親族が顔を出す。画面中央手前、座り込んで綿の品質を確かめている山高帽の紳士は、ドガの叔父ミシェル・ミュッソンで、その奥、新聞を広げている男性は、弟のルネ・ド・ガスであるという。その他、親族を中心に経営されている綿花ビジネスの様子を、ドガは集団肖像画の趣で描いている。
もっとも、ドガ本人は、とかく綿花一本鎗の現地の風潮にいささか食傷気味であったらしい。いかにも花の都・パリを象徴する画家としてイメージされるドガではあるが、アメリカという飛び地を自身の血の中に抱えていたことは、もっと注目されてよいだろう。パリのブルジョア家庭の出身と言いきるには、クレオール的な複合性を抱えたユニークな人物だったのである。
そのような出自の背景を考えると、パリの華のようなバレリーナたちを描いたドガが、時に、階級的な社会性に目覚めたような絵を残したことも、理解しやすくなるかもしれない。印象派の領袖・マネの影響は疑えないにしても、だ。
1876年の作になる『カフェにて(アブサント)』(オルセー美術館)は、そういう社会派・ドガの代表作であろう。夜の延長に朝を迎えたパリのカフェが舞台。アブサン(アブサント)のグラスを前に、憂いを溜めて座りこむ女。おそらくはアルコール依存症なのであろう。隣のボヘミアン風の男は、女の連れなのだろうが、女の孤独をケアする様子はなく、パイプをふかしながら、外の景色を追っている。
女にとっては助けにも慰めにもならない、クズ同然の存在の男だが、安酒と安香水の匂いがぷんぷんと漂ってきそうなふたりの腐れ縁は、自らもどうしてよいかわからぬどん底に呻吟するばかりのようだ。
さて、こう聞けば、ドガ先生、社会の底辺に生きる貧しき庶民に同情するあまり、その姿を活写した絵画によって、世に訴えたかったと、そう考えることになるだろう。
だが、ここにドガならではの落とし穴がある。社会的テーマそのものは、ドガの琴線に触れるものではあったのだろう。だが、描いた対象は、パリの陋巷の汚れた朝に見かけた淪落の男女などではなかったのだ。
女はエレン・アンドレという女優、男は版画家テブータン。ドガは知り合いのふたりに、ヌーヴェル・アテーヌというカフェでモデルをつとめてもらったのだ。つまりは、これもドガの心が組み立てたコンポジションということになる。
ドガの社会派的な眼差しが顕著な例として、今ひとつ、強烈な印象を与える作品に、『室内(強姦)』(1868~69 フィラデルフィア美術館)がある。
ひどく暗い絵だ。これがあの、白いチュチュをまとった可憐なバレリーナたちを描いた同じ画家の作品とはにわかには信じがたい。
タイトルが、『室内』と呼ばれたり、『強姦』と呼ばれたりするのは、画家によるオリジナルのタイトルが知られていないからだが、ミステリーに満ちたこの絵の落ち着きどころの曖昧さを象徴しているかのようだ。
寝台の脇に男は無表情に立ち、女は服の一部を脱がされ(剥がされ)て、男に背を向け、椅子にもたれて泣いている。初めてこの絵を知った時、私はムンクの作品ではないかと錯覚してしまった。それほどに、深刻であり、細かいシチュエーションは不明ながら、まごうかたなき罪の現場を、画家は目をそらすことなくとらえている。
私は今でも、このドガの絵を、社会派のマネよりは表現主義のムンクに近いと感じている。階級差というような視点では解けない、性を背負う人間の原罪とか宿業といったものを突きつけられているように思えてならないのだ。
『カフェにて(アブサント)』もまた、実は、一見して感じる貧困とか階級差の問題意識よりも、画家の目は、淪落そのもの、罪の宿業のようなところに据えられていたのではなかったろうか。コンポジションは、それを描出するためにとられた画家の手法だったはずなのである。
こう見ると、ドガという画家のユニークさは、単にバレリーナたちの艶姿を華やかに描いたなどという次元にあるのではなく、印象派を飛びぬけて、20世紀絵画へと通じる先見性を有していたということになるのではないだろうか。
そして、この次世代を先取りし、未来への橋渡しを果たすというドガの特性への私の関心は、次にあげるボナールとの近似という点において、頂点に達する。
まずは虚心坦懐に、以下のふたつの絵を見比べていただきたい。どちらも、室内で入浴する女性を描いた作品である。
最初の1点は、『浴盤で入浴する女性』(1885 メトロポリタン美術館)――。ドガの作品である。ドガは晩年、入浴する女性の絵を数多く描いたが、これはその中のひとつ。歳を重ねるに従い、視力の弱まったドガは、油彩からパステル画に移るようになるが、この絵もパステルで描かれた。
次なる1点は、『浴盤にしゃがむ裸婦』(1918 オルセー美術館)――。こちらは「アンティミスト(親密派)」と呼ばれたピエール・ボナールの作品。愛妻マルトを繰り返し描いたボナールには、入浴中の妻を描いた作品も多いが、これはその中でも代表作となる。
ドガの描いた入浴する裸婦は、妻や愛人ではなく(ドガは生涯独身)、モデルを雇い、浴盤を置いて入浴させたのである。ドガの関心の中心は、女性の体の動きにあったのかもしれないが、画家と女性との距離感や、ヌードとはいえ神話性などからは全くかけ離れたプライベートな居ずまいからは、親密性を際立たせずにはいられない。そこに、アンティミスト、ボナールへの道が切り開かれるのである。
もう少し見よう。ドガの『髪を梳く女』(1886頃 エルミタージュ美術館)――。そして、ボナールの『化粧室 あるいはバラ色の化粧室』(1914~21 オルセー美術館)――。どちらも後ろ姿の裸婦だが、極めて親密性の高い、極私的空間を舞台とする。
ドガにとっては、そのポーズ、舞台、構図など、すべては彼が用意した設定の中で組み立て演じさせた、コンポジションだったのかもしれない。
ボナールついては、かつて独自に詳しく論じたことがある(第29回)が、親密性の高いマルトの絵は、すべて共に過ごした私的な時間を繰り返し慈しむ中から生み出された、記憶の再生と深化を意味するものなのである。つまり、ボナールはボナール流に、記憶のコンポジションに努めていたことになる。
こうして見ると、踊子の絵だけに馴染んで何となくわかった気になっていたドガの世界が、実に深遠で、かついかに時代を突き抜けていたかに気づく。
もとは古典主義のアングルの弟子であったというドガは、印象派の中でも極めてユニークな立場を堅持した。だがそれは、「異端児」などという言葉ではとてもとらえきれない。
ドガは、「○○派」などという枠をゆうゆうと超えてやまない、巨大な宇宙そのものとして、美術史に屹立しているのである。