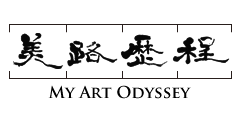
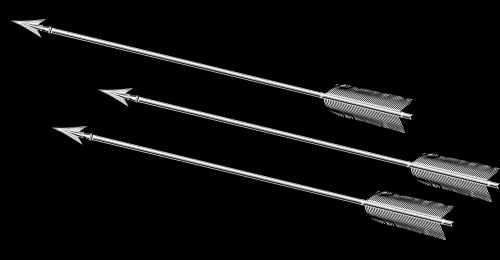
「グレコは魂の画家だ」――今から百年以上も前に、木村宗八はグレコを評してそう語っていた(『エル・グレコ』1916)。
このことを改めて思い知らせてくれるのは、彼の描いた聖セバスチャンの絵である。あの、輝くばかりの男性ヌードの美の競演を画家たちにもたらした、矢を射かけられた殉教者のことだ。
キリスト教に殉じたその聖性を引き立てるため、その肉体はひたすら美化され、グイド・レーニに至るエロスの美を極めたことは、前回に述べた。
ところが、同じく裸身を扱いながらも、この男性肉体美の路線から外れた、一風変わった聖セバスチャンを描いた画家がいる。他でもない、エル・グレコである。
エル・グレコ作『聖セバスティアヌス』(1576~79)――。クレタ島生まれの画家が、イタリアを経てスペインに渡り、かの地で最初に注文を受けて描かれた主要作品であると推測されている。
この絵が描かれたのとほぼ同時期に、グイド・レーニがこの世に生を受けている。エル・グレコは、レーニよりも前の画家なのだ。そのことを、当然のように感じるか、意外に感じるか、人によって分かれるかもしれないが、ここで大事な点は、レーニに至る美の流れの方が、聖セバスチャンをめぐっては主流であり、エル・グレコは忽然と現れた異端の星だということである。
ともかくも、エル・グレコの『聖セバスティアヌス』を、じっくりと見てみよう。
一見して目につくのは、小ぶりの顔に比べて、首から下が異様に長いことである。そして、長々とした胴体の胸から腹、下腹部、さらに腕や足へと至る四肢五体の表面に浮かぶ、凹凸に富んだ陰影である。胸骨や筋肉が浮きあがり、ごつごつとした印象を与える。
グレコが、肉体への相当のこだわりをもって描いていることは間違いない。だが、この肉体はセクシーだろうか? 目くるめく官能の輝きであろうか――?
否(ノー)ある。肉体を重要視するところは、他の画家たちと変わりがない。だが、エル・グレコが描く肉体は、独自の主張に貫かれている。
ごつごつとしたその肉体は、皮膚の下に五臓六腑を詰めた、血と肉を餡のように抱える生身の肉体である。捕縛されるその前まで、日々の労働にいそしみ、ほとばしる汗のなかに鍛えぬかれた、働く者の肉体なのである。
美を極めつくした神のごとき男性裸身像ではなく、世俗の世に日々を送り、摂食し、排泄もする、
人間の信念、真実……エル・グレコの聖セバスチャンは、肉体を描いて魂に肉迫する。肉体の実存主義とでもいうような、時代に先駆けた近代性が脈打つ。
エル・グレコには、もうひとつ、著名な聖セバスチャン像がある。1610年から14年にかけて描かれたとされる『聖セバスティアヌス』だが、やはり相当にデフォルメされた肉体で、首長、胴長、足長と、括られた木の幹と見合うような縦長である。
胴や四肢に与えられた陰影は、背景の渦を巻くような空と響きあい、ただならぬ悲劇の予兆のなかにこだまを交わし合う。そのなかにあって、セバスチャン本人は、上目づかいに、あくまでも澄んだ眼差しで天上を見上げるのである。狂い、
先にも触れた1916年に出版された木村荘八の著書『エル・グレコ』では、武者小路実篤がグレコについて語った言葉が引用され、賛同されている。
「彼の絵を見ていると之より宗教的な、之より清浄な絵はかけないと云う気がする。彼の絵には誰の絵にもない宗教的な淋しさ、目に涙をためた内に愛と感謝に満ちた孤独が味われる気がする。彼は誰も入れなかった所迄入っている。自分達は彼を愛敬し、彼のこの世に生きていたことを喜ぶものである。」――。
武者小路のエル・グレコ評は、聖セバスチャンの絵についても、そっくり当てはまると言えるだろう。
なお、この絵はいつの頃からか、上下に二分され、それぞれ別々に存在してきたが、今ではともにプラド美術館が所蔵し、元通りの一つの絵に復元されている。
月日が300年ほど飛ぶ。
その間、聖セバスチャンの絵は、男性ヌードの金字塔を目指して画家たちがしのぎを削り、グイド・レーニを頂点とする官能美を磨き上げた。殉教者が抱えていた精神性や宗教性は、輝く肉体美の錦の御旗のもとに、著しく後退した。
ところが、近代の入り口のところで、もともとの聖セバスチャンが蘇るのである。以下、どのような画家たちが、聖セバスチャンを描いたのか、具体的に見ていこう。
まずは、フランス象徴主義の旗手、ギュスターヴ・モロー(1826~1898)――。近代が近づくにつれ、物質主義、現実主義が世を覆うことになったが、そういう世の趨勢に背を向けたモローは、神話や古典を重視し、幻想的な内面世界を描こうとした。
そのモローなればこそか、彼は聖セバスチャンを繰り返し描いている。最もよく知られたモローの聖セバスチャンは、『殉教者に叙せられる聖セバスティアヌス』(1876頃 フォッグ美術館)であろう。『聖セバスティアヌスと天使』とも呼ばれる。
この絵の聖セバスチャンの表情はいかにも暗く、処刑の場で、孤独の極みのような姿を晒している。忠義をもって仕えた皇帝を始め、世の中の大勢から無理解によって憎み蔑まれ、死に追いやられることになったのである。
しかし、そこに強烈な光を放つ十字架とともに天使が現れ、セバスチャンに寄り添う。この瞬間、ローマ軍の一兵士だったセバスチャンは、文字通りの聖セバスチャンに昇華された。聖なる殉教者に叙せられたのである。
セバスチャンは決して孤独ではなかったのだ。この感動の場面を、モローは持ち前の神秘主義によって、幻想美に溢れた神々しいまでの熱量を秘めた作品に仕上げた。真実の栄光を象徴する聖セバスチャンの物語を、モローは不変の魂の美学に結晶させたのである。
モローが生きた時代は、印象派が隆盛となった時期と重なる。だが、光をとらえることを主眼とした印象派とは、全くそりが合わなかった。印象派の画家たちにとってみれば、彼らの絵は抹香臭い宗教や道徳、綻びの目立つ因習からの解放を意味したのだろうが、モローに言わせれば、それは人類古来の価値をみすみす放棄し、精神や徳を放棄した泥海にさまようことに他ならなかったのである。
やがて印象派が一世を風靡すると、モローはアートシーンの表舞台から身を引き、隠棲者のように暮らしながら、制作に勤しんだのであった。
日本にも、モローの描いた聖セバスチャンの絵がある。岐阜県美術館には、フォッグ美術館所蔵の『殉教者に叙せられる聖セバスティアヌス』のバージョン違いのような作品がある。一般には、『聖セバスティアヌスと天使』と呼びならわされているが、フォッグ美術館の作品と同じく1876年頃の作と推定されている油彩画である。
また、群馬県立近代美術館には『救済される聖セバスティアヌス』という水彩画があり、こちらは1885頃に描かれた作品となる。
弓を射られ、瀕死の重傷を負ったセバスチャンを、イレーヌら信徒の女性たちが懸命に介抱する。処刑が済んだと考えた刑吏や群衆はすべて立ち去り、他に誰もいなくなった寂然とした黄昏の谷に、孤独の、しかし熱い真実の時が流れる。
信仰の真実に生きる者の手に触れて、セバスチャンは一命を取りとめる。寄り添う魂が奏でる愛のあたたかみが絵に横溢し、見る者の胸を静かな感動で満たす。
同じシチュエーションを描いた、『徳高い婦人たちによって介抱される聖セバスティアヌス』(1869頃 クレメンス・セルス美術館)も、捨てがたい。こちらは油絵だが、たいへんに詩的であり、神秘性に富んでいる。
モローらしさは、聖セバスチャンを描いたどの絵に於いても、十全に発揮されている。
19世紀後半から20世紀初めという、印象派の時代のフランスに生きながら、やはり独自の道を貫いたオディロン・ルドン(1840~1916)にも、聖セバスチャンを描いた絵画がある。
前半生、宙に浮く眼球など怪奇幻想をモノクロで描いていたルドンは、後半生、色とりどりの花々を描くなど画風を大きく変えたが、聖セバスチャンの絵は、最晩年の1910年代に集中している。油彩、パステル、水彩と、多様な手法を用いながら、ルドンはいくつもの聖セバスチャンの絵を描いたのだった。
ルドンの聖セバスチャンに特徴的なことは、いずれも彼ひとり、木を背にしていることである。弓で射かけられて処刑される際に、木に括りつけられたという伝説に依拠しているわけだが、単なる伝統の踏襲を超えて、ルドン独自の意味づけが加えられていることと思われる。
1910年から12年にかけて制作された『聖セバスティアヌス』(ナショナル・ギャラリー・オブ・アート所蔵)は油彩画で、サイズも比較的大きな作品になる(144cm×62.5cm)。セバスチャンの白い裸身が大きな面積を占めるが、官能美を具現化した理想の肉体としてではなく、人間の悲哀そのもののように、そこに佇んでいる。
背景の木は裸の幹が主だが、ところどころ、小さな赤い葉をつけ、あたかも生命の木のような趣を見せる。足元にも、草や花々が添えられ、命の息づきでセバスチャンを囲む。ルドンの意識のなかには、キリスト教の殉教者ということを超えて、どこか死と再生のイメージがあるのだろう。
モローの『聖セバスティアヌス』を所蔵する群馬県立近代美術館が、実はルドンの『聖セバスティアヌス』も所蔵している。1910年から13年にかけて制作された、パステルによる作品だ。
この作品では、全体に月夜の海にも似た、銀の粉をまぶしたような、神秘の紗に覆われて漠とした雰囲気を醸し出しているが、セバスチャンは、かぐや姫の物語ではないが、木の幹の中に入り込んでしまったかのように描かれている。古木と一体化して、木の精と化したような印象を受ける。
胸と左足の腿、そして木の幹の下方に矢を見出すことができるが、殉教者としての伝統を維持しつつも、裸の上半身の周辺をいぶし銀の輝きをもつ青みのひろがりで包むような仕様は、ルドン独自のものだ。幹の中に閉じ込められた逼塞した孤独の世界と同時に、広く無限の世界に放たれた解放感、魂の救済をも感じる。
先のナショナル・ギャラリー・オブ・アートの作品同様、ルドンならではの、深い精神性をたたえた孤高の作品になっている。
最後に、ウィーン世紀末の画家、エゴン・シーレの描いた聖セバスチャンを見よう。『聖セバスティアヌス(聖セバスチャン)としての自画像』(1914)――。
画面の上下に太い黒字が書き込まれたことで明らかなように、1915年1月にウィーンのアルノット画廊で開かれた個展のためのポスターとして描かれたものである。
人間存在の根本に性を据え、作品でも果敢に性をとりあげたシーレは、少女の裸身を描いたことで警察に拘留されるなど、保守的な社会から
満身創痍のなかで、己の信じる絵の道を進むしかなかったわけだが、そのような自身の姿を描くに、無数の矢を射かけられた聖セバスチャンを重ねたのであった。
情け容赦もなく彼めがけて飛んでくる矢の攻撃に身を晒しながら、操り人形か何かのように、身を躍らせるしかなかったシーレ……。世の中の無理解と非難に囲繞された異端者としての孤独がひしひしと迫り来る。画業の成果を世に問う個展のポスターは、旧弊に毒された社会に向けた異端宣言でもあったのだ。
面白いのは、自画像を含め、多くの裸身を描き、時には露悪的に自慰行為に耽る姿まで描いたシーレが、このポスターでは服を着せていることである。聖セバスチャンの伝統を踏襲するなら、裸身の肉体を描いてもよさそうなものなのに、彼は敢えて着衣の殉教者を選んだ。聖セバスチャンを描くに、官能的な男性美を目指すような流儀に対し、徹底して反抗したかったのだろう。
シーレは肉体を追求した画家でもあった。しかしその肉体は常に精神と結びついていた。人間の赤裸々な姿を描くに、単なる美しいヌードを超えた、人間存在そのものとしての肉体を描き続けたのである。
矢を射かけられた場でこそ、着衣のセバスチャンを描いたものの、その実、シーレの描く肉体は、ごつごつとして、どこかエル・グレコの描いた肉体との相似を思わせる。
一例だが、シーレの『抱擁』(1917)と、エル・グレコ最晩年の作『ラオコーン』(1610~14)を、比べて見るがよい。聖セバスチャンの絵を巡る「もうひとつの潮流」が、ここでもしっかりと確かめることができる。
絵画における聖セバスチャンのイメージは、美しい男性ヌードの官能性を追求する道を辿る一方で、メインストリームに反旗を翻すかのように、魂や精神を重んじる、もうひとつの流れが存在してきたのである。
エル・グレコがこの流れの基礎を築き、400年もの歳月を飛び越えて、シーレとの響き合いを見せたことが興味深い。もともとビザンチン様式のイコン画家として出発し、西洋絵画との橋渡しをしたグレコは、時の橋渡し役をも果たしたことになる。
時間と空間を超えた橋渡し役という点を考えれば、20世紀初頭に白樺派の文人たちが中心となって古今の西洋絵画を次々と日本に紹介した際に、エル・グレコが魂の画家として巨匠の扱いを受けたのも、当然であったという気がする。