
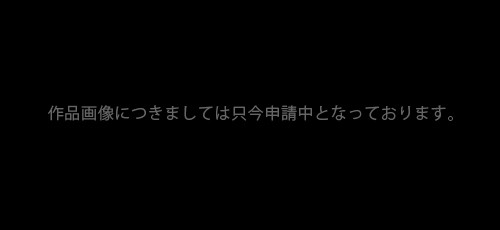
ボナールとの関わりを軸にすえながら、もう少し楠目成照という画家について見て行こう。黄金のパリと言われた1920年代、パリに留学し、ボナールの弟子として学びながら、結核を悪化させ、20代半ばで現地に客死した。
楠目の郷里である北九州市の市立美術館には、遺族から寄贈された楠目の作品が3点、収蔵されている。『フェアリーテールズ』(1920)、『少女像』(1922頃)、『裸婦像』(1922頃)である。
このうち、『フェアリーテールズ』のみはパリ留学に出る前、日本で描かれた作品で、1920年に行われた第2回帝国美術院展覧会(帝展)で入選を果たした。楠目としては、前年の第1回帝展で『Pさんの庭』が入選したのに続く、連続受賞であった。
まだ東京美術学校で学ぶ画学生であったことを思えば、大変な才能の持ち主であることは間違いなかった。
実をいうと、私はこの楠目の帝展入選2作品について、当時入選作からつくられた絵葉書によって、劣悪な画質ながら、かろうじて内容を知るばかりだった。
それが、このほど北九州市立美術館からデジタルデータを見せていただくことができて、心底驚いた。月並みな表現にはなるが、まさに目からウロコが落ちる思いがしたのである。
鮮やかな映像によって『フェアリーテールズ』は、一見して平凡な、庭での家族の風景を扱いながら、何とも斬新で、時代に先駆けた作品だった。しかも、パリに出て師事することになるボナールの作風にも通じるところを有していた。
鮮明な画像でまず驚いたのは、庭の緑の濃密さである。そこだけを見れば、アンリ・ルソーにも通じるかのような、樹林の存在感である。よく見れば、緑にも共鳴と反発があって、背景をみっちりと埋める、2本の木に茂るたわわな葉の緻密な描かれ方と、手前に置かれた鉢にすっくりと立つ葉ぶりの大きな木とのコントラストが実にいい。
ゴムの木のような鉢植えの木は、前景と背景の分断線であると同時に、画面の左側の母と娘と、右側の少年との間を断つ境界ともなっている。それによって、同じ庭で憩う家族の間にも、それぞれの胸の占める独立した夢想があることを知る。
同じく緑の庭にひと時を過ごすとはいえ、少女は童話らしき本の世界に浸り、母は一見、娘の本に視線を重ねるようでいながら、独自の想いに耽るのである。少年にいたっては、体の向き、視線すら、母と妹とは交わることもない。それぞれの胸に湧く想いを、楠田は「フェアリーテールズ」と呼んだのだろうか……。
私はこの絵を見て、咄嗟に、ボナールの『ブルジョワ家庭の午後 あるいはテラス一家』(1900)を思い出した。ボナールの絵では、庭に憩う家族、親戚の数は、10人を超えるが、殆どの人間の視線が交わらないという点では同じなのである。昼の庭に集いながら、殆どの登場人物が、それぞれ別々の想いにとらわれているのが実相なのだ。そこに、近代性が如実に表れてもいる。
また、楠目の絵の中央付近に置かれた植木鉢の木は、ボナールの『男と女』(1900)の画面中央で男女の心理を裁断した衝立(屏風)を思わせもする。
フランスに渡る前の楠目が、どこまでボナールに馴染んでいたのか、画集なりでその作品に接することが可能だったのかは、微妙なところだ。藤島美菜氏の研究によれば、日本の刊行物で初めてボナールが紹介されたのは、1913年発行の『現代の洋画』誌であったというが、この時はまだ白黒の写真による図版掲載であった。
次のボナール受容のエポックは、1922年に福士幸次郎の翻訳でレオン・ウェルト著『ボナール賞賛』が刊行されたことだというが、それは楠目が『フェアリーテールズ』を描いたよりも後のことになる。同じ1922年に、農商務省商品陳列館で開催された「仏蘭西現代美術展覧会」には、ボナール作品が2点出品されており、日本でのボナール受容が1920年代に始まったことを伺わせる。
それを思うと、楠目がパリでボナールに師事したのは、やはり時代の最先端にアンテナを張っていたからこそということになる。楠目がパリに渡ったのは、1920年代の初頭としかわからないが、当時、パリに留学した日本人画学生たちの多くがマティスやマルケが教鞭をとるアカデミー・ジュリアンに入学したのに対し、楠目はボナールが教えていたアカデミー・ロンソンに入学したことを見ても、楠目がパリでボナールとの出会いを期していたと考えてもよかろうかと思う。
楠目にとってのパリは、まさにボナールのパリだったのだ。
北九州市立美術館が所蔵する楠目成照の他の2作品=『少女像』と『裸婦像』については、パリ時代に描かれたものと思われる。画面から伝わってくる雰囲気が、日本時代の作品とは一変している。光に対する意識、そして色の用い方など……。
楠目が通った北九州の小倉中学(戦後は高校)の後輩にあたる佐野正幸氏は、学校では美術部に所属したが、ある日、同級生だった楠目の甥から、パリに学んだ伯父の作品だとして2、3枚の油絵を見せてもらい、美術部一同「仰天した」ことを証言している。まぎれもなく、「ヨーロッパの空気と光のなかに生きている人の描いた絵」と感じたからだった(『愛宕丘の四季』小倉高校明陵同窓会 1998)。
後輩たちを驚かせた楠目の絵が、これらの作品であったのだろう。とりわけ、『少女像』の色彩感は「仰天」という表現が大袈裟でないほどに印象的だったことと思われる。
ただ、楠目がパリで学んだのは、光や空気という技術的な面ばかりではなかった。2点の絵に共通して見られるモデルとの親密性こそは、「アンティミスト」と呼ばれた師のボナールを通して身に着けたものではなかったろうか。
洋画家の高畠達四郎氏は1921年から7年間パリに留学し、現地で楠目成照と親交をもった。『美術手帖』の1949年1月号に、高畠は「楠目とペーラシェーズ」という小文を発表しているが、それによれば、パリ郊外のサンクルーにあった結核療養所に入院した楠目を見舞ったところ、彼には親しいロシア娘がいたとしている。「深紅のバラを思わせる」女性だったという。
こうなると、『少女像』のバイオリンを手にした娘が、単なるモデルにバイオリンを与えてポーズをとらせたのか、親しんだロシア娘との日常的風景のなかから生まれたのか、気になってくる。
楠目成照の妹の楠目ちづさんは、長じて華道教授として名をなし、『花のように生きれば、ひとりも美しい』という著書を残したが、そのなかで兄の音楽好きについて触れている。
「上から2番目の、年の離れた兄は画学生でした。20代半ばで、肺病で亡くなってしまったのですが、音楽的な才能ももち合わせており、私は多くの教養を与えてもらい、とりわけピアノを専門的に習った時期もありました」――。
先の高畠も、パリの楠目がリムスキー・コルサコフの『シェヘラザード』を口ずさんでいたことを書いているし、またパリのアパートの戸口には、「金鶏の紙が切りきざんで」飾ってあったとしている。「金鶏」は、やはりリムスキー・コルサコフ作曲になるオペラのタイトルだ。
かくまでにロシア音楽に馴染んだのが、パリで出会ったロシア娘と何らかの関係があることは、容易に想像し得るところだ。高畠も、「ロシア娘は音楽を通して楠目と話が合ったらしい」と書いている。
『少女像』の少女は、バイオリン練習の合間に、まるでマンドリンでも弾くように、バイオリンを横にしてつま弾いている。バイオリンの演奏姿ではなく、演奏(練習)の手をとめ、ふと曲を離れて何か個人の想いに心を傾けている。
演奏中の公の姿とは違う、私的な時間と空間が切り取られている。それを見つめる画家の眼差しも、少女の「私」に寄り添っているように見える。
「アンティミスト」は「親密派」と訳されるのが普通だが、極私的なプライベート空間にこだわり、そこから作品を紡ぐ人たちを言う。ボナールはその代表格だが、楠目はその画風にも惹かれていたようだ。
アンティミストの親密性が最も顕著に発揮されるのは、化粧室や浴室での裸婦像になるが、ボナールは愛妻マルトをモデルに、数多くのその手の絵画をものした。
1914年から21年にかけて描かれた『化粧室 あるいはバラ色の化粧室』は、親密派としてのボナールの代表作だが、楠目の『裸婦像』も、やはりこういう流れに則している。『化粧室 あるいはバラ色の化粧室』ほど有名な作品ではないが、ボナールが1925年に描いた『化粧』のほうが、絵のトーンなど、楠目の作品により近いかもしれない。
気になるのは、楠目の『少女像』と『裸婦像』が、ともにおかっぱ頭の女性を描いており、親密性をも併せ考えるに、同じ女性を描いたのではないかと思われる点だ。だとすれば、それは例のロシア娘だったのだろうか……。
楠目の伝記的な情報があまりにも少ないので、推測の域を脱しないのは、いかにも残念である。
とここまで書いたところで、北九州市立美術館の河村朱音氏から、戦前のパリに長く住んだコレクターの福島繁太郎氏が、その著書『エコール・ド・パリ 1』(1950 新潮社)でボナールをとりあげたなかに、楠目に関しての記述が含まれているとの教示を受けた。
早速本を取り寄せてチェックしてみると、福島はボナールのあたたかな人柄を語る好例として、楠目を見舞ったエピソードを紹介していた。
それによれば、入院中の楠目に、ボナールは時々手紙を送って慰めたのみならず、病が重いことを聞いて、交通の便の悪いパリ郊外の療養所を、わざわざ訪ねたのだという。
楠目は後日、「ボナール先生がきてくれて驚いた」と、高畠に語ったそうである。師の好意が身に沁みて嬉しかったのであろう。
「日本かぶれのナビ」から出発したボナールに、日本人の愛弟子がいたということ、その人・楠目成照は若くしてパリに客死したが、豊かな才能を有していたこと――これらの点は、世界と日本の美術をつなぐ交流史からも、きちんと記憶されて行かなければならないと思う。
「絣の着物に小倉袴をはいた楠目さんは、聡明な色の白い背の高い、ほんとに若竹の様な少年だった。そして特長ある大きい美しい目と、赤い唇をもっていた。殊にその其秋水の様な澄んだ目は性格の純真さを一目して知り得る様な感じのいい目であった。(中略)
楠目さんが二階の入口の壁際にキチンと坐って、良人の絵の話に耳をかたむけたり、持って来たスケッチの批評を聴きつつ、其うす紅をさした双の頬に笑いをただよわして、遠慮がちに打語られた、あの少年時代の有様が今もはっきりと思いうかめられるのである」――。
北九州に暮した俳人の杉田久女が、1920年4月に著した「私の知っている楠目さん」という随筆の一節である。
「花衣ぬぐやまつわる紐いろいろ」、「谺して山ほととぎすほしいまま」などの名句よって、近代俳句史に燦然と輝くこの天才女流詩人が、楠目成照のことを書いていたのだ。
楠目とボナールを結んだ運命の糸は、パリから遥か極東の北九州に飛んで、もうひとつの奥の物語を紡ぎ出す。何故俳句作家の久女が画学生の楠目を知っていたかというと、彼女の夫が小倉中学の美術教師・杉田宇内で、楠目に絵を教え、その才能を見抜いた人だったからである。
小倉中学時代はもとより、東京美術学校に進学して以降も、楠目は杉田を慕い、帰省中にはたびたび旧師を訪ねて美術談義を重ねたらしい。
1919年に帝展に出した『Pさんの庭』が入選し、新進気鋭の若き画家として歩き出した楠目を、夫ともども久女は歓迎し、期待の眼差しで眺めていたのだった。久女自身、俳句に命を懸ける芸術至上主義で知られたが、絵ひと筋に邁進する楠目の情熱に、大いに共鳴したらしい。
「ものに熱し易くて、火の様な芸術欲に燃えている楠目さんは美術学校にいても只描きたい描きたいで躰に無理をしたりして健康を害したので、昨年の初夏の頃から(*小倉の)鍛治町の家へ帰って来ていた。(中略)
良人は非常に心配して、『君、躰を大事にしなくてはいけない、一年や二年早く名をあげても躰をこわしては何にもならないからね』とよく言ったりした」――。
作品に没頭するあまり、健康を損ねがちな楠目を、宇内はたいそう心配していたという。教え子思いの教師らしい風貌が伺われる。
杉田宇内は、東京美術学校の西洋画科を首席で卒業したとされ、若き日には大いに将来を期待された。卒業制作に描いたと言われる『自画像』(1908)という作品が残っており、今では北九州市立美術館に所蔵されているが、絵のスタイルとしては古典的ながら、実にしっかりとした画風である。自身の裸身を通して、人間存在というものの核を見据えようとする態度には、小手先の器用さを超えた芸術家魂の真実を感じてならない。
だが、美術学校卒業後、宇内は美術教師の道を選び、小倉中学に奉職して以降は、絵を教えることに専念して、自身が創作の絵筆をとることはなくなってしまう。未来の芸術家に期待して結婚した久女は、こうした夫の態度に失望し、その代償のように、俳句の世界に没入して行くことになるのだが、この随筆のなかでは、まだ夫婦仲は険悪化せず、楠目の存在によって宇内が美術教師として芸術の最前線に立つことが可能となり、妻の久女もそのことに満足している様子が窺える。
「楠目さんには地位も権勢も金力もない。只芸術熱ばかりが燃えていた。良人は自分の事の様に喜んで、自分は此十年余りを製作から遠ざかって暮して来たが、兎にも角にも自分の導いた中の一人が是から芸術界へ乗り出してゆくと云う事を以って、いささかながら教師としての責任を真面目になし得たものとして或満足を覚えている様であった。(中略)
もうよっぽど寒くなってからも、思いたつとヒョックリ夜分などたずねて来て、火鉢をかこんでは良人と遅く迄語る事があった。楠目さんはルノアールやセザンヌ、ゴッフォ、マネー、ゴーガン等いう近代の大家の作風や筆技などという事に非常に注意をはらって、東京にいる間もこれらの人々のをはじめ、ドガやモネーなんかのも丸善へ新しい画集や写真版が来る度にきっと買いあつめて、本場の作品傾向を実地に見る事が出来ないからというので、写真を通して不充分ながら色々と研究もしたり、(中略)それはそれは絵という事に対しては熱心なものであった」――。
楠目と宇内の間で、ヨーロッパの巨匠たちの名前が飛び交い、楠目が東京で画集や写真集を購入して、必死に時代の最先端の流儀を吸収しようとしていたことがわかる。ただ惜しいかな、ここにボナールの名前がない。これは、楠目が1920年の段階で、まだボナールの真価に触れていなかったのか、あるいはその場の聞き手である久女にボナールという名前が馴染みがなかったゆえに、漏れてしまったかのどちらかであろう。
やがて、宇内と久女の夫婦間の亀裂は広がり、久女は「足袋つぐやノラともならず教師妻」など、女性としての不如意を嘆く句をも詠み、そのことで宇内は社会的に傷つきもしてと、悪循環に陥って行く。
久女について書かれた近年の本では、このたぐい稀な女流詩人への贔屓のあまり、探求心の強い芸術家肌、天才肌の久女に対し、芸術に無理解で、無能で封建的な男として宇内が描かれがちである。田辺聖子氏の労作『花衣ぬぐやまつわる…わが愛の杉田久女』(1987)にしても、この弊を免れていない。
それは、かつて久女の奇矯な振舞いばかりを強調し、狂態として断じていた男社会への意趣返しなのであろうが、久女に寄り添おうとするあまり、宇内への理解がおざなりになってしまっている。
だが、楠目とのエピソードは、こうした単純な見方の修正を求めてやまない。ボナールに師事することになる楠目が、宇内と近しく親交し、そこで多くの学びを得ていたのだ。卒業後も、機会あるごとに宇内と語らい、美術への情熱をたぎらせていたのである。宇内が芸術を理解しない無能のぼんくらだったなら、楠目が慕うことなどなかったであろう。
もうひとつ、宇内の側から楠目とのことを注視する必要もある。才能溢れる教え子のパリでの客死は、師の宇内にとって、どれほど大きな悲痛、衝撃であったろうか――。楠目の両親は、もともと楠目を東大に進ませたかったという。本人の選んだ道とはいえ、宇内の後押しがあって絵の世界に足を踏み入れたことを考えれば、教え子の夭折は他人事でいられる筈もなかった。
楠目という青年画家は、教育者であることを優先して自身の絵筆を捨てた宇内が、なおも芸術家魂を共振共鳴させ、ひたすら期待をかけていた希望の星だったのである。その楠目が斃れたのだ。楠目の夢の挫折は、恩師・宇内にとっても、何がしかの崩壊であったのである。
宇内はつくづく思い知らされた筈だ。芸術というものの怖さを、芸術に懸けた人間が挫けた際の脆さ、はかなさを……。その悔悟と自省が向かう先は、俳句を生活のたしなみ程度にあしらうことをよしとせず、十七文字に命を懸ける妻の久女だったのだろう。このままでは危ない、危ないと案ずる気持ちが、妻の芸術至上主義に同調しない頑なさを生んだのではなかったろうか。
結局、久女は俳句への一途さが嵩じて、俳句界のドンにしてホトトギス派の領袖・高浜虚子に疎んじられ、一門から破門されてしまう。作品発表の場を奪われ、生き甲斐を喪失した久女は、心身ともに疲弊衰弱し、戦中戦後の混乱も重なって、1946年1月に死去する。宇内は教え子・楠目の死に続き、妻の久女が芸術に殉じ逝くのをどうすることもできなかった。
こうして見ると、杉田宇内、久女のふたりを襲った悲劇に、楠目の夭折が大きく関わっていたことがわかる。久女関連の研究や著作で、楠目のことがきちんと扱われたものを、いまだに知らない。だが、近年のジェンダー的論調からは見落とされていた新たな視点が、ここに開かれると私は信じる。
北九州市立美術館が所蔵する、ボナールの『パリの朝』、楠目成照の3作品、そして杉田宇内の若き日の『自画像』、さらには久女の俳句に至るつながりのなかから、大きな時代のドラマが浮かび上がってくる。いつの日か、国やジャンルの垣根を越えて、スケール感の大きい、骨太な物語を書いてみたいという希望もある。
ボナールの『パリの朝』に戻ろう。この絵の画面左端から中央に向けて伸びる長い影はいかにも印象的だが、画面の先に幻視するしかない影の主体は何だったのだろう……。
もちろん、リアリズムで考えるなら、校庭に佇むもう一人の少女であってよいのである。しかしそこには、敢えて描きこまぬことから生まれる漠たる思いのたゆたいが残る。想像が羽ばたく余地を、ボナールのこの絵が本然的に有しているのだ。
影は人間がそこに存在する証でもあるが、その影をつくるのは東の空から上ってきた太陽である。その朝日の向こう、東の遥か彼方、ぐるっと地球を半周した先には、日本がある。極東の、世界でどこよりも朝日が早くのぼる、日出ずる国である。
若い頃に「日本かぶれのナビ」と呼ばれたボナールは、パリの朝を描きつつ、その先の東の空、東の国へと、思いを羽ばたかせ、奥深い物語が開かれる運命的な予感を覚えていたのかもしれない。
「楠目に」と献辞を添えてサインしたボナールの心は、アンティミストにふさわしく、そこまでの極私的な絆を孕んでいたと思いたいのである。