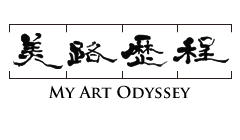

キューガーデン(王立植物園)のあるロンドンは、種苗や標本、植物画にいたるまで、世界の緑の集積地であった。そしてもうひとつ、ロンドンと並んで、海の彼方から緑が集められた中心地がヨーロッパに存在する。国立民族学博物館を有するオランダのライデンである。
国際貿易商社がそのまま国家になったようなオランダ。レンブラントやフェルメールの生きた17世紀、アートのみならず、オランダは経済的にも世界を股にかけて活動し、繁栄を極めた。あまたの東洋の文物がオランダに運ばれる中、植物もまた海を越えた。トルコからもたらされたチューリップがオランダで人気を呼び、ゴールドラッシュさながらの狂奔を生んでバブル経済の高騰を見たのもこの頃だ。
時代は下り、やがてオランダに代わってイギリスが世界の覇者として台頭することになるが、世界、特に東洋の文物や情報をヨーロッパに伝える役割はオランダの国ぶりの柱として定着した。こうした流れの果て、19世紀になって日本とヨーロッパをつなぐ巨人の出現を見る。フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1796~1866)である。
シーボルトというと、西洋医学を施療して名を高めた医者としてのイメージや、国禁の日本地図を持ち出そうとして国外追放になったスパイもどきのイメージが喧伝されがちだが、実は大変な博物学者で、しかも興味の中心は植物学であった。
種苗や標本など、シーボルトが日本から持ち帰った植物資料は数知れないが、最も多くは植物画であった。クック探検隊の植物学者ジョセフ・バンクスにシドニー・パーキンソンという絵描きがいたように、シーボルトにもその目となり記録者となった絵描きがいた。長崎の絵師、川原慶賀(1756~1860?)である。
慶賀は出島のへの出入りが許された絵師だったので、シーボルト来日(1823年)以前にもオランダ商館の風俗などを絵にしてはいた。だが、シーボルトとの出会いがその画業に決定的な影響を与えた。シーボルトの望むままに、あたかも現代で言えば写真を撮るような感覚で風景や文物、動植物を絵に写してゆく。その結果、目も筆もリアリズムを研ぎ澄まし、真摯さや律義さを増してゆくのである。それは例えば、写楽の役者絵や北斎の赤富士のような極端にデフォルメされた美の創造とはおよそ異なるわけだが、慶賀のこうした特質は何よりも植物画において発揮されることになる。
1826年にはオランダ商館長一行による江戸参府が行なわれ、シーボルトの指名を受けて慶賀も同行し、旅の先々で絵筆をとった。江戸への旅の記録をまとめたシーボルトの『江戸参府紀行』の中に、慶賀を評した次のような言葉がある。
「彼は長崎出身の非常にすぐれた芸術家で、特に植物の写生に特異な腕を持ち、人物画や風景画にもすでにヨーロッパの手法を取り入れ始めていた。彼が描いたたくさんの絵は、私の著作の中で、彼の功績が真実であることを物語っている」――。
慶賀の絵はオランダ船に乗って、ヨーロッパへ運ばれた。日本に現存する慶賀の絵は100点ほどだが、オランダを中心にヨーロッパに伝えられたものは6、7000点に及ぶと言われる。慶賀は、日本以上に西洋で評価された画家なのである。
ほとんどがヨーロッパに渡ってしまった川原慶賀の絵を見るには、どうすればよいのか……。幸いにもデジタル時代になって、距離を隔てながらも絵画にアクセスすることが可能になった。とりわけ長崎歴史文化博物館が立ち上げたサイトで、ライデン国立民族学博物館の所蔵になる慶賀の絵が見られるようになったのは嬉しい限りだ。
このサイトでは風俗画や動物画など、多様な慶賀の絵が鑑賞できる。出島のオランダ商館の様子を描いた「唐蘭館絵巻」は、特殊な風俗が知られ、西洋画風の味わいも面白いが、絵としてのみ見れば物足らなさも残る。「(日本)人の一生」というシリーズもしかりで、当時の人生模様を覗きからくりのような多彩さで見せもし、また処々に窺うことのできる遠近法の影響にも興味を引かれるが、絵そのものが感動を呼ぶようなものではない。風俗画における慶賀の作品は、歴史資料としての価値は高かろうが、アートとして見れば「並み」の印象を脱しきれない気がする。
だが、こと植物画に限っては、西洋のボタニカル・アートに引けを取らない。先に引用した『江戸参府紀行』の一文を見れば明らかなように、シーボルトははっきりと慶賀のその道における才能を見抜いていた。シーボルトはバタビアからデ・フィレニューフェという絵心のある男(専門の画家ではなかったという)を呼び寄せていたので、初めはその指導を受けたかもしれないが、植物画における慶賀の才能はじきにこの半端な「師匠」をたやすく乗り越えてしまったのだと思われる。
長崎歴史文化博物館のサイトでは、450点を超す慶賀の植物画が鑑賞できるが、ひとつひとつの可憐な命の息づきに、ため息が出る。
ハマナデシコの絵は、細い茎がすっくと立ち、その先に咲く一輪の赤い花の重みゆえか、頭を少し左にかしげている。笹舟のような葉が茎を挟んで生えるさまが、両の腕(かいな)を広げたようで微笑ましい。扇形の花弁を重ねた紅色の花はいかにも可憐だが、花弁の先に刻まれたのこぎりの刃のようなぎざぎざが個性を放っている。初々しくやさしげな娘の微笑みに、やんちゃな険が差したとでもいおうか……。
興味深いのは、艶やかな花の少し下に、先端を赤く滲ませ、ほどなく開こうかという蕾が配されていることだ。観察の賜物には違いないが、植物の成長過程を意識せずにはありえない構図だ。日本にも本草学の伝統はあったが、この絵を支える目と筆は、西洋の植物学に近いように思う。シーボルトの影響は明らかであろう。
キンポウゲの絵にも、そうした植物学的意識が透けて見える。茎の先に開く黄色い花は2輪。1輪は全体がわかるよう正面から描くが、もうひとつは敢て裏側から描いている。そして花以上に印象的なのが、ギザギザに富んだ広い葉だ。葉の形、広げ方、葉脈の走り具合、緑の濃淡など、葉の表情はいきいきとして瑞々しい。
それにしても、いずれの絵も少しも殊更でないにもかかわらず、何とも充足を感じさせる。植物画として過不足ない世界が自立している。シンプルながら、全く見飽きない。目前の対象を、一歩引いたところから虚心に見つめているのが心地よい。
一見、宗教的教理に縛られて見える中世の絵が、時にルネサンス絵画以上に心を和ませ、癒しを与えることがあるが、それと同じ理屈で、ひょっとすると、自我の勝った多くの泰西名画よりも、慶賀の植物画は21世紀の今日的な精神美学を有しているのかもしれない。
川原慶賀の絵における植物学的傾向は、根を食用にしたり、実を結ぶものを描く段になると、いっそう顕著になる。例えばニガウリ(ゴーヤー)やカシウリ(マクワウリ)などウリの類いでは、花や葉に併せて下に実を描いている。ヘチマやキュウリも、しかりだ。
ダイコンでは楚々とした白い花や葉、茎を中央に描いた下に、横たわるダイコンの根の部分をまるまる描き添えている。同じく植物を対象としてはいても、こうした絵から受ける印象は、先のハマナデシコなど花や葉だけを描いた絵に比べて、ぐっと解析的、科学的だ。
ゴボウには2通りの絵が存在する。花や葉、茎だけを描いたものと、その下に茶色の根を添えたものと―。花や葉の本体(地上に出た部分)の描き方に大きな差があるわけではないが、地下で成長する根の部分を描き加える手法は、ダイコンなどの絵と同様、植物学的な要請に沿った慶賀の習熟を窺わせる。
ヒイラギの絵では、触れればいかにも痛そうなぎざぎざに富んだ葉と、小ぶりの白い花が密生するさまを中心に描く一方で、画面の左下隅には実と種の、右下隅には花一輪のアップを添えている。蓮の一種であるベニコウホネの絵では、水から姿を出した花と茎、葉からなる全体像を描いた下に、花とその部分アップを4つも添えている。
ここまでくると、西洋植物画と比較しても、植物学的なアプローチが極めて顕著であると言わざるを得ない。シーボルトとの濃密なやりとりを感じさせるに充分だ。慶賀としても、数次にわたる「開眼」があったのではなかろうか。
シーボルトからは言葉でのみ説明を受けたのだろうか。西洋から持参した何がしかの見本となる植物画を見せられたのではなかろうか。ひょっとして、シーボルトが帰国後に編纂を期していた「日本植物誌」の構想まで教示されていたのではなかったか。シーボルトの意向を受けて次々に日本の植物を描き続けた慶賀だったが、やがて自分の絵がオランダに運ばれ、世界へ広められていくことを、説得もされ、後には自覚するようもになったのではなかろうか……。
絵はいたって静かだが、日本の絵画風土に育った川原慶賀にどのような「出会い」や「発見」があって、西洋植物画にも劣らぬ科学性や近代性を獲得するに至ったのか、それを考えれば、これほどにドラマティックな美の変容もないのである。
1828年に、長崎から出航を待つオランダ船の積荷の中に国禁の日本地図が含まれていることが発覚、いわゆる「シーボルト事件」が発生して、シーボルトは国外追放となる。この時川原慶賀も尋問されたが、事なきを得、その後もしばらくは、シーボルトの助手でその後任となったハインツ・ビュルゲルを介して慶賀の描く絵がオランダへ送り続けられた。
そうした慶賀の絵をもとに、シーボルトは日本の植物を150点のカラー図版付きで紹介する『フローラ・ヤポニカ(日本植物誌)』をまとめ、1835年から1870年にかけて30分冊で刊行する。日本の植物を世界に紹介する、初の本格的な植物画集であった。
図版の制作に際し、シーボルトはドイツ人の画家に慶賀の素描を下絵にして描き直させている。実や種子の部分アップを画面に添えるなど、当時の西洋植物学の最前線に立つ出来ばえとなったが、生きた植物をじかに写生した慶賀の原画の正確さ、精密さが、功を奏している。慶賀が生前に『フローラ・ヤポニカ』を目にすることはなかったであろうが、慶賀の絵があればこそ、日本の植物研究の金字塔と言われ、植物画集としても歴史に残るこの偉業も陽の目を見るに至ったのである。
一方で慶賀は、1836年に『慶賀写真草』を刊行している。息子の盧谷の手を借りながら共同作業でまとめた薬用植物図鑑の木版冊子である。ここで言う「写真」とは、正確に写す、写生することを意味する。単色刷りなので、『フローラ・ヤポニカ』に見られる華やかな美しさは見られないが、シーボルトから教わった解析的な西洋の植物学の手法が随所に活かされている。いやむしろ、慶賀はここでは絵画(アート)としての美を極力抑えることで、薬用植物を紹介する実学に徹しようとしたようにすら思える。
慶賀の真骨頂は、シーボルトという巨人に寄り添いながら、植物を真摯に写していた、その絵にこそある。『フローラ・ヤポニカ』では、縁の下の力持ちのようなかたちで活躍するしかなかった慶賀だが、オランダのライデン国立民族学博物館に多くの絵が保存されてきたのは幸いであった。
実はライデンだけでなく、千点を超す慶賀の植物画を保存している場所がある。サンクト・ペテルブルクにあるロシア科学アカデミー・コマロフ植物研究所。シーボルトの死後、未亡人がロシアの科学アカデミーに売却したものが伝わっている。植物の種が風に乗り、他所に伝わって異郷の土に根を張るのと同じく、慶賀の植物画もまた海を越え、世界に根を下ろしたのだ。
『バンクス花譜集』の展覧会に啓発されて、この冬から春、長崎歴史文化博物館のサイトに繰り返しアクセスしては、ライデンに伝わる慶賀の植物画を鑑賞した。新たな植物の絵が開かれた瞬間、その素晴らしさに目を瞠ることしばしばだった。植物標本などとは全く異なる生き生きとした命の輝きに、思わず胸を熱くした。
ズネゴ(カラスムギ)の、小さな釣鐘(小穂と呼ばれる)をいくつもぶら下げたような姿も、実に印象的だ。艶やかな花に見慣れた目にも、はっとさせられる。姿のおもしろさに加えて、風のそよぎまでもが感じられる。ここでは、写すという行為を、アートする心が支えている。
センニチソウの、細い茎の先に咲くぼんぼりのような丸い赤紫の花の、これはまた何と可憐なことだろう。道端で目に触れても、そのまま見過ごしかねないほどの楚々たる存在に違いないのだが、慶賀の筆にかかれば、その愛らしさにおのずと微笑みがこぼれる。
ノコギリソウでは、ムカデのように細かなギザギザを連ねた葉が、今にも踊り出しそうな躍動感に満ちていて、見る者の胸を弾ませる。群生する小さな黄色な花の印象が控えめな分、くねくねと身を躍らす葉の動きは、マティスの「ダンス」さながらだ。
写すことに尽くそうとした慶賀の視線は、どこまでも真摯かつ謙虚である。しかしその心は、ただ淡白なだけではない。対象となる植物に、充分に興趣を感じている。その命の息づきに、胸をときめかせている。眼前の草花と、命をこだまさせているのだ。その意味で、慶賀は植物画の王道を行っている。
1842年、長崎港を描いた風景画の中に、警備に当たる鍋島藩と細川藩の家紋が描きこまれていたことが問題視され、慶賀は長崎から追放されてしまう。その後の消息はよくわからない。没年も、墓所もはっきりとしない。
長崎近郊の野母崎に観音寺という寺があり、1846年の完成になる本堂の天井は150枚の花卉図からなるが、この中に慶賀のものが4点あるという。植物画に最も輝きを見せた画家・川原慶賀の最後の意地だったろうか……。
長崎という特殊な舞台に生きたため、東西交流史の一幕に、シーボルトの目をつとめた絵師として登場させられることが多い慶賀。だが、写真機代わりのアルチザン絵師という既存のイメージを超えて、世界が認めた植物画のアーティストとして、慶賀は復権を待っている。緑の園たる地球という星のボタニカル・アートの歴史において、川原慶賀こそはまぎれもない巨匠であると、私は信じてやまないのである。