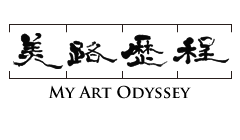

外には燦々とした陽光が溢れている。無窮の青空の彼方には、白波を返す海原が広がり、鳥や獣、虫の棲む緑の深い森があり、人々の集う広場もある。
しかし、光彩陸離たるそのような景色は、色を喪い、記憶のなかに閉じ込められてしまった。コロナを恐れ、家に立て籠もる人は少なくない。東京に暮らす知り合いの老人は、春以来、家から一歩も外に出ていない。そのストレスは重しとなって、心に鬱を溜め込むことになるだろう。
そのような人に、この絵を薦めたい。「色彩の魔術師」と呼ばれたラウル・デュフィ(1877〜1953)の『画家のアトリエ』(1935 フィリップス・コレクション)──。
タイトルにあるように、ここは画家自身のアトリエである。2つのイーゼルがあり、1つには描きかけの女性のヌードが置かれている。壁や床、奥の部屋にも、いくつもの絵がある。画布に描かれた建物や運河、船……。青空が透けてきたように、部屋の多くが水色に染まる。奥の部屋はバラ色や茶色に塗られている。窓枠やカンバス、扉など、四角四面の矩形が目立つが、それでいて、角ばった堅苦しさなど微塵もない。
妙に、楽しくなってくる絵だ。見ているだけで、ウキウキしてくる。踊りだしたくなるような、明るい軽快さがある。スウィングする感覚とでも言おうか。ジャズが聴こえてきそうだ。音楽に乗って、どこからか声が流れてくる。「この世は美しい」──。
デュフィはフランス北西部、大西洋に面した港町、ル・アーブルに生まれた。貧しいながらも音楽を愛好する一家で、父は教会でオルガンを弾き、指揮をした。母はヴァイオリンを奏でた。デュフィの絵に音楽を聴くような感覚が溢れているのは、幼少期の家庭環境と無縁ではないだろう。デュフィ本人は、「絵画はオーケストラの楽譜」だと語っている。
デュフィが描いた『画家のアトリエ』というタイトルの作品はいくつかある。だが、デュフィは決して狭い意味での室内画家ではない。自然の風景も、都市の景観も、人々も、静物も、コンサート会場や競馬場に至るまで、貪欲に描いた。決して、北欧の室内画家・ハマスホイのような、インテリア画の専門家などではなかった。
それでいて、今私が特にデュフィの室内画──それも、室内から屋外を覗く絵に惹かれるのは、内と外が混然一体となって輝く小宇宙を形成し、そこに生命の息づきが満ちているからだ。ふさぎがちな心の重しを撥ね退け、口笛でも吹いて、スキップでもするような、軽やかな気分にいざなってくれるからである。
この絵でも、窓から向かいのアパートが見える。土色の建物の上に青空が覗く。窓にはガラスが嵌め込まれているに違いないが、透明で、その存在を感じさせない。向かいのアパートとの間の、空気すらも感じない。建物と青空がストレートに、こちらの室内にまで飛び込んでくる。
内と外の境が曖昧になり、ひょっとすると、ボタンひとつ押せば、するすると壁が上にあがって、遮るものは全くなくなってしまうような気にさせられる。内にありつつ外と息を重ね、外は内にまで波のように押し寄せるのだ。
よく見ると、外から侵入した青色が、実際のフォルムをはみ出して浸潤している。青の洪水──デュフィの絵には極めて特徴的な青の広がりである。
青……ヒヤシンスの青。ベリーの青。オオルリの青。アオスジアゲハの青。ネオンテトラの青。サファイアの青。彼女の瞳の青。空の青。海の青。地球という星の青……。そうだ、宇宙飛行士のガガーリンは言ったっけ、「地球は青かった」と──。
1枚の画布が、人工衛星とこだまを交わし合う。そして私は、1枚の絵によって、この星に息づく生への信頼を取り戻す。
デュフィの絵に導かれ、海辺や高原でマスクを外した時のように、新鮮な空気を胸いっぱいに吸おう。自然界の輝きを、日光浴をするように、全身全霊で浴びるのだ。そして呟こう。ああこんなにも、この世はみずみずしい生命に満ち溢れているのか!
改めて、芸ア ート術の力を思う。芸術に感謝。デュフィに感謝。この星に感謝……。デュフィの絵から聴こえるスウィングするリズムに、いつしか胸ははずみ、おのずと腰は揺れ始める。光と色のハーモニーにたぎる生の歓びが、明日への活路を鼓舞するのだ。