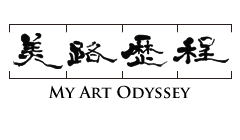

子供に自由に絵を描かせると、空に真っ赤な太陽を添えることがしばしばある。「御日様」という言葉があるくらいなので、子供心に、陽射しに満ちた昼の空にはあってしかるべきものと心得られているのだろう。
子供の絵ならば、微笑んで見ていられるが、美術作品の絵画で空に太陽を配するとなると、実は相当に難しい。意味づけというか、かなりの覚悟を定めていなければ、陳腐なだけである。
虹にも同様のことが言えそうだ。広い蒼穹にかかる虹はヴィジュアル的には充分に魅力的だが、そう頻繁には登場させられない。
自然現象としても、そう滅多に出現するものではないことにもよるが、下手に描けば絵は安直、月並みに堕してしまう。そういう危うさを抱えつつも、しかし、さすがに名匠たちは味わい深い虹の名画を描き出した。
初めに、フランドルの巨匠、ピーテル・パウル・ルーベンス(1577~1640)の『虹のある風景』を見よう。1636年頃に描かれたというから、巨匠晩年の作になる。ロンドンのウォレス・コレクションが所蔵するが、いかにも名画の風格に溢れ堂々とした傑作だ。
画家の暮したフランドルの風景である。画面右側に森、左に移るにつれ平野がひろがる。手前の水辺には牛やアヒルの群れ。水際の道を男女の農夫たちが歩き、干し草を積んだ馬車と行き交う。
ごく日常的な自然の風景である。同じ風土を描いたブリューゲルとの近似を思わせもする、農民たちの大地の姿である。
面白いのは、登場する農民らの表情だ。よく見ると、農民たちの間に感情の行き来があり、視線のベクトルが交差していることが読み取れる。
中央の3人連れのうち、真ん中の鋤を手にした男は、自身の隣を歩く、頭に金属器の水がめを載せた青い服の女性に言い寄っている。「なあお前さん、そういつまでも固いことを言わんでもいいじゃないか。そろそろ俺の思いを受け入れてくれよ」とでも言っているかのようだ。
女性は水がめを頭上に載せていることもあって、姿勢を崩さず、緊張を解く気配がない。しかしその表情は、男から恋心を聞かされ、まんざらでもなさそうだ。
3人組の左端、朱色の服を着た女性は、馬車を駆る男と視線を交わしている。男が笑いながら声高に女に話しかける。「仕事を終えたら、後で訪ねて行くからな。ふたりきりでたっぷり楽しもうや」――とか何とか、かなり露骨な表現で男は戯れ言を弄しているかに見える。女のほうも堂にいったもので、「何を言ってんだか。どうせあっという間に沈没じゃないか!」とでも応酬しているのだろう。
「相関図」をより鮮やかに仕立て上げているのは、水辺で牛の群れを追う男の存在である。手に握った棒で牛を御する方向とは逆に、視線は3人連れの方を向いている。
おそらくこの牛追いの男は青い服の女に気があり、鋤の男に言い寄られているのが気になって仕方ないのであろう。女が口説き落とされてしまうのではないかと、はらはらドキドキ、牛追いの仕事をしていても、気が気でないのである。
そういう、男女のバチバチな視線、エロスの感情の交差が、大地に繰り広げられている。素朴にして健やかな生の姿。性もまた、ミツバチが蜜をつくるほどに、自然な風景を描く。
そして、すべてを見通すかのように、空には七色の虹が輪を描く。命あるものに祝福の賛歌を贈り、にっこりと天が微笑むかのようだ。
なお、この絵が湛える自然体のエロスと幸福感は、画家自身の私生活と関係があるように思う。ルーベンスは1626年に最初の妻イザベラをペストで喪い、4年後の1630年に、53歳にして16歳のエレーヌ・フールマンと再婚している。
エレーヌはしばしば晩年の画家の作品にモデルとして登場することになるが、仲睦まじさを象徴するように、都合10年間に及んだ結婚生活で、5人の子供を産んでいる。最後の子は、ルーベンスが亡くなった時にまだ生後8か月だった。
若妻を想う気持ちと官能の愛の充実が、この絵が湛えるほのぼのとした幸福感の源泉であったのだろう。
神話世界にも虹が登場する。宗教画に虹が現れた場合、次に見る神話との関連による。
実際の絵で説明しよう。チロル出身の風景画家、ヨーゼフ・アントン・コッホ(1768~1839)が1803年に描いた『ノアと風景(ノアの献げ物の風景)』――。
長老を中心に男女の一行が火を焚き、水辺に集う。家畜を伴う男たちもおり、周囲には多くの動物もいる。これだけでは、絵の内容を把握することは難しかろう。しかし、中央奥の山上に、黒っぽい巨大な木箱が乗り上げているのに気づけば、たちまちにして画題が何か、氷解することになる。
巨大な箱は、旧約聖書の創世記に登場するノアの箱舟なのである。地球を襲った洪水を、箱舟に乗ってかろうじて難を逃れたノアの一団。今ようやく洪水が退き、ノアが率いる人間や動物たちは、箱舟から外に出た。そして、火を焚き、神に感謝の祈りを捧げているのである。
では何故、ノアの箱舟のエピソードを描いたこの絵に、虹が現れることになるのだろうか――? それは、創世記9章13節から17節で語られる「神との契約」において、虹が重要な役どころを担うからである。
神は言う。「私は雲に虹を置く。これが私と大地の間にたてた契約のしるしである。私が雲を地の上に湧き起こすと、雲には虹が現れる。そして私は、あなたたち及びすべての生き物、あらゆる肉なるものとの間にたてた契約に心を留める。水が洪水となって、肉なるものすべてを滅ぼすことは、もはや決してない。雲に虹が現れる時、私はそれを見て、神と地上のすべての生きもの、すべて肉なるものとの間にたてた永遠の契約に心を留めるのだ――。
多くの命の犠牲の果てに、神は肉あるものの生を認める。神と地上の命あるものとが和解する。その和解の契約のしるしが、虹なのだとされる。
つまり、コッホのこの絵に虹が描かれたのは、肉あるものたちは救われたという、神の契約が示されたことを意味するのである。
19世紀にナポリで活躍した画家ドメニコ・モレリ(1823~1901)が描いた『箱舟を出た後のノアによる感謝の祈り』(1901?)では、生き残った動物たちが今まさに箱舟から出てくる様子を描いており、状況をよりわかりやすく伝えている。
高い岩場に乗り上げるように停止した箱舟の背後から、空に大きく半円形に虹がかかる。人間と動物がこの世に生きて行くことを認めた、神の契約のしるしである。
ちょっと不思議な気がするのは、コッホにしてもモレリにしても、ルーベンスから200年ほども後の時代の画家だということである。旧約聖書に忠実に描いたわけだろうが、世俗世界を生きる農夫らに虹の微笑みを付与したルーベンスのほうが、よほど時代の先を行っている。
さて、虹が雨上がりに現れることは、日本人であるなら等しく理解していると思うが、私の経験では、英国のスコットランドを旅した時ほど、多くの虹と出会ったことはなかった。
山と谷がつらなり、しかも雨が多く、天気が変わりやすい。15年あまり前、商業都市のグラスゴーから北西部の港町オーバンまでバスに乗ったことがあるが、大粒の雨が車窓を叩いたかと思いきや、ひとつ谷を越せば嘘のように晴れ間が広がり、美しい虹が山の端に姿を見せた。つづら折りの山路を行くバスの進行と、天候の変化が重なり合って、まるで山里ごとの道しるべのように、いくつもの虹が迎えてくれたのである。
このスコットランドを始めとする英国の虹の風景を、神話や伝説によらず、まさに自然現象の奇特な光景として迫真の力で迫ったのが、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775~1851)である。
ロンドンの下町育ちながら、ヨーロッパの各地を旅して独自の風景画を描き続けたターナーにとって、湿潤の大気に神秘の風景として現れる虹は、恰好のモティーフであった。名だたる画家のうち、虹に魅せられた巨匠として、筆頭格にあげられる。
『キルチャーン城とクルチャン・ベン・マウンテンズ、スコットランドの正午』(『Kilchern Catsle With The Cruchan Ben Mountains Scotland Noon』)は1804年の作品になるが、廃墟の名城を囲む山々や湖の上空に、半円形の見事な虹がかかる。この絵の虹は、私自身がスコットランドで見た虹の印象に最も近い。
1831年頃に描かれた『ロッホ・オー(オ―湖)にかかる虹』(『Rainbow over Loch Awe』)では、湖の上に漂う大気の中に光の輪を浮かびあがらせたような雰囲気が個性的である。
風景を風景としてリアルに描くというより、その印象を極限にまで突き詰めようとする意志が画面にみなぎっている。半世紀ほど後のセザンヌが、飽きもせずにリンゴの静物画を繰り返し描き続けたのにも似て、ターナーも虹を素材に、大気の中の光の屈折や色彩の放射、空気感といったものを、画布の上で確認し、極めようとしているかに見える。
『虹』(『The Rainbow』)という、そのものずばりのタイトルを冠した作品もある。1820年頃に描かれたというが、もはやスコットランドであるとか、山とか湖、古城などはどうでもよくなって、虹を素材に、画家の腕の限りを尽くして、光のエチュードを奏でているかのようだ。
ターナーは早熟の才能を見せ、ロマン主義の画家としてスタートを切ったが、何々主義、何々派などという既成の枠にはめることの難しい孤高の境地を進むことになる。
それはまた、印象派の先駆者として道をひらくことにもつながった。彼を魅了してやまなかった虹の絵を追っただけでも、そのことは充分に見てとれる。
最後に、我らが日本の虹の絵を見ておこう。素材的には何でもござれの浮世絵に、やはり虹も登場していた。
まずは、歌川国芳の『春の虹げい』――。普通に考えれば、風景をワイドに眺めたところで、天空に虹がかかるというのが、常套の描き方だろう。しかるに国芳のこの絵は、今まさに鰻のかば焼きに食らいつこうとする女のアップが主で、女がふと空の虹に気づいて視線を動かす瞬間を描いている。
古今東西、およそ虹を描いた絵で、これほどに人物が中央を占め、虹が脇役として画面端に添えられた例はないだろう。奇想で知られた国芳ならではの、嬉しい驚きに満ちた虹の絵だ。なお、人物の下が半円形に切れているのは、この絵が、もともと団扇の張り絵用に描かれたことを物語っている。
その真逆、空にかかる虹が主役の至極まっとうな風景画も、国芳にはある。『東都名所するがだひ』――駿河台を行く主人と従者の彼方の空に、虹が堂々と描かれる。
従者が指をさして、「旦那、虹が出てますぜ!」と声をかける。主人はその言葉に、手を額にかざして遥かな虹を仰ぐ。従者がたたんだ傘を肩に担ぎ、向こうからこちらへ歩いてくる男も傘をすぼめようとしているところを見ると、今しがた、雨がやんだばかりと思われる。
今の駿河台からは想像がつきにくいが、「台」と名のつく、景色が開けた場所だけに、空にかかった虹はさぞや美しく、見事だったのであろう。
浮世絵における風景画の天才と言えば、歌川(安藤)広重(1797~1858)がいるが、彼にもやはり虹の絵がある。『名所江戸百景 高輪うしまち』――。
17世紀の前半にあたる寛永年間に、江戸高輪の増上寺安国殿の普請のために、京都から多数の牛車が取り寄せられた。牛車が集められた場所は、以後、「牛町」という地名がつけられたが、広重のこの絵では、その故事来歴を踏まえて、牛車の輪が手前に描かれている。
また、「高輪」という地名の「輪」に引っかけて、牛車の輪をフィーチャーしたのでもあった。言葉遊びだけでなく、確かに、この絵ではフォルムとしても輪がいくつも重ねられ、こだまを交わし合う。牛車の輪。虹の輪。食べ残しのスイカの皮の輪……。半円形が交差し、交響楽のような厚みを出している。
海を望めば、沖合には、いくつもの帆かけ船が停泊している。品川沖のお台場も見える。これは1853年のペリー来航後に工事が始まり、翌54年に竣工したものだ。そういう時事性までをも加味して、広重は夏の夕方の雨上がりの情景を描く。
面白いのは、人はいっさい登場しないことだ。夕立がやってきて、そこにいた人々は皆、家の中やひさしのある場所へと避難したのであろう。岸辺でスイカを食べていた人(食べ残しが2つあるので、男女のカップルであろう)も、取り急ぎ、雨を避けてその場を離れた。
ようやく雨はあがったが、まだ人々は戻ってきていない。犬だけは、早くもその場に現れている。だが、犬がくわえているのは草履で、先ほどまでは人の脚に触れていたものなのであろうが、今はもぬけの殻で、ここでも人はオフ扱いをされている。
そういう、人々の存在を徹底してオフにし、雨上がりの「静」が景色を支配するなか、無言のページェントのように虹が空にかかるのである。
見事としか言いようがない。『江戸名所百景』は1856年から58年にかけて描かれ、広重最晩年の傑作と呼ぶにふさわしい作品群を集めている。画業の集大成となるさまざまな工夫が凝らされ、高い芸術的境地に達している。
明治維新まで10年――。広重の虹は、どこか此岸から彼岸へとつなぐ趣を擁しつつ、江戸から明治へ、近世から近代へとつなぐ橋渡しとして、天空に輝いているのかもしれない。