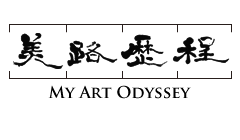

イギリスに10年暮らしながら、ロンドン大学に付随するコートールド美術館には行きそびれてしまった。改築工事で休館中であるのを機に、この秋、来日を果たしていると聞き、早速出かけてみた。
東京都立美術館の会場に足を踏み入れてみて、驚いた。後期印象派の作品が多いことは知っていたのだが、並みいる巨匠の中でも、セザンヌの扱いは特別だった。静物画、風景画、人物画など、油彩だけで10点の力作が並ぶ。コレクションのひとつの柱がセザンヌなのである。
コレクションの創始者であるサミュエル・コートールドが、1922年、ロンドンでの展覧会でセザンヌの風景画を目にし、気に入ったのが収集を始めるきっかけだったというが、母国フランス以外で、これほど充実したセザンヌのコレクションを保持している美術館は稀であろう(イギリスだと、バーンズ財団美術館がやはりセザンヌ作品を多く所持している)。
ちょうど、その人の静物画についてアーチ誌に書いたばかりであったこともあって、私の目は否応なくセザンヌ作品に集中することになった。静物画について自分なりの見解が定まるまでにも相当の時間がかかったが、セザンヌはそれをもって手を離してはくれないようであった。ひと夏の間、フィリップス・コレクションの『ザクロと洋梨のあるショウガ壺』の写真を眺め続け、その静物画を理解しようと努めたが、今度は、コート―ルド美術館が所蔵する真作の傑作群を前に、セザンヌへの眼差しを研ぎ澄ますこととなった。
セザンヌは徹底して対象を見つめ、凝視の中からおのれのヴィジョンを探り当てた人だった。その集中力と執拗さは、画家たちの中でも図抜けており、そこに彼の芸術家としての核心部分も存在し、またそれゆえにこそ、「近代絵画の父」として後世から崇敬を集めることにもなった。
リンゴや果物などの静物、そしてプロヴァンスのサント=ヴィクトワール山などは、何度も繰り返し描かれ作品化されたが、そういう姿勢こそがまぎれもないセザンヌであるとして、称揚されたのである。その人生にはゴッホのような「派手さ」はなくとも、画業を貫く過激さでは引けを取らず、通好みの画聖となっている。
納得のゆくまで、対象と対峙し、見つめ、キャンバスの前から離れようとしないセザンヌである。対象が、リンゴにしろ山にしろ、動かぬものであるうちはよい。だが、人物画、肖像画となると、そうは行かない。
画商のヴォラールはセザンヌによって肖像画が描かれたひとりであるが、ヴォラールの残した証言によれば、1枚の肖像画を描くのに、画家の前で数時間ずつ115回もポーズを取らされたという。しかも、少しでも動こうものなら、「リンゴは動いたりしない!」と怒鳴られる始末。相手が人間であろうと、セザンヌは彼独自の手法を貫き、手を抜くということを知らなかったのである。
さて、コートールド美術館展では、2点の人物画が出品されていた。『パイプをくわえた男』(1892~96頃)と『カード遊びをする人々』(1892~96頃)――。
興味深いのは、単独の人物肖像画として画面に収められたパイプをくわえた男が、2人の人物を描いた『カード遊びをする人々』でも、テーブルの左側に腰かけたプレイヤーとして登場していることである。
しかもセザンヌは、この絵と同工異曲の、カード遊びに興じる田舎の男たちの絵を、繰り返し描いているのである。2人の男がカード遊びをするバージョンが3点、3人の男のバージョンが2点伝わる。男たちはいずれも、セザンヌが父から譲り受けた別荘のジャス・ド・ブッファンで働く労働者たちであった。
肖像画、人物画に於いても、セザンヌの反復志向は踏襲された。セザンヌは、どのジャンルに於いても、徹底してセザンヌ流を貫いてやまなかったのだ。
セザンヌの描いた肖像画は、自画像を含め、200点近くあるという。セザンヌと言えば、まずは静物画と風景画をイメージする人が多いが、当人は、画家の本能として、人を描くことにも積極的だった。
その中で、自画像と並んで、最も数多く描かれた人物は、妻のオルタンス・フィケであった。自画像が26点、オルタンスが29点とされるから、自身の姿を含め、セザンヌが最も数多く描いた肖像画は、オルタンスのものだったことになる。繰り返し描くというセザンヌの絵画原理を、肖像画において一身に引き受けることになったのが妻だったのである。
セザンヌがオルタンスをモデルに選んだのには、理由があった。若くして出会った頃から、オルタンスはモデルのアルバイトをしていたが、その特徴は、長時間じっと動かずにポーズを構えることができることだった。モデルが動いてポーズが崩れれば、「リンゴは動かないぞ!」と怒鳴ったというセザンヌである。オルタンスが他人には代えがたい不動のモデルとなったのは、まさに動かぬがゆえであった。
夫婦の共同作業から、どのような作品ができあがったのか、代表的な1点を見てみよう。ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵する『赤いドレスを着たセザンヌ夫人』(1888~90頃)――。
ひと目見て誰もが感じるのは、並の肖像画からは懸け離れた何がしかの新しさであろう。対象となる人物を、個性豊かな生き生きとした姿として捉え、人格や内面まで汲み取って画布に写すといった、レンブラント以来、私たちが肖像画に対して抱いてきたイメージを裏切る、それでいて、凡庸でない、緊張感に満ちた強い印象を与える仕上がりなのである。
主人公であるはずの彼女の印象以上に、その衣装やポーズ、色合いなどが、周囲の物――腰かけた椅子の背や後ろの壁、カーテン、窓や暖炉の一部などととともに、それぞれに自立しつつ、互いに調和を見せたり反発し合ったりして、主張を繰り広げている。
ちょうど、静物画においてリンゴやテーブルクロス、壜などが、それぞれに自己主張を展開していたように、妻を描いた肖像画においても、セザンヌは視点や視界をめぐる実験的なコンポジションを形成している。形と色あるものが放つ放縦なベクトルを、もう少し押し進めれば、キュビズムに行き着くしかないであろう、そのぎりぎりのところで、絵をまとめているのだ。
そのいう、ラボラトリーでの観察結果のような絵に肖像を提供した妻は、長時間の製作にもよく耐えて、無表情を固めている。そこだけを見れば、夫の革新的な画業に献身的に協力する妻と、素晴らしきパートナーシップに思えるかもしれない。
だが事実を言えば、夫婦関係は冷えきっており、夫は家を出て別居状態を続けているにもかかわらず、肖像画を描くにあたって必要な時だけ、モデルをつとめるよう妻を呼び出すのである。妻もまた、この時だけは、我が出番とばかりにアトリエに出向き、筆をもつ夫の前で、黙然とポーズをとり続けたのである。
世間の常識からすれば何とも奇妙な、およそ他人には理解不能な夫婦であったに違いないが、セザンヌはこの不思議な関係の上に、肖像画というジャンルに於いても、革新的な近代絵画を創造しようと努めたのだった。
ふたりの出会いとその後の足跡をたどってみよう。
1869年、セザンヌはパリのアートスクールでオルタンス嬢に出会った。この年、セザンヌは30歳、オルタンスは11歳年下の19歳だった。彼女は製本の仕事を本業としながら、アルバイトでモデルをしていた。
翌年には恋仲になり、同棲を始め、1872年には息子のポールをもうけるに至る。しかしセザンヌは、オルタンスと息子の存在を、銀行家の父には秘したままだった。父の機嫌を損ね、毎月手にする仕送りが途絶えるのを怖れたからだと言われる。オルタンスは日陰の身ながら、若きセザンヌを支えた。
『赤い椅子に座るセザンヌ夫人』(1877 ミュージアム・オブ・ファイン・アーツ、ボストン)は、セザンヌがオルタンスを描いた最も早い時期の肖像画のひとつである。
一見して、印象派らしい仕上がりの絵で、多様な細かい色づかいが著しい。全体としては淡い色彩感が作品を包む。椅子や背景の壁、オルタンスの衣裳やフォルムなど、静物画のような印象を与える肖像画だ。
正規の結婚はしていないが、息子を産んで5年、オルタンスも日々の暮らしの中に落ち着きを見出したように見受けられる。柔和で、静かな印象の絵だ。
この時期は、セザンヌが印象派に寄り添った時代の最後にあたる。1877年、第3回印象派展に出品したセザンヌの作品を見て、幼なじみで作家のゾラ(後に対立し、仲たがいをする)は、「セザンヌは、間違いなく印象派のグループの中で最高の偉大な色彩画家である」と評した。そういう雰囲気を、この絵も湛えている。
ところが、やがて印象派を離れるのと軌を一にするように、セザンヌのオルタンスへの愛情は冷めてしまう。別居状態が普通となり、いびつな夫婦生活が続いた。別居の理由はもっぱら夫の側にあり、いつでも自由に外出し、野にあって思う存分に絵を描けることを欲したからだという。
1886年になって、息子への相続に関する法的な必要性からセザンヌは正規にオルタンスと結婚するが、その際にも、「彼女に対し、もはや何の感情も抱いてはいない」と公言する始末。
同じ年、父が死去すると、セザンヌは妻のもとを離れ、母親や妹たちと一緒に暮らし出す。この時にも、「妻はスイスとレモネードにしか関心がないのさ」と放言して憚らなかった。オルタンスの故郷がスイス国境近くで、アルプスの麓での暮らしやそこでのカフェ通いを愛したことに対する揶揄である。ちなみに本人は、光と色彩に溢れた南仏プロヴァンスに夢中だった。
ふたりの間に違いや差はあったに違いないが、それにしても、セザンヌの口から出た言葉は、オルタンスに対し、ひどく冷たい。
印象派の女流画家メアリー・カサットによれば、セザンヌはどのような時でも紳士的で礼儀正しかったというが、妻のオルタンスに対しては、手のひらを返したように、冷淡で思いやりがない。
だが、それでいて、セザンヌはオルタンスを必要とした。肖像画を描く段になると、別居中の妻に連絡をとり、アトリエまで足を運ばせたのである。
しかも、29点ある妻の肖像画のうち、製作が集中するのは、1880年代から90年代にかけてで、これは、もう愛が冷めたと公言した時期に他ならない。女性として、妻としてなら、愛情は枯れてしまったものの、オルタンスはみずみずしい永遠のミューズとして、セザンヌの創作意欲を刺激し続けたのである。
興味深いのは、同じ衣装をまとった肖像画が、違う年にも描かれていることである。例えば、先に見たメトロポリタン美術館の『赤いドレスを着たセザンヌ夫人』(1888~90頃)でオルタンスが来ていた赤い衣装は、3年から5年後に描かれた『黄色い肘掛け椅子のセザンヌ夫人』(1893~95 個人蔵)という作品でも使われており、これはおそらく、アトリエに呼ぶにあたって、セザンヌが例の赤いドレスを着て来るようにと、オルタンスに注文を出していたことを窺わせる。
つまり、セザンヌはここでも例の「反復」を試みていたわけである。前者は正面からの絵で、後者は斜めから見た絵になっている。リンゴをあっちに置きこっちに並べと、コンポジションの変奏に余念がなかったように、セザンヌはオルタンスを借りて、肖像画における変奏を試みているかに思える。
なお、後者の作品では、オルタンスは殆ど
画家として、夫として、2重のエゴイズムが支配する製作現場で、オルタンスは妻としての不幸や屈辱に耐えつつ、不動の姿勢で、抉るような画家の眼差しを全身で受けとめていたのである。
見ようによっては、サドマゾの究極の姿にすら感じられなくもない。全くもって、セザンヌという画家の業の深さは、尋常の物差しでは測りしれない。
2014年11月から翌年3月まで、ニューヨークのメトロポリタン美術館で「セザンヌ夫人、オルタンス・フィケの肖像」展が開かれた。セザンヌが妻オルタンスを描いた29点のうち、24点をそろえる画期的な企画展だった。
2017年には、パリのオルセー美術館で特別展「セザンヌの肖像画展」も開催された。これまで静物画、風景画が中心だった世の中のセザンヌへの関心が、このところ肖像画に向かっているようだ。わけても、オルタンスを描いた作品群への関心はつとに高まりつつある。
そうした流れのきっかっけを作ったのが、2009年に出されたスーザン・シドラウスカスの著書『もうひとつのセザンヌ~オルタンスの肖像』であった。それまで、絵に描かれた無表情、不愛想なさま、そして愛を伴わぬ形ばかりの妻であったことから、取るに足らぬものとして無視されがちだったオルタンスの存在を、画家にとっての「ミューズ」として捉え返したこの書が契機となって、一連のセザンヌ夫人の肖像画が見直されることになったのである。
もちろん、そこにはフェミニズムの影響もあろうが、若い日のスケッチなどをあげて、実は妻への愛も豊かだったとするようなロマンティックな見解には、もろ手を挙げて同意しがたい部分もある。だが、オルタンスのミューズとしての役割を強調している点は、大いに評価したい。
予見を廃し、虚心にセザンヌ夫人の肖像画を見つめると、木偶であったり仮面のようであったりする表情が、何がしかを物語っていることに気づく。無表情が語る雄弁さに、時に身の震えるような思いを得る。
『温室のセザンヌ夫人』(1891~92 メトロポリタン美術館)は、いかにもそのような傑作である。土を思わせる黄土色の背景に、樹木や鉢植え、花などを配し、土色に赤みをさしたような顔色の夫人がこちらを向く。
従来のセザンヌ評者は、夫人と背景の考えぬかれた配色や構図の妙を説く。だが私の正直な印象では、それ以上に、訴えかけるような夫人の表情が目を射貫く。
決して生き生きとした豊かな表情とはいえない。むしろ、内なる思いを押し殺したような絶対的無表情である。諦念を感じさせるが、どこか無抵抗の抵抗のような女性の意志をも感じてしまう。
女性として、妻として、夫に対し言いたい思いは山ほどにあったろう。不平不満を並べたてたなら、夜が明けても尽きぬに違いない。エゴイストの夫に、飛びかかり、つかみかかりたいような怒りは全身にたぎっていたはずだ。
しかし、彼女はすべての激情を押し殺して、画家の前にモデルとして坐っている。すべての言葉を呑み込み、あらゆる動作を停止して、画家と対峙している。そのようにしてでなければ、夫とまみえる機会がないことを、妻は知りぬいていた。
見つめ見つめられるという互いの視線が交差する。画布を筆が這う音だけが耳立つ絶対的な沈黙の場は、夫と妻との間に火花の散るような出会い、対決の時でもある。氷のような冷たさが支配する中に、
夫が妻を求める唯一の時。妻が夫に望まれるその場限りの舞台……。あたかも、明日地球が滅びると知って、この時とばかりに雌雄が交わる、そのような熾烈さが
色彩、形、構図……画家の頭の中は、おそらくこれでいっぱいなのである。だが、描く対象となる人間は、物ではない。人はリンゴとは違う。壜やテーブルクロスでもない。
画家は、非人情な眼差しと筆遣いに徹しようとするが、水が指の間からこぼれ落ちるように、人の人たるところが画面からにじみ出る。夫人の胸に巣くう憂鬱の思いが、画家の構えるエゴイズムの枡からあふれ、こぼれ出る。
ひょっとして、との思いが頭をよぎる。色と形のコンポジションに拘泥しているようでいて、セザンヌはその実、夫人の憂いを見抜き、内なる嘆きの声に耳を傾けていたのではないか。
――さあ、見て下さい。穴のあくほどに、しっかりと見つめて下さい。これが、あなたによって不幸に突き落とされた女の偽らざる素顔です……。
その声ならぬ声を、セザンヌは聞きつけ、胸の内に拡大して、渦を巻く大エコーの響きの中に、絵筆をとっていたのではなかったろうか。
思い出していただきたい。先に見たパイプをくわえた男やトランプに興じる男たちも、憂いに沈み、諦念のなかに生を重ねるかのように見えた。
セザンヌにとって、画布にとどめたいと欲する人物像の典型とは、現実社会の労苦に疲弊し、憂鬱を溜め込みながら、なおも生きようとする人間だったのではなかろうか。そのように生きる人間こそが、セザンヌが画家として信じるに足る肖像画の対象だったのだろう。だとしたなら、自分に対して満腔の不幸を訴えてくるオルタンスという存在こそは、第一に肖像画として描くべき「聖女」だったことになる。
並の男ならば、自分のせいで不幸をかこつ女など、しんどいばかりで、離れたいと望むことだろう。現に、男、夫としてのセザンヌは、オルタンスから逃亡をきめこんだ。
だが、画家としてのセザンヌは、逃げようとしなかったのである。むしろ、不幸の塊のような妻を、自ら求め、目の前に座らせて、積極的に描き続けたのである。かくて、オルタンスはセザンヌの肖像画における「聖女」となり、「ミューズ」となった……。
一連のセザンヌ夫人の肖像画は、世にも奇妙な男女の物語の産物である。それは、断崖絶壁に立つようなきわどさを有し、真剣での立ち合いにも似た、絶体絶命の緊張を秘めている。
究極の夫婦の絆か、或いは、絶望的な闘いか? 愛の極致なのか、復讐の無言劇だったのか……?
謎はなかなかに解けそうもない。この先、夫人を描いたセザンヌの肖像画が、いっそうの注目を浴び、新たな議論を呼ぶことだけは、間違いないかと思われる。