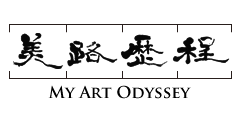

画芸術は枠の中の平面を基本とする。四辺に囲まれた画布が世界の限りとなる。だがすぐれた絵は、時にこの四辺の枠を飛び越える。描かれた情報は枠内に収められるが、絵に込められた思いは、画布を超えて物語をつむぐ。
私は仮に、この画布内に現れた情報を「オン」と、画布外に隠れひろがる世界を「オフ」と呼ぼう。今回とりあげる広重の浮世絵『浅草田圃酉の町詣』(安政4年 1857)は、この「オフ」の妙味の光る名画である。
この絵は、歌川広重(1797〜1858)最晩年の代表作『名所江戸百景』の中の1点になる。『名所江戸百景』は全部で119点の絵からなる(広重本人の絵は118点と言われる)が、ゴッホが模写した『亀戸梅屋舗』や『大はしあたけの夕立』、大鷲が画面上方から下界を望む特異な構図の『深川洲崎十万坪』など、広重の到達点が窺われる傑作が目白押しである。さまざまに凝らされた創意工夫の中に、オフの美学も含まれていた。
猫が窓外を眺めるこの絵は、吉原の妓楼の一室を舞台とする。猫の視界の先には田圃がひろがり、酉の市を訪れた人たちの姿も遠望される。画面左下に置かれた熊手模様の簪はその土産物、男客が女への贈り物として持参したものだ。この簪があるゆえに、男と女が単なる客と遊女の関係を超えた愛し合う間柄、なさぬ仲であることが暗示される。
窓際に茶碗が置かれているのは、一刻も早く女に逢いたい一心で駆けてきた男が喉を潤したものだろうか。手拭いは溢れる汗を拭いたものか……。
それほどに切望した逢瀬である。酉の市の話が終るのも待ちかねてひしと抱き合い、むさぼるように互いを求め、むつみ合うことになる。猫の尻尾の先、立てかけられた屏風の奥では、まさに今、愛の営みの真っ最中、何とも濃密なオフが繰り広げられているのだ。簪の上にちらりと見える懐紙の束が、単に鼻をかむためのものでないことは言うまでもない。
一見すると、オンの画面は静謐そのものである。しかし、オフに抱えるのは、熱き激情の坩堝のような世界である。屏風の奥の激しい肉体の動きや喘ぎ声が、哀しいまでの思慕の情とからんで部屋に満ち、やがて窓を越え、夢のように天地に吸い取られてゆく。
オンとオフのつなぎ役となるのが猫だ。画面の中心でオンを張りつつ、恋しさ、せつなさ、辛さ、ひたむきさなど、オフの想いの使臣として鎮座する。オリジナルの初刷りでは、この白猫は「きめ出し」という技法によって半立体に浮き上がっている。精緻な技法を施したのは、そこが絵の中心核であり、オンとオフの接点だからだ。
江戸の猫絵師と言えば国芳が有名だが、実は広重も猫好きだった。『百猫画譜』という、猫の姿態のスケッチ集もある。このスケッチ集は最近では猫のデザイン画として人気があり、手拭いなど猫グッズの柄になったりもする。ただ、『浅草田圃酉の町詣』の凄さは、猫マニアがもらす「可愛い!」の感想を遥かに超えている。
並の画家なら、男女のむつみ合いを描き、その横に猫を配するであろう。お取込み中の女主人に背を向け窓外を見る猫を描くにしても、男女と一緒の画面に登場させるだろう。だが、広重は敢えて主人公の男女をオフ扱いにした。よほど絵画に対する突っ込んだ卓見がなければ、こういう大胆な構成などとれるはずもない。
猫は、姿は見せぬ女主人の胸の想いを仮託されるかたちで、遥か遠方へ眼差しを向ける。夕空には雁が群れをなして飛んでいる。籠の鳥である女の身からすれば、どうしたって自由への希求と重なる。巣に帰る姿は、男との愛の巣をもちたいと願う女心の飛翔でもある。そう思えば、猫の前の窓格子がどこか牢獄のようにも見えてくる。
酉の市で売られる「熊手」物には、福を掃きこむ、かきこむといった意味があるという。自由と幸福への願いは、オンとオフを統合して絵に満ち溢れる。
『名所江戸百景』は広重の遺作ともなった作品集である。1854年に起きた安政の大地震で甚大な被害を受けた江戸の町の復興を祈る気持ちが、絵筆をとらせたとも言われる。ひとつひとつの景色に愛惜が込められ、40年を超す画業の集大成的な覚悟が随所に見受けられる。
広重が亡くなってちょうど10年後に、明治維新が起きる。『名所江戸百景』がもつ革新性は、そういう時代のうねりと無縁ではなかろう。この『浅草田圃酉の町詣』の絵に込められた自由と幸福への希求も、どこか西洋の人権思想とも遠いこだまを交わしつつ、時代の夜明けを待つ静かな祈りに昇華している。