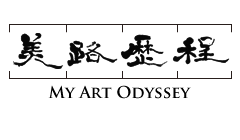

「廃墟の画家」として知られ、あわやギロチンにかけられるところだったユベール・ロベール。その人の面影を伝える最も有名な肖像画は、1788年、革命勃発の1年前に描かれたものである。この時55歳であったロベールは、強い意志を感じさせる精悍さを見せ、何かストレートな力に満ちている。「廃墟」からイメージしがちな感傷的なキャラクターとは遠い印象だが、絵筆はモデルとなった人物の人間性や徳性といったものも真っ直ぐにとらえている。
この肖像画を描いたのは、18世紀のヨーロッパで最も高名だった女流画家のエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン(1755~1842)であった。一般的には、王妃マリー・アントワネットのお抱え宮廷画家としてつとに知られる。えらく長い名前だが、ヴィジェは画家であった父の姓、ルブランは結婚した美術商の夫の姓であった(夫とは後に離婚)。
ヴィジェ=ルブランが初めて王妃に引き合わされ肖像画を手がけたのは1778年。まだ22歳の若さで、ウィーンから嫁いできた王妃とはたまたま同い年だった。この時には、純白のサテンのドレスに身を包んだゴージャスな王妃像を描き、いかにも王室が望む公式の肖像画にふさわしい出来ばえとなったが、互いに通じ合うものがあったのであろう、2人はやがて王妃とお抱え画家という身分の差を超えて、肝胆相照らす仲となる。以後、ヴィジェ=ルブランは悲劇の王妃が断頭台の露と消えるまで、30点あまりのマリー・アントワネットの肖像画を残した。
王妃は、近親結婚を繰り返した結果である、いわゆる「ハプスブルグ顔」の特徴(尖った顎、ぶ厚い唇、垂れた目など)をわずかに受け継いでいたが、ヴィジェ=ルブランは、実際の姿よりもいくぶんソフトに、美しく描いた。もっとも、その気品に溢れた優雅な姿は、お抱え画家にありがちな権力への追従とか擦り寄りというものとは質を異にしていた。
目の前のモデルの人間性、その人の最も善良な部分を引き出し感得して、あたかも腕のよい園芸家が植物を愛で美しく花を咲かせるように、キャンバス上に永遠の輝きとして定着させる――。これはヴィジェ=ルブランの画家としての天性の美質で、さまざまな人物の肖像画を描く際に一貫して維持された姿勢だったが、王妃を描く場合にも、いささかも変わるところはなかったのである。
面白いエピソードが伝わっている。髪を結いあげ、髪粉をふいた公式モードでなく、前髪を分けて額に垂らすような普段着の姿で描かせてくれないかと、ヴィジェ=ルブランは王妃に頼みこんだという。王妃はその願いを許諾はしなかったものの、「大きな額を隠すためにそうしたと、言われたくないですもの」と言って笑い、場を和ませた。
王妃のウィットもさることながら、この逸話にはヴィジェ=ルブランが肖像画家として目指していたものがはっきりと見えてくる。宮廷の頂点に立つ王妃を描きつつ、ひとりの女性、人間としてのマリー・アントワネットに、画家は惹かれていたのだ。
1783年に描かれた『シュミーズ姿のマリー・アントワネット』は、そういうヴィジェ=ルブランの志向に、ある程度沿ったかたちで世に出たものである。モスリンの白いシュミーズ・ドレスは、王妃が王宮を離れ、離宮のプティ・トリアノン滞在中によく着たお気に入りのファッションだった。頭に載せているのも、ここでは麦わら帽子で、プライベートな感じを強くしている。
だが、この絵がサロン展に出品されるや、くつろいだ恰好が公に描かれるべき王妃の姿にふさわしくないと批判され、轟々たる非難を浴びてしまう。個人的な女性としての王妃を描いたことが、批判、非難の渦を招いてしまったのだった。絵はやむなく、会場から撤去せざるを得なかった。
だが、そこは王妃の画家、ヴィジェ=ルブランである。立ち居やポーズはそっくりなまま、青いサテンの豪華衣装に身を包んだ正装姿に変更した作品をたちどころに製作、サロン展に再出品した。今度の作品は、大評判であったという。
この年、ヴィジェ=ルブランは王立アカデミーの会員に認定されている。画商の家族は会員になれないという原則があったが、王妃の強い押しがものをいった。
どうも、シュミーズ姿の軽装の王妃像は、ヴィジェ=ルブランと王妃と、2人の共同の企てだったような気がする。革命によって倒されることになるアンシャン・レジーム(旧体制)の奥の院のような所で、2人の女性によって、型にはまらぬ自由が希求され、何がしかの新しさが指向されていたのだ。
21世紀の今から見れば、このことは貴重である。その試みが、世を席捲した革命勢力からすれば、ピント外れに映るものであったにしても、だ。
1789年7月14日に革命が勃発。王妃マリー・アントワネットは家族ともどもオーストリアへの脱走計画をもくろむもうまく行かず、革命裁判で夫・ルイ16世に続いて死刑宣告を受けた後、1793年10月16日、37年の短い命を断頭台に散らした。
ヴィジェ=ルブランが生前の王妃を最後に描いた絵は、1787年にものした『マリー・アントワネットと子供たち』と名づけられた作品である。それまでと違い、王妃ひとりではなく、子供たちと一緒の構図をとっている。画家の意志よりも前に、王朝側の意向が優先された。
社会全体に体制への不満がくすぶり、国王夫妻への批判が次第に高まりを見せる中、王室としては、母としての王妃、王朝の保護者としての姿を国民の前に示すことで、イメージアップを図ろうとしたのである。権勢の頂点に咲く絢爛たる花のようなイメージは後退し、代わって王の子供らを守り、育て、国の未来を
王妃の表情が憂いを含んで見えるのは、ちょうど絵の製作中に赤ん坊(女児)が亡くなったからだ。右端の王子の後ろの揺り籠が空なのは、そのためである。苦難や哀しみを背負いつつも、王妃と子供たちは懸命に生きようとしている。そのけなげさがこの絵の身上であろう。それゆえか、絵はどこか聖家族を思わせる。ヴィジェ=ルブランの眼差しは澄み、絵筆は格段に深みを増している。
直観で描くだけでなく、歴史に基づく絵画伝統を継いだ寓意も巧みに滑り込ませている。例えば、画面右手、揺り籠の奥に見える大きな宝石キャビネット。これは、古代ローマのコルネリアの逸話を踏まえつつ、どのような宝石よりも子供が宝だとする意味を表している。ローマの貴族たちが奢侈に耽る中、グラックス兄弟の母コルネリアは、宝石を見せてくれと訪ねた客に我が子たちを見せ、自分の宝石はこれだと語ったという。ヴィジェ=ルブランは、古代ローマの賢母に、王妃を重ねようとしたのである。
だが実際には、この絵がサロン展に出品されると、世評は画家の知性を理解せず、巨大な宝石キャビネットに財宝を蓄える王妃の贅沢三昧への非難にすり替えてしまった。無知ゆえの誤解もあったろうが、そのように仕向けようとする勢力の声高なアジテーションが勢いを制したと見るべきだろう。
絵画作品としての芸術性は充実し成功したが、王室の目論見は外れてしまったのである。王妃が投げかける遠くを見据えたような眼差しは、フランスの未来と子供たちの将来を気遣うものだが、自分自身の悲劇の運命をも見通していたのかもしれない。
1789年に革命勢力によって王族が拘束されると、ヴィジェ=ルブランにも危険が迫り、ひとり娘を伴いパリを脱出した。まずはイタリアに逃げ、その後、オーストリア、ロシアと、流転の亡命生活を送った。革命も終わり、1802年、13年ぶりにいったんパリに戻るが、ナポレオン統治下の雰囲気に馴染めず、再び旅に出て、イギリス、スイスなど、流浪を重ねた。彼女がようやく故国フランスに落ち着いたのは、1809年、54歳になってからである。
祖国を離れている間、各地の上流婦人の肖像画を多く描いた。「マリー・アントワネットのお抱え絵師」はフランス宮廷を離れても充分に魅力的であったし、ヴィジェ=ルブランにまかせれば必ず美しい肖像画に仕上がるので、評判は上々だった。無論、そうした仕事をこなさなければ食べてはいけないという、背に腹は代えられない事情もあったが、それらの作品は、「生活のため」とだけ言いきることができない充実ぶりを見せている。
各国の宮廷にも出入りした。ロシアではエカテリーナ女帝の家族たちを描き、プロイセンではルイーズ王妃の肖像画を何点も残している。聡明で知られた(しかもフランスの革命派に対してきわめて辛辣であった!)ルイーズ王女には、親近感を覚えたらしい。王宮で王族を相手に描く時、かつてヴェルサイユ宮殿で王妃を描いていた時代の思い出が走馬灯のように頭をよぎったであろうか……。
肖像画を描く技量だけを頼りに、ヴィジェ=ルブランは女手ひとつでヨーロッパを駆け巡ったのである。革命による境遇が強いたこととはいえ、行動する女性としても、彼女は時代に先駆け、傑出していた。
画家としては、常に誠実だった。相手が王族であれ、貴族であれ、対象となる人物の美点を最大限に引き出し、画布に定着させるという彼女の特徴は、何処にあっても、誰を前にしても、いかんなく発揮されたのだった。
2018年の夏に開催された「ルーブル美術館展 肖像画芸術――人は人をどう表現してきたのか」(国立新美術館)で来日した『エカチェリーナ・ヴァシリエヴナ・スカヴロンスキー伯爵夫人の肖像』(1796)も、旅の途上の作品だが、ヴィジェ=ルブランの実力と美点が充分に窺われる傑作である。
モデルとなったエカチェリーナは、ナポリ駐在ロシア大使の夫人だった女性で、ヴィジェ=ルブランが彼女を描いた時には34歳、既に夫は他界し、未亡人であったという。そのような不幸を微塵も感じさせないほど、画布の女性は向日性とでも言うような輝きに満ちている。ヴィジェ=ルブランも夫と別れ女手ひとつで生きて行く身であったが、伯爵夫人の哀しみの中にも明るさを失わない健気さに、共感を覚えたのだろうか。
実際のエカチェリーナもたいそうな美人であったろうが、描く人=画家の心ばえの美しさを通してでなければ、こうした絵は仕上がらない。画家とモデルと、人間としての美点が響き合って美しい絵を生んでいるのだ。
フランスから逃亡して以降のヴィジェ=ルブランに、なおもマリー・アントワネットを描いた作品が2点ある。
1点は、1790年、旅先のフィレンツェで発注された自画像(実際に描いたのはローマだという)で、絵筆を構える35歳のヴィジェ=ルブランが窺える魅力的な作品だが、描きかけのキャンバスには、マリー・アントワネットと思しき人物の肖像が描きこまれている。
フィレンツェのあるトスカナ大公国は、マリー・アントワネットの兄、ピエトロ・レオポルト1世が統治していた。絵の依頼主が彼なので、その関係もあっただろうが、ヴィジェ=ルブラン自身、パリを離れてなお、おのれの画家としてのイメージは、マリー・アントワネットを描いている姿が何よりも自分らしかったに違いない。
この絵を描いている時点で、王妃はまだ処刑されてはいない。王妃を描いていた日々を懐かしむ思いに加え、奇跡のように無事を祈る気持ちが、自画像の中のキャンバスに凝固したと、そう見ることも可能だろう。
もっとも、彼女は後にこの絵の複製画を製作しているが、その際には、描きかけのキャンバスの中の人物を、マリー・アントワネットから自分の娘のジュリーに変更している。革命政権から「人民の敵」と指弾された王妃の肖像のままでは、フランスへの帰郷が覚束ないとの政治的判断が働いたと言われる。王妃の絵に固執することは、彼女の立場を危うくする可能性があることを、ヴィジェ=ルブランは熟知していたのだ。
しかし現在、1790年の自画像として流布するものは、圧倒的にフィレンツェのウフツィ美術館が所蔵するマリー・アントワネットを描いたオリジナル版のほうで、イギリスはサフォークのナショナル・トラストが管理する複製画の方にスポットが当たることが少ないのは、当然すぎるほど当然な気がする。
さて、もう1点は、それから10年後、アントワネットの長女、マリー・テレーズのために描いた『亡き後の王妃』(1800)という作品である。かつて王宮で描かれた幾多の肖像画の王妃の、栄華を一身にまとう絢爛豪華ななりとは異なり、ここではまるで寝室で描いたかのように、飾らず、最もプライベートなひとりの女性の姿が描かれている。
「あなたの才能のお蔭で、愛しい母と久しぶりに会えました。絵は、決して忘れることのない、心の中の母の姿そのものでした」――マリー・テレーズはヴィジェ=ルブランに、そう礼状をしたためたというが、娘にとって「心の中の母の姿そのもの」だったというこの肖像は、ヴィジェ=ルブラン自身の記憶の中に生きる永遠のマリー・アントワネットでもあったのだろう。
思い出されるのは、ヴェルサイユ宮殿での王妃との親しいやりとりの中で、ヴィジェ=ルブランが、髪を結いあげず、髪粉をふかず、前髪を分けて額に垂らす非公式のスタイルで描きたいと頼みこんでいたことである。偽らざるひとりの女性としてのマリー・アントワネットこそが、ヴィジェ=ルブランが美点を見出し、画家として真に描きたいと望んだ対象だった。
フランス革命直前の、時代の峠のようなところで、運命的な出会いを果たした王妃と画家――。政治の嵐はふたりを離別させ、生死をも分けることとなったが、想いの中の絆は、断たれようもなかったのである。
王妃の没後7年にして、ヴィジェ=ルブランはようやく、理想のマリー・アントワネット像を描くことができたのであった。