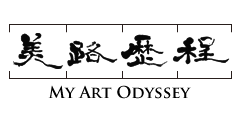

日本に桜の花が咲く頃、ヨーロッパにはイースター(復活祭)が訪れる。
ところで、上記のオラトリオについて、内容を即座に指摘できる日本人は極めて少ないかと思われる。これは音楽に限らず、実はかなりの美術好きでも、ヨーロッパの美術館を訪ねた際、宗教画、とりわけ旧約聖書がテーマとなったものは、タイトルを見ただけではチンプンカンプン、虚ろな思いに陥ることが多い。西洋絵画と接するに、最も彼我の距離を感じて途方に暮れるのがこの手の宗教画なのだ。
ここに紹介する1点の絵も、私にとっては長い間、気になりながらもよくわからない謎の絵であった。絵が飾られているのはロンドンのナショナル・ギャラリー。イギリスに居住した10年の間、何度となく足を運んだが、そのたびにこの絵を見かけ、強い印象をもった。作者はオランダ絵画の巨匠レンブラント。晩年の自画像は渋くも深い印象を残す傑作だが、その近くにあって、この絵は劇的な輝きの中にミステリアスな光を放っていた。
タイトルは「Belshazzar feast(ベルシャザールの饗宴)」とあった。しかし愚かにも、私は長くその絵の意味について、調べることを怠っていた。重い腰を上げるきっかけは、ヘンデルにも「ベルシャザール」なるオラトリオがあることを知ったからであった。美術、音楽の垣根を超えて登場する主題とあれば、どのような話なのか知らねばならないと念じた。
話のもとは、旧約聖書の「ダニエル書」による。時はユダヤ人たちがバビロニアに囚われ連行された、いわゆるバビロン捕囚の頃――。驕れるバビロニアの統治者ベルシャザールは、ユダヤ人から奪った祭器を用い廷臣や後宮の女たちと酒宴を楽しんでいた。その時、突如として人の指が現れ、壁にヘブライ文字を描いた。字の読める者がおらずダニエルという賢者を呼ぶと、驕りのゆえにバビロニア統治は終わるとの神の託宣であると解く。その夜、ベルシャザールは殺された……。
絵の中心に描かれたのはバビロニアの独裁者、ベルシャザールその人だ。ユダヤ人にとっては神聖極まりない聖具に酒を盛り、被支配者を愚弄するように饗宴に興じた。その衣装の豪華絢爛を、レンブラントは質感豊かに描く。権勢の頂点に立ちながら奈落へと転落しようとする瞬間、セレモニアルなヴァニティ(虚栄)の象徴として輝く。
奇蹟として現れた文字に向けられた人々の驚愕の視線の集約度がすごい。絵に漲るベクトルが強力に一点へと押し寄せられる。これぞバロックという劇的緊張感は、作者の力量をいやが上にも物語る。だがそうした技術論以上に、私はレンブラントという類まれなる芸術家の内面的な襞の深さに惹かれる。
聖書に忠実に従えば、不思議な文字が現れた時、その意味するところが人々には解らなかったという。だがベルシャザールをはじめ、この絵の登場人物たちの心を襲ったのは、平たい疑問などではない。驚愕と衝撃には不吉な予感が
意味不明の文字が出現したことで、ベルシャザールの内面に急速に何かが動き始める。音を立てて崩れて行くものがある。後ろめたさ。不安。
レンブラントは、アムステルダムのユダヤ人が多い地区に居住したこともあり、ユダヤ人の知己もいた。ヘブライ文字を登場させたこの絵には、そういう人脈が役立ったとも伝わる。だが、レンブラントは宗教画を宗教画の枠に留めない。人は皆、権力を握れば、謙虚さを忘れ、驕りがちである。しかし人間の本性の中には、そのような驕りとともに、天を怖れぬ振る舞いへの恐怖もあるのだ。そういう人間性への深い洞察は、レンブラントの真骨頂であろう。
旧約聖書に材を借りつつ、レンブラントはあくまで人間の心の問題として扱い、主題を昇華している。もとより、ユダヤ民族に限った話などではない。旧約聖書は日本人には馴染みのない世界だが、すぐれた画家の手になる絵画からは、一宗教を超えた人間の真実が読みとれるのだ。