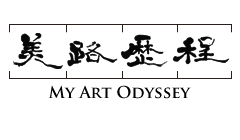
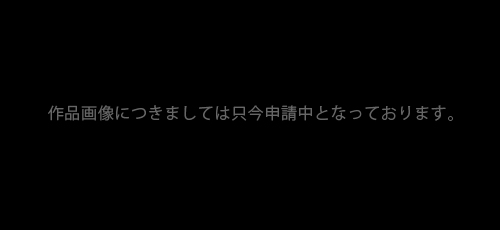
バタビアを発ったオランダ船は、毎年夏に長崎に入り、秋には出港する。その年、1828年の秋も、オランダ船コルネリウス・ハウトマン号は、多くの荷を積み込み、出航の日を待って長崎港の湾内に停泊していた。
ところが、9月17日夜半から九州を襲った猛烈な台風によってコルネリウス・ハウトマン号はいかり綱が切れ港内を流された挙句、座礁した。船体の破損がひどく離礁できず、いったん積み荷をおろすことになった。
荷物を検査した長崎奉行所は仰天する。シーボルトが持ち出そうとした膨大な荷の中に、日本地図や北方資料など禁制の品々が含まれていたのである。鎖国体制を揺るがす大事件が発覚した。世に言うシーボルト事件である。
シーボルトは国外追放、問題の地図を渡したとされた幕府天文方の高橋景保は入牢の上、獄死した。江戸参府に同行し、シーボルトに従って行動していた川原慶賀も連座を免れず、入牢し、「叱り」処分を受けた。
シーボルトは日本を去った。だが慶賀との縁はなおも続く。シーボルトがバタビアから出島に呼び寄せ、助手として働いていたハインリッヒ・ビュルゲルを通して、慶賀の植物画はオランダ船に載せられ、引き続きシーボルトのもとへ届けられたのである。
このことは、慶賀とシーボルトとの関係に新たなベクトルを開くものだったろう。海の彼方のシーボルトが、なおも自分の絵を求めているという事実を、慶賀自身はどう受けとめたであろうか。事件に巻き込まれ入牢する憂き目にあっても、慶賀は、身に危険が及びかねないシーボルトとの縁を断とうとはしなかった。自身の画業が西洋に渡ることの意義を彼なりに自覚していたということであろうし、そうまでして望まれる自分の絵に対する自負もあったことかと思われる。
失意のうちに日本を去ったシーボルトは、オランダで慶賀の絵を手に取り、どのような気持ちに駆られたであろう。慶賀の筆が捉えた日本の植物を目にして、抑えがたく郷愁を覚えたことであろう。
その郷愁の中心には、長崎で結ばれたお滝と彼女との間にできた娘・イネの存在があったことは間違いない。オランダに戻ってすぐに、ふたりに宛てて綴った日本語の手紙が残されているが、愛情に溢れた文面からは、シーボルトがどれほど後ろ髪を引かれる思いで日本を去ったかが窺われ、哀切極まりない。
手紙を受け取ったお滝は、特製の
お滝といえば、青色の大きな花を咲かせるアジサイを愛したシーボルトが、愛妻の名を冠して、「ヒドランゲア・オタクサ」と学名をつけたことはあまりにも有名だ。
シーボルトが帰欧後に精魂傾けて出版した日本植物学研究の金字塔『フローラ・ヤポニカ(日本植物誌)』では、青色の大輪の花を戴くホンアジサイが、絵入りで紹介されており、お滝とのエピソードもあって、『フローラ・ヤポニカ』所載の植物画の中でもとりわけ知られた存在となっている。
ただし、『フローラ・ヤポニカ』に載る植物画は、慶賀の絵をもとにドイツ人がしあげたものである(詳しくは後述)。私はこの有名な絵の元になった慶賀の絵を知りたいと思ったが、今のところ、ライデン大学のコレクションの中に1点、慶賀の描いたアジサイを確認できただけである(長崎歴史文化博物館のサイトより)。
未見の慶賀のアジサイの絵がないとも限らないが、ライデン大学の1点は、花の形がいわゆる鞠状をなしておらず、また葉の形状も微妙に違う。植物図譜らしい科学的な体裁もない。果たしてこれが『フローラ・ヤポニカ』の下絵になったものかどうか、私には自信がない。
『フローラ・ヤポニカ』のアジサイは、気品に満ち、堂々として華麗である。シーボルトが妻にしたお滝という女性を、そして彼女に対するシーボルトの愛情を偲ばせてやまない出来ばえだ。
ヨーロッパに戻ったシーボルトは、海を越えて持ち帰った膨大な資料をもとに、日本に関する著作に取り組む。日本3部作と言われる『
大学時代、医学と同時に植物学の知識も身につけたシーボルトであったが、日本の植物に関する自著を学界でのトップレベルにすべく、もう1人の専門家と組むことにする。ミュンヘン大学教授のツッカリーニ、植物学の中でも特に解剖と分類の研究に秀でた学者あった。
ツッカリーニの助力も得て、シーボルトは膨大な日本の植物資料を整理、1835年に第1冊が出されたのを
『フローラ・ヤポニカ』に掲載された図版は全部で151点。画家として最も多くの図版を手がけたのは植物画家として実績のあったミンジンガーで、製版は主としてジーグリストが担当した。ともに、ミュンヘンのツッカリーニの人脈といってよい。
このチームが、図版の植物図譜作成にあたって、下絵としたのが慶賀の描いた植物画であった。慶賀の絵は水彩画であったし、そこから図版として印刷するには、いったん版画にして摺り上げたものに、1部ずつ色を手で加えてゆくという、大変な手間のかかる作業がとられた。
慶賀の絵から『フローラ・ヤポニカ』に至るまでの具体的な作業の段取りは、個別的で一様ではない。慶賀の原画との距離が近いものもあれば、かけ離れたものもある。シーボルト、ツッカリーニらが、それぞれにどのような判断を下し、作業過程を決定したのか、概括的に論じるのは困難を極める。
だが、西洋の植物図譜の専門家集団の目からすると、慶賀の絵がそのままでは必要条件を満たしているとは思えなかったらしいことは、想像がつく。時には、シーボルトが日本から持ち込んだ植物標本も参考にしながら、花や実などの分解図等、植物図譜として充実したものに仕上げるべく手が加えられた。
また花自体も、慶賀の目が捉えた実像に比べ、より見栄えがよくなるよう、量・
慶賀の絵と『フローラ・ヤポニカ』の図譜を実際にいくつか比較しながら、どのような手が加えられたか、具体的に見てみるとしよう。
アケビは、枝と葉、花の部分だけを見れば、左右逆ではあっても、比較的、慶賀の絵がそのまま使われたものになる。決定的な差は、慶賀の絵になかった実が描き足されていることだ。慶賀は春のアケビを描いたわけで、その際、秋になる実については実視がかなわず、描き入れることがなかった。しかし、ツッカリーニらの専門チームはそれに満足せず、植物図譜としての完璧さを期して、実を、断面図まで含めて大胆に描き加えたのだった。慶賀の原画も花の解剖図は添えており、それは『フローラ・ヤポニカ』でも使われたが、全体のバランスの中ではおとなしい。
レンギョウでは、慶賀の2つの絵が持っていた要素を1つに合成し、画面を構成した。花をつけた枝を玉すだれか何かのように湾曲させて画面に収めた慶賀の観察眼のユニークさは、左右が逆転されたといえ、一応はそのままに受け継がれている。ただ、湾曲した枝の隙間を埋めるように描き加えられた色抜きの枝葉の図は、慶賀の原画からかけ離れたものになっている。多くの解剖部分図も含め、全体として、たわわな印象が強く出されている。
ハマナスの絵は、慶賀の原画からかけ離れて見える。しかし委細に検討すると、改編の過程が透けて見えてくる。慶賀が横から写した本体とは別に添えた、真上から見た花の正面俯瞰図を、ツッカリーニらは本体の横向きの花と入れ替え、本体の主要な花の姿に改めるという離れ業を行なっているのだ。その強引な花の図譜としての移植手術に伴い、慶賀の筆が捉えていた精密なディテールは微妙に歪められることになる。
バラ科の低木樹であるハマナスは、枝の部分にびっしりと細かい棘が生えているのが特徴で、また楕円形の葉も周囲に細かいギザギザが刻まれている。慶賀の絵が押さえていたこれらの特徴は、『フローラ・ヤポニカ』では、枝の棘はともかく、葉のほうとなるとギザギザの部分への意識がおざなりな印象を受ける。
また、花と葉を増やし、ボリューム感を足した意図はそれとして、葉の広がる形状が実際のハマナスとは少し異なるように見える。葉の印象度をあげようとして盛りすぎたとでも言おうか、強引さがどこかに無理を生んでいるのだ。
ハマナスはシーボルトが出島で栽培し、生きたままヨーロッパまで持ち帰ることに成功した植物のひとつである。少なくとも、シーボルトは実物をその目で見ていたはずだが、『フローラ・ヤポニカ』の図譜製作の現場は、充分に実見のかなわぬ者たちの手に委ねられていたということになるであろう。
『フローラ・ヤポニカ』の製作者の側から、図譜の成立までの過程を追うと、植物図譜にふさわしい絵の充実のために、かなりの努力を払っている様子が窺われる。その視点だけで見れば、慶賀の絵は補充しなければ形にならない未成熟なものとなる。ツッカリーニらの植物図譜専門チームの目に、慶賀の絵は稚拙に映ったに違いないのである。
しかし、それは当時の西洋植物学の図譜が抱えた規範から見た評価であって、純粋な意味での植物画、言わば科学を離れたアートの次元から見た場合には、必ずしも慶賀に不利な評価ばかりではないだろう。
私を含め、21世紀の日本人の目からすると、『フローラ・ヤポニカ』に掲載された図譜は、一見ゴージャスで美麗ながら、型にはまった、いかにもな装いに満ちている感じが拭えない。慶賀の実写に想像が加わって生まれた歪みを問題視するよりも先に(それはそれで、あくまで科学の目であろう)、その図譜の見栄えそのもののなかに、慶賀の絵に感じた美としての心地よさからそれたものを感じてしまうのだ。
ボタニカルアート(植物画)は、博物学の一環としての植物学に付随して生まれ発展したという事情はあるだろうが、植物学から独立した美術としての側面も併せ持つ。科学者たちが仕上げた図譜であれば、美しい仕上がりではあっても、どこか、人形の化粧のような、無機的な印象が否めない。アート(美術)ではなく、それはあくまでも美しい科学なのである。
だが、慶賀の絵は違う。彼の植物画に強く感じられる特徴は、その草花に対する慈しみにも似た愛情である。眼前の草や花と息をひとつにしながら、ともに陽の下に憩い、風を感じ、光と戯れる、そうした語り合い、微笑みを交わし合うような姿勢である。
トウガンの絵では、画面中心に実と枝葉、花の全体図を置き、別途、花弁とおしべも配される。かつ、全体を囲うように、実の輪郭がぐるりと墨の線で描かれた。観察にもとづく、実に神経の行き届いた絵であることは、一部は裏側をも見せている大小の葉の様子や、実や蔓を覆う細かな産毛の筆致、実の立体を表す微妙な陰影のつけ方など、さまざまなところで顕著である。
だが、それでいて、慶賀は何とも大胆なのである。大きな実の輪郭線が
また時には、あっと驚くほどアートとしての飛躍を見せる。タラヨウの絵は「日本長崎登與輔」の署名入りのものだが、他には類例のない独自の構図で描かれた。右半分に葉1枚のアップを置き、葉の上に「タラヨー」と記入し、その下方には花や実の細かな解剖図を添える。そして左半分には、わざわざ幅広の短冊のような枠で囲う中に、茎と葉と花の全体図を収めている。
10点を数える詳細な部分解剖図には西洋植物図譜のスタイルが踏襲されているが、全体の大胆な構図、とりわけ左側の枠囲いの部分は、極めて独自な――そしてどこか日本的な伝統にもとづく美意識が働いている。慶賀は、時空を飛び越え、現代の前衛アートすら思わせる、不思議な美のワンダーランドを構築しているのだ。
このような絵を目の当たりにすると、『フローラ・ヤポニカ』を覆う科学的常識を凌駕した慶賀の画家としての天分に、舌を巻く思いがする。美術(アート)の次元において慶賀がいかに抜きんでているか、唸らされるのである。
ちなみに、いかなる事情によるのか、トウガンもタラヨウも、『フローラ・ヤポニカ』では紹介されていない。
慶賀のその後について触れよう。
シーボルトが長崎を去って6年あまりがたった1836年、慶賀は『慶賀写真草』を発表、木版印刷で出版された。ここで言う「写真」とは、「真の姿を写す」との意味で、草の類27種、木の類い29種の計56種に及ぶ植物の図譜を柱に、それぞれに薬学的な情報を添えている。
その凡例の中に曰く、「すべ都て一花の弁を解体して
これは、シーボルトとの交流の中で触れた西洋植物学のスタイルを、慶賀なりに咀嚼、継承し、日本でも形にしたかったからだと思われる。言うなれば、『フローラ・ヤポニカ』の姉妹編とでも言うべき所業になる。
実際、いくつかの花において、『慶賀写真草』は『フローラ・ヤポニカ』と近似する絵を載せている。例えば、先に紹介したレンギョウの玉すだれのように湾曲した枝とそこに咲く花の様子は、『フローラ・ヤポニカ』と共通する。
『フローラ・ヤポニカ』中の代表作であるキリも、花と葉の様子が『慶賀写真草』と相似形を描く。『フローラ・ヤポニカ』において、キリは、ロシア王女の出身にしてオランダ王妃であり、『フローラ・ヤポニカ』の経済的支援者であったアンナ・パーヴロヴナの名前から、「Paulownia imperialis」という学名がつけられたが、日本では太閤秀吉の家紋であったという歴史的事実を踏まえて、高貴な身分にふさわしい花とされたのだった。ヨーロッパの王室をも巻きこむ大切な花に付された図譜が、遥かな日本で出された『慶賀写真草』での絵と酷似するのである。
ただ、『慶賀写真草』は慶賀の生前中に出たものは多色刷りではなく、木版による出版技術の限界もあって、慶賀の植物画の素晴らしさを知っている身からすると、出版の意義はともかく、仕上がりの美しさは、『フローラ・ヤポニカ』と比肩すべくもない。西洋の植物図譜を見ていたに違いない慶賀自身も、おそらく『慶賀写真草』の図版印刷の拙さについては、心穏やかではなかったかと思われる。
その後、1842年には、慶賀は長崎港を描いた絵の中に、警備にあたっていた佐賀藩(鍋島)と熊本藩(細川)の家紋を書き入れたことから、国家機密漏洩に問われ、長崎追放となる(同時に江戸立ち入りも禁じられた)。「出島出入絵師」としては、事実上の「死刑宣告」でもあったろう。
そこからの年譜的な追尾は、資料が不足して難しい。だが、長崎から遠く離れることはなかったか、いかなる事情か、いつしか長崎に戻ったらしい。出島絵師ではなくとも、長崎の町絵師としての晩年の画業があったようなのである。
1853年に条約締結のために長崎を訪れたロシア提督のプチャーチンの肖像画を残している。また1860年には永島キクという老婦人の肖像画(「永島キク刀自絵像」)を描き、自身の落款を添えている。落款は「七十五歳 種美寫」というものだが、慶賀の生年が1786年であると推定される根拠となっている。
植物画に類する仕事がなかったわけではない。
1841年前後のことと推定されるが、狩野派の絵師ら総勢22名の画家たちが、全25図の絵を寄り合わせて画帖を作成した。『狩野家及南画寄合画帖』――。この中に、慶賀の絵が1点見出される。青竹に紅白の薔薇をからませ、竹の枝には小禽をとまらせた。全体として中国画の南蘋派の影響を窺わせる作風だが、花弁のひとつひとつの色と形を写した薔薇の花の丁寧な描写や、薔薇の枝に細かく付された赤い棘、また楕円形の葉の描き方などに、往年の慶賀の植物画の面影が見てとれる。
また、長崎半島の南端、野母崎にある脇岬観音寺に伝わる150点の花を描いた天井絵の中の5点に、慶賀の落款がある。天井絵の1枚は42センチ四方の正方形で、これが150枚、格子状にびっしりと本堂の天井を埋める。慶賀の師にあたる石崎融思とその一門によって描かれたとの記録があり、完成は1846年であるとされる。
慶賀は60歳ほど、長崎追放から4年後になる。花卉図を揃える晴れの場に、自分も名をつらね、絵を残すことが、絵師としての自負であったかもしれないし、「出島出入絵師」の地位を剥奪されてなお、植物画に関しては自分の出番だと、気を吐いたということかもしれない。
天井絵は公開されていないので普通には観覧が難しいが、慶賀の作のうちムサシアブミ、ノウゼンカズラについては、長崎歴史文化博物館のサイトで見ることができる。天井絵なので木にじかに描いており、勝手が違ったところはあったかもしれないが、慶賀にとって久しぶりの植物画であったことは想像に難くない。
ムサシアブミに関しては、ロシア科学アカデミー図書館所蔵の慶賀コレクションの中にも植物画があり、日本巡回展でも展示されていた。西洋の植物図譜のスタイルに倣う意識が特に強い仕上がりなので、脇岬観音寺の天井絵とは構図を異にするが、部分部分を比較すればやはり似ている。
また『慶賀写真草』の中でも、慶賀はムサシアブミを紹介し、図版を載せている。脇岬観音寺の天井絵のムサシアブミは、とりわけこの『慶賀写真草』のものと酷似している。
その名の由来にもなった、くるりと巻き込んだ「
1859年、シーボルトは30年ぶりに日本を再訪する。日本は開国し、オランダ貿易会社の長崎支店評議員の肩書を得て、シーボルトは12歳になる長男のアレクサンダーを伴い、長崎港に上陸した。
63歳になっていたシーボルトは、初来日の折に塾を開いた懐かしい鳴滝の家に居を定め、旧門人たちと再会を果たす。やがて幕府の要請によって江戸に赴き、顧問として活動する。
激動する国際情勢下、日本のために尽くそうとしたシーボルトであったが、その努力がかえって諸外国から敬遠され、オランダ総領事の申し入れにより、幕府から解任されてしまう。いったんは長崎に戻るが、オランダ政府はシーボルトの活動が国益に沿わないと判断、帰国命令を出す。再来日での日本滞在は2年半ほど、老シーボルトは失意のうちに日本を去った。
その間、慶賀は何をしていたのだろう。一般に慶賀の没年は1862年とされるが、これはちょうど、老シーボルトが日本を去った年にあたる。シーボルトが再来日を果たし、長崎や江戸に滞在していた間、慶賀は70代半ばながら、まだ存命中だったことになる。だが、慶賀がシーボルトと再会したという記録は見当たらない。
先に述べた、「永島キク刀自絵像」の肖像画を慶賀が手がけたのは1860年だが、その前の年に、シーボルトは再来日を果たしているのだ。絵を描くだけの気力体力が備わっていたにもかかわらず、慶賀はシーボルトのもとを訪ねていないようなのである。
いくつかの疑問がわく。慶賀は『フローラ・ヤポニカ』を目にする機会はなかったのだろうか――。全巻は無理でも、分冊が1部でもオランダ商館に持ち込まれることがあれば、その下絵作者として、慶賀にも閲覧がかなうようなことはあり得ないのか。
或いは、図譜の写しのようなもの――ツッカリーニのもとで版画にしたものを、人づてに渡されるようなことはなかったのか。
もし、何らかの形で、慶賀が『フローラ・ヤポニカ』を目にする機会があったなら、どのように感じたろう。『慶賀写真草』とは比較にならない、その美しい仕上がりに驚嘆したであろうか。自分の描いた絵が、そのように立派に使われたことを、誇らしく感じたろうか……。
それとも、自作の絵に手が加えられ、描き足されたことを知って、冒涜のように感じ、心を傷めることになったであろうか。また、「化粧」が過ぎて日本の植物の自然な姿から逸脱してしまった図譜を目の当たりにして、落胆や怒りを覚えることにはならなかったであろうか……。
それはもはや、小説のような形でしか、追うことのできないテーマかと思われる。
慶賀の推定没年は1862年。シーボルトは帰欧後、オランダでも公職から離れざるを得ず、故国ドイツに戻ったが、1866年、ミュンヘンで70年の生涯を閉じた。江戸幕府が瓦解し、明治という新しい日本が誕生する2年前のことである。
シーボルトは、慶賀の植物画を『フローラ・ヤポニカ』の下絵に使った。ツッカリーニとともに、西洋植物図譜として超一流のもの仕上げるべく、強引に手を加えた。だが、面白いことに、シーボルトは『フローラ・ヤポニカ』発刊後も、慶賀のオリジナルの絵を保管していたのである。下絵として用済みになった後にも、慶賀の絵を捨てなどはしなかったのだ。
ここに、シーボルトの慶賀に対する複雑な思いを見ることができる気がする。ツッカリーニのような西洋植物図譜の専門家の目からすると、未熟とも異端ともされた慶賀の絵に対し、シーボルトは愛着をもっていたのではなかったろうか。
慶賀の絵さえ保持していれば、他の追随を許さぬ日本植物研究の大家として、
シーボルトの死後、彼が保管していた慶賀の植物画コレクションは、帝国ロシア科学アカデミーに売却された。歴史の激動を経て、今はロシア科学アカデミー図書館が所蔵する。
そして今、その慶賀の植物画が注目を浴びている。ベールに包まれた知られざる国の植物資料としてではなく、ボタニカル・アートとしての価値が見直されつつあるのだ。『フローラ・ヤポニカ』の豪華壮麗な図譜に比べて見劣りのする下絵として扱うのではなしに、アートの次元における独自の生命力が光を浴びるのである。
『フローラ・ヤポニカ』を超え、歳月を越えて、慶賀の絵は蘇る。この不死鳥のような復活を、草葉の陰の慶賀本人、そしてシーボルトは、どのように見、考えるであろうか……。
(了)