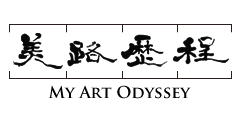

海外、とりわけヨーロッパに暮らす日本人にとって、フジタは(藤田嗣治)特別な存在である。私自身、10年に及んだイギリス暮しの折々にパリを訪ねたが、花の都の華やぎにときめく胸に、フジタはぐっと身近に、そして誇らしく感じられた。
モンパルナスにある老舗のブラッスリー、ロトンド、クーポールには、1920年代から30年代、世界の芸術家たちの溜り場だった熱気が今も煮凝りのように沁みついている。モディリアーニ、ピカソ、シャガール……幾多の天才画家に伍して、フジタもその渦中にいた。おかっぱ頭に丸眼鏡、ちょび髭の独特の出で立ちは、過剰な自己演出の賜物ではあろうが、いかにもパリの寵児の恰好だ。異端者を吹聴して息巻く様子は、「フーフー(foufou=お調子者)」の渾名を頂戴することになった。
さて、フジタを寵児に仕立て上げたのが、画面に溢れた独自の「素晴らしき乳白色」であった。東京美術学校を卒業後、1913年に26歳で渡仏、雌伏の8年を経て、フジタはそれまで誰も筆にしたことのない輝ける乳白色で女性のヌードを描き、パリ画壇のスターの座に躍り出た。面相筆で引いた黒の輪郭線の内側に、ほの白く輝きながら浮かびあがる女性の肌――。浮世絵以来の日本の伝統を意識しつつ、コスモポリタニズムの凱歌のように咲かせた大輪の花であった。
爆発の年となった1921年以来、初期のフジタの女性像は、一世風靡した売れっ子モデルのキキを使うことが多かった。ここに紹介した絵もまた、寝台に裸身を横たえるのはキキであるが、明らかにゴヤの「裸のマヤ」を意識したポーズをつけつつ、フジタはもうひとつ、印象的な点景を置いている。猫である。
この絵は、殆どモノトーンに近い色合いで描かれている。乳白色の魅力を最大限に引き出すためであろうが、白に対する黒としては、カーテンのような背景を除けば、女のちょっとアフロっぽい髪やわずかな陰毛、こちらを見据えた両の瞳、そして女の足元に添う猫だけなのだ(しかも白と黒のブチ!)。ここではそういう色彩の対比で猫が選ばれた可能性があるが、実はフジタはこの後、晩年に至るまで、女性像に、自画像に、少女像にと、しばしば猫を添えることになる。猫だけを描いた作品もある。何を隠そう、フジタは日本を、そして世界を代表する「猫画家」でもあるのだ。
「私は猫を友達としている。(中略)贅沢な猫でなければいけないと言うのでもなく、捨て猫でも泥棒猫でも、拾い上げて飼うのである。もっともフランスでは滅多に捨て猫はいないが、それでも年に1回や2回は迷って来るので、そんなのを飼ってやるのである」――。フジタは捨て猫を拾って自宅に連れ込んだ。次第に数が増え、何匹もの猫がフジタのアパルトマンで同居していたという。
瞼に浮かぶ気がする。宴のような芸術家たちの集まりで、社交界の花形さながら派手な立ち回りを演じた後、ひっそりとした深夜の街をアパルトマンへと向かうひとりの異邦人(エトランジェ)。街灯の灯りが滲む石畳の裏通り。蹌踉(そうろう)とした足元の先に、うずくまる一匹の猫がいる。主のいない宿なしの野良猫だ。孤影に吸い寄せられるように、男は猫を拾い上げる。そのぬくもりを感じながら、じっと顔を覗き込む……。寵児の心の内に沈む孤独が捨て猫と響き合う、震えるような瞬間である。
響き合いは、フジタの猫の大事な要素だ。女性のヌードの場合も、添うものとしての猫の存在は雄弁である。眠る裸身の女の傍らでうずくまる猫は、女と同じ夢に逍遥するかに見える。自画像の肩口からやんちゃな顔を覗かせた猫は、すまし顔の芸術家への強烈なカウンターパンチだ。フジタの猫は心の鏡となり、共鳴板とも反響板ともなり、思いを託す化身ともなった。
戦時中、日本でフジタは戦争画に手を染め、戦後はそのことで責めたてられ、1949年にはパリに戻る。「私が日本を捨てたのではない。日本に捨てられたのだ」――、捨て猫同然の思いでフジタは故国をあとにした。異(い)なる者としての孤独の宿命を背負いながら……。
晩年、フジタは多くの少女像を描いた。パリで見かけた少女というより、画家自身の心の中に住む少女たちであったろう。少女たちは、しばしば猫を抱いている。いたいけな少女に抱かれた猫は、おそらく、フジタ自身の化身なのであろう。無垢な童心は、老境のフジタの懐かしい心の巣であったに違いない。