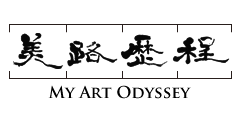

堂々たる木だ。樹齢数十年にはなるだろう。大地から聳え立つ太い幹は途中いくつもに分かれ、それぞれにまた幹をなし、そこからいくつもの枝を伸ばして豊かに葉を茂らせる。一本の木でありながら、まるで森のようだ。
日本人なら誰しもが、テレビCMに流れる「この木なんの木」の歌を思うに違いない。コマーシャルに登場した木はハワイ・オアフ島のモアナルア・ガーデンパークのものだが、この絵の木が聳えていたのは、フランス東部、ブザンソン近郊のフラジェ村であった。描かれたのは1864年、画家クールベの作。故郷オルナンの町からほど近いこの村に、クールベの父が農場を所有しており、画家も幼い頃、そこですごしたのだった。
クールベは写実主義の画家として知られる。時代の対抗軸としては、ロマン主義がある。1855年にレアリスム宣言をしたクールベは、「自分の生きる時代の風俗や思想や事件を見たままに表現すること、つまりは生きた芸術(アール・ヴィヴァン)をつくることこそが、私の目的である」と述べた。
この木の描き方も、それを地で行くスタイルだが、太い幹のところどころが白く変色しているさまや、巨木の左右に2匹の犬が走っているところなど、いかにもレアリスム(リアリズム)の画家らしい。
キャンバスに留まりきらない巨木からは、名峰を仰ぎ見るような圧倒的な印象を受ける。幹に枝ぶり、葉の繁り具合など、どこを見ても生命力に溢れている。大地に根を張り、じっと風雪に耐え、成長を続けるその姿からは、聖人のようなスピリチュアルなものさえ感じさせられる。
日本では各地に巨木信仰が見られるが、ヨーロッパでも、地中海沿岸域では古くから樫の木に対する崇拝が盛んで、古代ケルト人たちの間でも、樫の木は神聖視された。ドルイドと呼ばれたケルトの祭司たちは、樫の木を宗教儀式に使ったという。成長を続ける姿や、冬には葉を落とすものの春の訪れとともに見事に葉を茂らす再生のさまなどが、生命力の象徴と考えられたのだろう。
樫の巨木に注がれたクールベの眼差しにも、こうした生命力の淵源を覗くかのような畏敬の念、敬虔な心映えが反映している。レアリスム宣言で述べた「生きた芸術(アール・ヴィヴァン)」とは、ありふれた、そんじょそこらの事象の「見たまま」ではなしに、生の本質、世界の根源に迫り得るような真実をつかむことを意味したのではなかったろうか。
クールベにはまた、一連の海を描いた絵画があるのだが、この静的な樫の木とは一見反対に見えるような荒れ狂う波濤の絵(「波」「嵐の海」など)も、静と動の差を超えて、アール・ヴィヴァンの瞬間をとらえたものだったのだろう。さらにいえば、クールベ作品中随一の「問題作」として知られる、「世界の起源」と題された絵――性器を露出した女性の下半身をリアルに描いた作品――も、力の淵源へのこだわりが生んだ「アール・ヴィヴァン」であるように感じる。
不思議なことに、西洋絵画では、バルビゾン派のコローやルソーなど、田園風景として自然や森を描くことはあっても、1本の木に眼差しを集中して描いた絵はあまり見られない。クールベは、この点でも先駆者であった。もっとも、クールベに、この絵のほかに1本の木を描いた絵があるとは聞かない。1本の木を描いた貴重な1枚の絵なのである。
なお、この絵はアメリカでの所蔵を経て、長らく東京の村内美術館のコレクションに収められていた。だが2013年になって、フランスのクールベ美術館に買い上げられ、今では画家の故郷オルナンに戻っている。日本から去ってしまったのはいささか淋しい気がするが、植物の種子が風に乗って飛散してゆくように、この絵も、世界に流浪を重ねた挙句、故郷の大地に再び根をおろしたのだ。
木ということで思い出すのは、ジョイス・キルマーというアメリカの詩人が詠んだ「木(Trees)」という詩である。キルマーはアメリカには珍しくカトリック教徒で、第1次世界大戦に出征し、フランスにて31歳の若さで戦死した。
私は思う、木のように美しい詩を見ることはあるまいと。
飢えた口を、甘く豊かに溢れる大地の乳房に押しつける木。
ひねもす神を仰ぎ、葉の繁る腕をあげ祈る木。
夏には髪にコマドリの巣を宿すこともある木。
その胸の上には雪がつもり、親しげに雨とも暮す。
詩は私のような愚者が詠む。
だが木は神だけがつくるもの。
タイトルでは「Trees」と複数形が使われているが、詩の本編ではすべてが単数形で、詩人の眼差しはあくまでも1本の木に注がれている。
ここでは木の種類は特定されていない。しかし、クールベの描いた「樫の木」は、いかにもキルマーの詩にふさわしい。
大地から幹を伸ばし、葉を茂らせる木への崇敬。木が宿す聖なる生命力の讃仰――。時を超え、画家と詩人の胸にこだました思いの響き合いに、私もまた心を添わせたい。