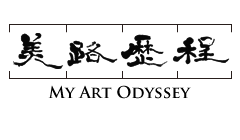

ヘンリー8世の宮廷画家となったホルバインが、偉丈夫の体躯堂々とした王の全身像を描いたのは、王が3番目の妻となるジェーン・シーモアと結婚した1536年か、翌年であろうと言われている。そしてこの1537年、ジェーン王妃が待望の男子を出産した(後のエドワード6世)。
ローマ教皇庁にたてついてまで結婚した2番目の妻、アン・ブリンを王妃の座から引きずりおろし斬首刑にしてしまったのも、男子が生まれない焦りが大きな原因であったことを思えば、46歳にしてようやく後継者たる王子に恵まれた王の喜びはひとしおであったに違いない。
ホルバインにはジェーン王妃を描いた肖像画もあるが、フランス仕込みのマナーを身につけ、よろず華やかで、政治にもくちばしを突っ込んで政敵を作ることにもなったアン・ブリンとは対照的に、控えめな性格として知られた女性らしく、地味目な姿をキャンバスに収めている。
王子誕生で宮廷は慶事に涌いたが、好事魔多しというか、ジェーン王妃は産褥がもとで出産から12日後には死去してしまう。王子は得たものの、王はたちまちやもめとなってしまった。
そのような事情を経て、1538年、宮廷画家ホルバインに特命が下った。デンマーク王室に、クリスティーナという王女がいた。御年16歳、ミラノ公妃の肩書をもつ。11歳の時に形ばかりの結婚をし、2年後には未亡人となって今に至っていた。このクリスティーナ王女の肖像を描いて来いと、今流にいうなら、お見合い写真を発注するような感じで、ホルバインが派遣されたのである。
王女をスケッチした日時が記録に残されている。1538年3月12日、当時ブリュッセルにいた王女は3時間だけホルバインの前に立った。もちろん、この時はスケッチだけである。急ぎロンドンに引き返したホルバインは、このスケッチを王に見せたところ、王は大いに気に入り、ホルバインは等身大の肖像画を完成させた。こうして、イギリスの宮廷画家の手により、デンマーク王女の美しい姿が絵として残された。
全身黒装束なのは、ミラノ公の未亡人という公式の立場から喪服を着ているためだ。黒づくめの衣装が王女の白い顔を引き立たせ、清楚な美しさを際立たせている。しかも人文主義に親和し人間を見つめる眼差しを深めたホルバインは、彼女の控えめな美しさのなかにも、芯の通った賢さを見逃していない。
案の定、肖像画に満足したヘンリー8世によって、縁談が具体化されると、クリスティーナ王女はきっぱりと言いきった。「私に首がふたつあったなら、喜んでひとつをさしあげましょうに……」――。
短期間のうちに次々と妻を変える男としての王の問題性と、下手をすれば処刑台に立たねばならなくなるかもしれないその危うさを、彼女はよく理解していたのだ。「首(head)」をもちだしたあたり、アン・ブリンの処刑に対する揶揄がわさびをきかせている。
そういう歴史物語の語り部として、ホルバインのこの絵を鑑賞することも、なかなかに楽しい。だが、純粋に絵画として見ても、この絵は実に魅力的だ。等身大の全身立像という点もユニークだし、喪服の黒に背景の深い青と、全体の色使いを抑えた分、王女の顔と手の白さが輝くようである。
おそらくはホルバイン自身、この16歳の王女に、すっかり魅せられてしまったのだろう。貴人の肖像画として型通りでない分、新しさを感じてならない作品なのである。背景の壁の青の沈んだ深さなど、どこかピカソの青の時代さえ思わせるではないか!
デンマーク王女との縁談が破談となった翌1539年、ホルバインに新たな王命が下った。今度はデュッセルドルフに向かえという。神聖ローマ帝国の一翼をなすベルク公国のヨハン王の娘、アンナ・フォン・クレーフェ(英語名アン・オブ・クレーヴス)に会って肖像画を準備せよとの命令である。もちろん、結婚相手の候補として、その姿かたちを写したものが必要だったのだ。
面白いことに、アン・ブリン、ジェーン・シーモアと、2番目3番目の妻はいずれも王妃づきの侍女に懸想した結果、強引に王妃の座にあげたわけだが、今回は、外交によって海外の宮廷から王妃となる女性を選ぼうとした。王の嗜好よりも、国としての事情が優先されたのである。
ローマ教皇庁と対立したイングランドは、欧州内に同盟国をつくる必要があった。ヘンリー8世を支え、宮廷政治を率いてきた政治家、トマス・クロムウェルの差し金であったことは間違いない。
ホルバインは再びドーヴァー海峡を越え、ベルク公国に赴き、アンナ王女の肖像画を描いた。今度は、全身立像ではなく、腰から上の上半身で、正面からその容貌がよくわかるよう工夫されていた。華麗な衣装や装飾のなかに、落ち着きのある、しとやかな女性が描かれた。
実を言うと、このとき、ホルバインはアンナの妹のアマリアをも描いている。姉妹のどちらかが王の気に入ってもらえればという、念の入れようだった(アマリアを描いたホルバインのスケッチは現存する)。姉妹の絵を見た王は、姉のアンナの方を気に入り、結婚が決まった。
王は新妻の到着を待ちわび、海峡を越えてイギリスに到着したばかりのアンナの部屋に、召使を装って忍び込むほどであった。ところが、いざ実物の彼女に接するや、王は立腹した。ホルバインの描いた肖像画の中の美女とは似ても似つかぬと、機嫌をそこねてしまったのである。
結局、この結婚は半年しか続かなかった。それでも、アンナは処刑台に送られることなく、「王の妹」という称号や所領地、年金ももらった上でイングランドに留まることになった。王の不興を買って明日の運命をおびえることもあったろうが、外交上の配慮もあってか、本人としてもひとまずは安心して王妃の座を降りることができたのである。
その代り、処刑台に向かわねばならぬ人物が生まれた。王の片腕と言われた寵臣、トマス・クロムウェルである。飛ぶ鳥を落とす勢いで権力の中枢に駆けあがった男は、弱点が生じるや、政敵たちから目の敵にされ、讒言(ざんげん)の嵐が王に寄せられた。
王はノーフォーク公の姪で新王妃の侍女となったキャサリン・ハワードに惹かれ、やがて5番目の妻とする。要は、容貌に秀でた侍女にお手付きをするのが、根っから好きでたまらないのだ。
その結婚の日、ロンドン塔ではクロムウェルの処刑が執り行われた。1540年7月28日のことである。このあたりの光と影のコントラストの強烈さ、目のくらみそうな野蛮、狂暴ぶりは、いかにもテューダー朝らしい。
アンナ・フォン・クレーフェを描いた絵がそもそもの発端となっているので、画家も無事でいられるはずがなく、ホルバインは宮廷画家の地位を追われることになった。もっとも、処刑されたわけではないので、実物に比べて美しすぎるとされた絵が、王を騙そうとするようなよこしまな意志から生まれたものとは判断されなかったのだろう。余人をもって替えがたい偉大なる肖像画家としての才能は、誰もが認めるところだったのである。
ホルバインには、トマス・クロムウェルを描いた肖像画もある。恰幅のよい体の上には、いかにも才気あふれた、そして権謀術数にもたけていそうな政治家の顔がのる。1532年から33年頃の作と言われるので、1536年に宮廷画家に任命されるよりも前のことになる。
10年もしないうちにお互いを襲うことになる運命を、テューダー朝きっての政治家も画家も、その時には知る由もなかった。
スイスのバーゼルを襲った新教の波に押し出されるように、1526年、ホルバインがトマス・モアを頼ってイギリスに渡ったことは既に記した。その時が第1次のイギリス滞在で、1532年以降、2度目の滞在に入る。
宮廷画家に任命されるのは1536年のことだが、この間、ホルバインが英王室と無縁であったわけではない。彼のパトロンは、ほかでもない、ヘンリー8世の寵愛を受け、先の王妃を押しのけて新王妃の座にのぼった、かのアン・ブリンだったのだ。
1533年5月31日と6月1日に行われた、アン・ブリンの戴冠パレードで、沿道のデザインをまかされたのはホルバインだった。12歳の頃から3年ほど、フランスで宮廷生活を送ったアンは、ヨーロッパを代表する画家として、ホルバインの実力を熟知していたのである。
アンはホルバインに、ジュエリーのデザインも依頼した。彼女から王へと贈られるニューイヤーのプレゼントも、ホルバインにデザインをまかせた。新王妃がホルバインに寄せる信頼は絶大であった。
かの有名な「大使たち」(1533年)という作品さえ、アン・ブリンのコミッションによって描かれたという説まであるほどなのだ。絵の中の小道具からは、アンが新女王であることが宮廷に報ぜられた4月11日の日づけが見てとれるという。
であれば、当然ながら、ひとつの疑問が頭をもたげてくる。ホルバインが描いた、アン・ブリンの肖像画はないのだろうか。この、ある意味ではテューダー朝随一のヒロインは、並びなき信頼を寄せる大画家の前で、ポーズをとることはなかったのだろうか――。
イングランドの宮廷画家として、王をはじめ王族や宮廷人の肖像画を描いたホルバインだったが、アン・ブリンのものは現存しない。だが、常識的に考えて、ホルバインがパトロンである王妃アン・ブリンの肖像画を手がけていないはずはない。これはまず間違いなく、独裁者の怒りにふれ、アンが処刑されてしまった後、王命ないしは王の意向を気にする廷臣たちによって、その肖像画が廃棄されてしまったのだろう。刑場の露と消えたのは王妃の肉体ばかりでなく、王妃を描いたホルバインの肖像画も同じ運命をたどったのである。
とはいえ、それはあくまで正史の語る歴史である。ホルバイン描くアン・ブリンの肖像画は、どこかに、誰かの手によって、たとえそのコピーであったとしても、隠されていたことはないのだろうか。
アン・ブリンが死刑にされた表だっての理由は、不貞を働いたというものである。だが、そのような説を信じる者など、誰もいない。2度目の子(男子だったという)を流産した後、王の愛は急速に冷め、アンとの結婚を後悔し始める。天の祟りゆえに、男子が授からないと思い込んでしまったのである。
そこに付け込んだのが、アンやその親族、一派と対立した輩たちである。あることないことを王の耳に吹き込んで、アンを刑場に送ることに成功する。アンは、明らかに王の気まぐれと、残忍な宮廷政治の犠牲となったのだった。
だが、アンを支持したグループの中にも、処刑を免れ、生き残った人たちがいた。かつ、アンには1533年9月に生んだ女児がいた(後のエリザベス1世)。強引に母を奪われてしまったこのエリザベスのために、アンの肖像画を何としても守りぬかねばと念じた人たちは、必ずやいたはずなのである。
ロンドンのロイヤル・コレクションのなかに、ホルバインがアン・ブリンを描いたとされる1枚のスケッチがある。これが本当にアン・ブリンの肖像なのか、過去にもやかましい論争が続けられてきた。王妃としての公式の衣装でない、プライベートの服装に見えるが、画家との親密さの表れと見るべきか。このスケッチをもとに描かれた肖像画のほうは廃棄されてしまったが、何とか、もと絵だけは守られたということだろうか。
同じくロンドンのナショナル・ポートレイト・ギャラリーには、ホルバインの絵をもとにしたというアン・ブリンの肖像がある。数点あるが、多くは17世紀になって製作されたものだ。
これらは大きく分けると2系統のリソースに分けられる。ひとつは、ロイヤル・コレクションに残るスケッチ画をもとにしたものだ。そしてもうひとつ、ホルバインの絵をもとにしたと伝えられ、王妃の服装をまとったものがある。明らかに典拠となったホルバインの1点の絵があることを示唆するものの、今に至るまでオリジナルの絵は不明である。
1649年にウェンセスラス・ホラーによって作られたエッチングは、ホルバインがとらえたアン・ブリンの面影を、かなり忠実に伝えてくれているように思う。
その死後に描かれたアン・ブリンの肖像と称されるものは、一般に「罪人」としてかなりバイアスのかかった筆致で描かれている。王を狂わせた女狐、妖艶な悪女といったイメージである。
だが、生前にホルバインが描いた肖像画をもとにしたこのエッチングでは、何よりも、高貴な気品が目立つ。静かな面差しの奥に、凛としたものを秘めている。
処刑の日、アンは化粧をして刑場に赴くが、首を刎ねるフランスからの特注の剣が到着していないとの理由で、延期を言い渡される。ロンドン塔内の牢に戻り、この世での奇妙なおまけのような一夜を過ごす。翌日、再び彼女は死出の旅路のために装い、公衆の視線の中を刑場まで歩き、白いうなじを、剣を手にした処刑人の前に差し出した。
2日にわたってこのような場に立たされた彼女の精神的なストレスは相当なものだったに違いないが、最後まで取り乱すことはなく、堂々とした最期であったと伝えられる。
エッチングからは、そのような凛とした気概や気品が漂ってくる。ホルバインがとらえたアン・ブリンという女性の偽らざる姿だったはずである。
アンナ・フォン・クレーフェ(アン・オブ・クレーブス)を描いた絵がきっかけとなって、ホルバインは宮廷を追われた。それでも、彼はロンドンに留まった。祖国ドイツにも、かつて暮らしたスイスにも戻らなかった。
独裁者・ヘンリー8世のもとでの宮廷画家という仕事は、まさに命がけで、緊張を強いられるものだったに違いないが、任が解かれてこれ幸いとロンドンから脱出しなかったところを見ると、その地で得られるものの大きさを、彼自身、わきまえていたということなのだろう。
この時代、ロンドンはまだ、7つの海を支配した後の大英帝国のような繁栄の中にあったわけではなかった。むしろ、ヨーロッパの辺境として、無粋にして粗暴、ブルータルな部分を多分に残していた。
それでも、そこには他の国、よその宮廷には見られない、独特な濃密さが生きていた。権力への野望、愛をめぐる葛藤など、どろどろとした人間の欲望が渦巻く、原色の坩堝(るつぼ)だったのだ。善も悪も、栄光も没落も、愛と死も、すべてが劇場の如くに、一流の「主役たち」たちによって演じられていたのである。
そのロンドンに、ホルバインは魅せられた。イングランド宮廷という、毒を含んだ絢爛の舞台に惹かれた。そこで、濃縮酸素を吹き込まれたかのように、画家は生き生きと活躍し、「主役たち」を描くことにおのれの生きる場を見出したのである。
アンナ・フォン・クレーフェの肖像画を描いてから3年後、ホルバインは疫病に倒れ、還らぬ人になる。その時に制作中だった最後の作品は、奇しくも、ヘンリー8世の登場する絵であった。「ヘンリー8世と床屋外科医たち」(1543年)――。1540年、床屋ギルドが床屋外科医組合として認められ(刃物を扱う床屋が古くは外科手術にも関わっていたことの名残)、新組合からコミッションを受けて描くことになった絵だが、組合代表者たちに囲まれて王が鎮座する。
ベルク公国から輿入れさせたアンナ王妃を押しのけてまで王妃にしたキャサリン・ハワードは、不貞のかどにより、2年後の1542年には刑場の露と消えた。アン・ブリンの時とは違い、今回は王の目を盗んだ不倫行為が実際にあったと信じられている。もはや王には、男として若妻を引き留める魅力も体力もなくなっていた。
この絵の中でも、でっぷりと太り、老境にさしかかった王に、かつての逞しさや輝き、威風堂々たる偉丈夫ぶりはない。それでもホルバインにとって、王はなお絵の中心になくてはならない存在だったのである。この絵のために、王が絵筆をとるホルバインの前に立つことはなかったといわれる。王は実際のヘンリー8世というより、もはやホルバインのイメージの中の王だったのだろう。
それにしても、このホルバインの遺作となった集団肖像画には、時代を先取りした何とも新しいセンスを感じてならない。例えば、レンブラントの「夜警」、或いは「テュルプ博士の解剖学講義」――。17世紀、オランダの黄金の世紀を闊歩した市民群像を生き生きと描いたそれらの集団肖像画と、ホルバインのこの遺作は、ほぼ一直線につながっている。
北方ルネサンスの専門家、オットー・ベネシュが曰く、「彼(ホルバイン)の絵は人間だけが住む宇宙である」――。しかり。エラスムス譲りの人文主義にはぐくまれたその人間主義が、ホルバインの真骨頂なのである。
テューダー朝宮廷という特殊な舞台で、ホルバインの目と筆は磨かれた。酸いも甘いもではないが、あまりにも濃密な密度で、人間の叡智も、傲慢も、愛も、愚かさも、虚しさも、すべてを彼は見たのである。
作曲家・ヴォーン・ウィリアムスの作品に、「グリーンスリーブスによる幻想曲」という曲がある。テューダー朝を思う時、ヘンリー8世がアン・ブリンのために作曲したと伝えられるこの物悲しいメロディーははずせない。
ホルバインの手になるテューダー朝の「主役たち」の肖像画の数々を、彼、彼女らの有為転変に思いを馳せながら、グリーンスリーブスのテーマが変容する曲をBGMとしつつ、芳醇のウィスキーでも堪能するような気持ちで、愉しみ、味わうことは、人の世の真実に誘われるとてもゴージャスな時間のように思える。