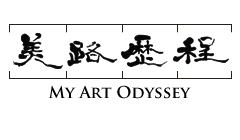

その人が暮らし活躍した町、アムステルダムはもとより、ロンドンやパリで、またベルリンやウィーン、ひいては日本の熱海市(*注)においてさえ、その筆になると言われるその人自身の姿に接してきた。レンブラントの自画像――。
17世紀、黄金期のオランダ絵画の頂点に立ち、光と影のマジックを自在に操りながら、数多くの名画をものした天才画家。油絵のみならず、エッジングや銅版画に至るまで才能を尽くした美の巨人。その人が、他のどの画家にもまして自画像を数多く描いたのである。それ自体がミステリーと言える。
レンブラントは何を思い、自らの姿にこだわり続けたのか。画家は終生、自画像を描き続けた。44年に及ぶ画家生活において、手がけた自画像は90点にものぼるという。死の年、1669年だけでも、3点の自画像が存在する。
そもそも、自画像とは何であろうか。画家は何のために自画像を描き、作品とするのか? 一般的に言って、画家が自身の像を描くのは、かくあらん、ありたしと願う自己の姿を、自らに確認もし、他人にも見せたいということが基本にあるだろう。強調したい、誇張したい自己の一面をクロースアップすることになり、それが自己陶酔や自己顕示につながる所以ともなる。
だが、レンブラントの自画像は、そういう理想像に引っ張られたような偏り、一方を向くベクトルから免れている。敢えて言うなら、彼の自画像にはすべてのベクトルが入れこまれている。酸いも甘いも、長所も短所も、誇らしき部分も弱き部分も、人間存在として自己が抱え、心の内側に巣食うすべてを見透かしてしまう、そのような鏡としての自画像なのである。
25年以上も前になるが、私自身も関わったNHK教育テレビのエルミタージュ美術館のシリーズ番組でレンブラントをとりあげた際、ゲストとして出演したヴァイオリニストの前橋汀子氏が、レニングラード音楽院留学時代、学業の合間にエルミタージュに通った思い出を語り、レンブラントの絵を見ていると、バッハの無伴奏を聞くような気がすると言われた。
宗教画も肖像画も、エルミタージュには優れたレンブラント作品が数多く所蔵されている。前橋氏がレンブラントのどの作品にバッハを感じたのか、聞き漏らしてしまったが、今にして思えば、氏の語る無伴奏ソナタや無伴奏パルティータは、何よりもレンブラントの自画像こそが似合うように感じる。
レンブラントの人生は、起伏に富んだ破天荒なものだった。浪費家で、投機に手を出して失敗もした。債務が重なり、財産没収の憂き目にも遭った。家庭的にも、多くの子が生後ほどなくして死去、妻サスキアも早世した。妻の死後、女性関係は泥沼化し、子までなしながら、家政婦のヘンドリッキアとはなかなか結婚できなかった。しかも、その彼女にも先立たれ、晩年は孤独で質素な暮らしだったという。
90点もの数があれば、自画像だけでもその画風の変化はおのずと見てとれる。まだ若い頃には、表情のデッサンのために描いたようなものや、光と影のエチュードのような作品もある。だが、やがてレンブラントの自画像は、そのような次元とは異なるところに結実するようになる。人生の蓄積が自画像を深くしたのだ。内省的な姿を粗い筆遣いで描いた晩年の自画像となると、もはや狭義の絵画を超え、文学や音楽にも押しなべて響くテーマが聞こえてくる。人生とは何か? 生きるとはどういうことなのか……?
レンブラントの自画像はまた、どこか、戻って行く世界を思わせる。波乱に満ちた私生活や、輝ける画業の成就の合間に、常にそこへ立ち戻って行く鏡のような世界である。鏡の中に自己を見つめ、心の高ぶりを抑え、自分を引っ張らんとする力の向きを知る。それで容易に行動が変わるわけでもなかろうが、せめて力のベクトルだけは見据えておかねばならない。
作品点数が多いおかげで、世界のどの代表的な美術館に行っても、レンブラントの自画像に接することができる。無論、美の世界は多様だ。様々な名画が見る者を魅了する。溜息が出るほど、ひたすらに美しい絵もよい。日常を超えた幻像の絵画も面白い。色彩が爆発したような絵にもときめきを覚える。
しかし、そういう中にあって、レンブラントの自画像の前に立つと、おのずと粛然とした気持ちになる。彼の自画像が今度は新たな「鏡」となって、おのれの存在の深いところまで覗きこむような気になる。お前は何をしているのか……自問が湧く。そしてどこからか、バッハが聞こえてくる。
*注 熱海市のMOA美術館にはレンブラント作と言われる若き日の自画像があるが、2005年に行われたレンブラント・リサーチ・プロジェクトによる調査では、工房作との評定が下された。