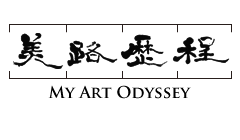

地中海沿いのリゾート地、コスタ・デル・ソルからほど近いスペインのマラガ。ピカソの生まれ故郷としても知られるこの町で、春の聖週間を見学したことがある。巨大なキリスト像と聖母マリア像を載せた2つの山車が、にぎやかな楽隊に率いられて街を練り歩く。
それぞれが成人の像であり、聖母は幼子イエスを抱いているわけでもないので、母子というより、男女のカップルのように見える。いかにも、キリストは男神、マリアは女神で、あたかも日本の雛祭りの「お内裏(だいり)様」よろしく、男女一対であることが当たり前のように感じられる。無論、それはあくまでも南ヨーロッパなどカトリック圏内での感覚には違いないが、聖母マリアがいかに人々に慕われているか、祭りの熱狂の中で如実に知らされる思いがした。
さて、先にヴェネツィアの秘宝、ティツィアーノの「聖母被昇天」について述べたが、聖書のどこにそんな記述があったかと訝しく感じた読者もいたかもしれない。そうなのだ。実はイエス・キリストの生涯――その誕生から伝道と様々な秘蹟、そして殉教の死と復活までを記した聖書が完成されてよりだいぶ後になって、その母であるマリアへの信仰が広まり、ついには教会側も聖母と崇めるための伝説や神話を追加することになった。地上での命が尽き、亡くなったマリアが、天使たちによって天に昇らされ永遠の命を得る、いわゆる聖母被昇天は、そのようにして付加された「後出し」の教義なのである。
キリスト信仰にマリア信仰が融合していった理由は、様々に説明は可能だろうが、もしイエスへの信仰だけに頑なに限っていたならば、その後のキリスト教の隆盛はなかったことは確かだろう。真実に生きようとした青年が体制から排撃され、磔刑に処せられる、厳しくも男らしいイエスの物語に、無尽の愛を注ぐ女性としてその母マリアが加わることで、人々の祈りの心に潤いや和みが生じ、峩々と聳える山に広々とした海が和すがごとく、円を描く世界へと昇華したのである。
聖母被昇天に戻ると、実は日本人にとって、意外にもこれは馴染のある画題である。かのウィーダ作「フランダースの犬」において、ネロ少年は毎日のようにアントワープ大聖堂を訪ねては、この教会に飾られたルーベンス作の「聖母被昇天」の絵を眺めたとされているからである。
結局は貧困と不如意によって野垂れ死にのように世を去るしかないのだが、ネロ少年は、波打つ金髪が肩にかかり太陽の光が額を照らすこのマリア像に、2歳の時に死別した母の面影を重ね見ていたのだった。昇天とともに永遠の命を与えられた教義上のマリアと、尊敬する大画家ルーベンスによって永遠の命を与えられた絵画の中のマリアと、少年は二重の意味での永遠の母を見ていたのだろう。
実は「フランダースの犬」の物語は、ベルギーはもとより、ヨーロッパの国々では、あまり人気がない。日本でのみ、アニメにもなるなどして、とびぬけて人々に親しまれてきたのである。ネロ少年の物語に惹かれて、アントワープ大聖堂を訪ねる日本人はひきもきらない。
ネロ少年の悲劇に対する同情心がなせる業には違いないのだが、聖母に寄せる想いへの共感が裏打ちしていることもあるだろう。それはどこか、ヨーロッパから遠く離れたマカオや長崎に聖母像があり、違和感に軋むどころか、アジア的風土の中にしっくりと溶け合い、落ち着きを見せることと、通奏低音が鳴るようなところで、軌を一にしているように感じられる。

日本がイタリアと国交を樹立して150年になるということで、2016年は美術の世界でも記念の展覧会が目白押しである。お蔭で、イタリア美術の核のひとつをなす聖母像について、集中的に鑑賞することが可能となり、改めて聖母なるものとその絵について、考える機会に恵まれた。
東京都美術館で開かれたボッティチェリ展にも足を運んだが、この展覧会と、ちょうど1年前、2015年の春に開かれた「ボッティチェリとルネサンス フィレンツェの富と美」の展覧会(東京渋谷「Bunkamuraザ・ミュージアム」)によって、ボッティチェリの描くいくつもの聖母像に接することができたのは幸いであった。
というのも、本場フィレンツェのウフィツィ美術館を訪ねた時には、ボッティチェリと言えば「プリマヴェーラ(春)」や「ヴィーナスの誕生」など、華麗でゴージャスな大傑作にどうしても目を奪われてしまって、聖母像の方にはなかなか意識が向かなかった覚えがある。それが他ならぬ日本での展覧会で、フローラやヴィーナスだけでなく、ボッティチェリが心血を注ぎ続けたひとつの核となる世界が聖母像であったことを知らされたのである。
無論、当時の社会の仕組みや教会の威光を思えば、画家として認められようと願えば、聖母像は必須のテーマであったことは疑いない。だが、ボッティチェリの聖母像には、そうした世の習いに従うとか務めを果たすといった次元を超えた、創造への強い意欲を感じる。おそらくは、対象となるのが女性だからであろう。ヴィーナスだけでない、自分は聖母像に於いても見事な女性美を描ききるといった、みなぎる意志が画面に横溢している。
聖母像は、画家にとっては決まり事や制約が多い画題のはずだ。服装も赤と青に限定される。構図にしても、とんでもない変化球が可能なわけではない。気品がなければならず、「肉」を感じさせるなど、もってのほかであろう。
だが、それゆえにこそ、画家にとっては、枠を外さず、ツボを押さえつつ、その上で個性を吹き込むチャレンジングな領域であったに違いない。制約を受けつつも、画家が精魂を傾けて描き出す聖母は、外見的にも内面的にも、とびきり美しくなければならないのだ。
先に「聖母被昇天」に関して、聖母が「後出し」のように聖人化し、昇天させられた旨を述べた。被昇天に限らない。聖母を描く際には、決まってこの「後出し」に似た時系列を超えた視点が介入してくる。聖母は幼子イエスとともにあって、本来はその時点では知るはずもないわが子の未来の受難の運命を、既に予知しているかのような悲しみや憂いを湛えていなければならないのだ。ボッティチェリの聖母も、しばしば伏し目がちな表情の中に清らな憂愁を湛えている。
2016年のイタリア・イヤーの幕開けを告げるように始まった東京都美術館でのボッティチェリ展の目玉は、「書物の聖母」と呼ばれる聖母子像であったが、これが期待にそぐわぬ傑作であった。憂いを湛えた眼差しや面差しに清潔な透明感を醸し出しつつ、後光の輪や聖母の溢れる金髪など金の使い方や花のあしらいが、華やかさを演出もする。
ボッティチェリという画家は、本質的にはやはりヴィーナスやフローラなど、華麗な春の花を思わせる美神像に卓越した才を発揮する画家だと思う。その彼の特質は、聖母を描くにも生き生きと発揮されている。宗教画として許されるぎりぎりのところまで華やぎに装い、神聖にして艶やかな独自の女性美を創出しているのだ。

聖母像との出会いの中で、忘れがたい強烈な感動の体験がある。それは意外にもイタリアではなく、「北のヴェニス(ヴェネツィア)」と呼ばれるロシアのサンクト・ペテルブルクでのことだった。もとはロマノフ王朝の冬の宮殿であったエルミタージュ美術館で、ダ・ヴィンチ作の聖母像に打ちのめされたのである。
多くの名画を収蔵するエルミタージュ美術館だが、その展示室に足を踏み入れ、聖母像が近づいてきた瞬間の胸の高鳴りが忘れられない。私が訪ねたのはまだソ連時代で、町の名もレニングラードと呼ばれていたが、鎌と槌に象徴される厳しさ、いかめしさが跋扈する空気にあって、「エルミタージュ(隠れ家)」の名の通り、息をひそめそっと生き続けてきた宝物に出会うかのようなときめきを感じた。
エルミタージュには、ダ・ヴィンチ作の聖母像が2点あるのだが、まず目を射抜いたのは、「ブノワの聖母」と呼ばれる一点であった。掛け値なしに言えば、美しいの何のと言う前に、その絵の聖母の、あまりに他の聖母像とかけ離れた姿に、衝撃を覚えた。
まず、この絵の聖母はいたって若い。幼げな印象さえ残している。少女のようなその若き母が、膝に抱えたわが子(イエス)に、無邪気に微笑みかけている。その微笑みがまた、教会のしかるべき場所に威厳をもって飾られるように装われたものとはおよそ違う、町の井戸端にでも見かけそうな、市井の只中に咲いた人間臭い笑みなのである。とはいえ、笑みが下品なわけでは少しもない。母と子の間には純粋な愛があるばかりで、たとえ雑踏や陋巷に見つけた母子であったとしても、無垢な愛に満ちた微笑みには、神々しさが輝いている。
幼子イエスの未来の殉教を匂わせる小道具(十字架を象徴するという白い花など)は用意されているものの、ダ・ヴィンチにとって聖母子の聖なるゆえんは、そのような次元にはなかったように思われる。
もう一点の「リッタの聖母」は、弟子の手がかなり入っているとも言われるが、「ブノワの聖母」とは対照的な仕上がりだ。聖母はやさしさと憂いをともに漂わせてはいるものの、「ブノワ」のような人臭さは敢て排除されており、超然的で玲瓏とした美しさに輝いている。均整がとれた(とれすぎた)構図も相まって、どこか幻想味をも醸し、遥かに時代が下ったポール・デルヴォーのシュールレアリスム絵画の裸の美神さえも思わせる。
北の果てのエルミタージュに残る聖母像を見ただけでも、「神の手を持つ」と言われたダ・ヴィンチの天才ぶりは如実に伝わってくる。
そして2016年早春、ボッティチェリの聖母と妍を競うように江戸東京博物館で展示されたダ・ヴィンチの「糸巻きの聖母」――。久しぶりに目にするダ・ヴィンチの聖母像であったが、実に見ごたえがあり、堪能した。
「ブノワの聖母」は1475から78年頃の作、「糸巻きの聖母」は1501年頃の作と言われるので、両者の間には四半世紀の歳月の経過がある。聖母像の常識に反旗を翻すかのように、ことさら人間臭い母子の愛を描いた若き日の「ブノワ」に比べ、50歳になる「糸巻き」では落ち着きの中に揺るぎない円熟が見てとれる。
「糸巻きの聖母」を目にして誰もがまず気づくのは、幼子イエスが母の方を向かず、その眼差しが反対方向、糸巻き棒へと注がれていることだ。それゆえ、幼子の体全体の動きがダイナミズムを生じ、緊張を生む。母に向き合わず、十字架に似た糸巻き棒を見やるのは、後の受難の運命を象徴していることはもちろんだが、一方では、おしなべて子というものがやがては母のもとを離れ、巣立ってゆくことを暗示しているようにも思える。
幼子を見つめる聖母の眼差しは、静かな諦観の中にほのかな憂いを浮かべ、その意味では伝統を踏まえている。だが、絵を統べる力学が収斂する意外なポイントは、聖母の右手にある。気功師のかざす掌さながら、幼子の背後から一定の距離をとって置かれた掌――聖母の地味な衣装から浮き出たこの掌に、幼子に寄せる母の想いのすべてが込められている。
会場では、「モナリザ」につながるスフマート(ぼかし技法)が強調されていたが、私はこの聖母の右手に釘づけになり、そこから絵の全体に目を広げた時に、自分なりにダ・ヴィンチの聖母像との真の出会いをもてた気がした。
その聖母像は、柔らかく、静謐かつ穏やかで、しかも神々しい。キリストの母であるがゆえに神々しいのではない。子を思う母の永遠の愛のゆえに、神々しいのだ。ダ・ヴィンチという天才の人間を見つめる深い眼差しが、子を愛する母を清め、聖母像の神々しさに結晶させたのである。

聖母像との私的な出会いを語るに、もうひとつ、思い出深い場所がある。ハプスブルクの古都、ウィーン。エルミタージュを訪ねるよりも前のことだったが、この町の美術史美術館を初めて訪ねた際に、ラファエロの描いた聖母像に恍惚となった。
「牧場(草原)の聖母」――。構図、色彩はもとより、人物の姿、表情など、どのように見ても、瑕瑾のない実に美しい絵である。背景の風景やところどころに配された草や花も含めて、すべてが調和と均整の中にあり、その完璧さに唸らされる。
聖母と言えばラファエロと言われるほどに、彼の描く聖母像の美しさには定評がある。ルネサンス絵画の美の規範を確立したとも言われる。ウィーンで「牧場の聖母」に出会わなかったら、その後、聖母に注目する私の眼は育たなかったかもしれない。
パリでもベルリンでもロンドンでも、ラファエロの描く聖母像には、特別なものを見る気持ちで接してきた。もちろん、私の好みもあって、それらのすべてがウィーンでの出会いのような濃密な陶酔を与えてくれる訳ではなかったが、中に1点、衝撃という点ではウィーンをしのぐ聖母像に出会った。フィレンツェのピッティ美術館が所蔵する「小椅子の聖母」がそれである。
この絵には、2つの異なるエピソードが付随する。1つは、画家が道で見かけた仲睦まじい母子の姿に感銘、その場でワイン樽の蓋にスケッチしたというもので、名もなき市井の母子が聖母子像に発展したことを物語る。そしてもうひとつの逸話は、画家の愛人と彼女との間に生まれた子がモデルになったというもので、こんな噂が人々の口にのぼってしまっては、聖母への冒涜として、画家の立場が危うくなることはなかったのかと、余計な心配をしてしまう。
どちらにしても、そのような逸話の尾ひれが付きまとうこと自体、この絵が持つ本質を端なくも語っていると言える。すなわち、誰の目にも明らかながら、この絵の聖母は憂いに沈み、目を伏せてはいない。幼子イエスを腕に抱きつつ、視線はきりりとこちら側、絵を見る私たちの方に向いている。
おっと、こういう目線は、ヴィーナスのものだったのではないかと、一瞬、たじろいでしまう。そうだ。この聖母は、あまりにも女なのだ。ありきたりの聖母像を完全に超えている。その衣装や装飾も、艶やかな印象を与える。それでいて、もちろん、この絵には人を惑わせるようなところは微塵もない。聖母は聖母然としていなくとも、やはり神々しいまでに美しい。
「聖母の画家」が描いた数ある聖母像のうち、おそらく人気ナンバーワンはこの絵なのではないだろうか。かくいう私も、ラファエロの聖母に惹かれるきっかけはウィーンの「牧場の聖母」であったものの、今では彼の聖母像として一押しは、この「小椅子の聖母」なのだ。
元来、聖母とヴィーナスとは、対立する概念としてとらえられてきたはずだった。「肉」を伴う愛の女神が、「肉」を離れた聖母と重なり得るはずもなかった。だが、ラファエロという鬼才によって、女性を描く高み、極みに於いて、表も裏もない、統合した女性として止揚したのだと、そう思いたい。
聖母像をめぐる私の想念は、再び、マラガで見かけた聖週間の山車へと戻ってゆく。イエスとカップルかと見まがえた女神としてのマリアである。聖母像は、まさにキリストの母としての神聖で厳格な姿と、理想の美しき女神の間を揺れている。悲しみも、やさしさも、艶やかさも、愛おしさも、女性ならではの特質が、すべからくぬくもりとともに息づいている。
多くの日本人同様、聖母像に接するに、私個人としては信仰の対象とする感覚が抜けている。聖母像を前に、頭を垂れ、ひざまずき、掌を合わせ、十字を切る、そういった「常識」を免れている。だからこそ、その美術としての魅力が百パーセントに、ストレートに迫ってくる。
イタリア・イヤーということで、多くの聖母像が日本に上陸する。純粋アートとしての聖母像を考えるには、意外にも、日本という土地空間は、恵まれた場所であるのかもしれない。