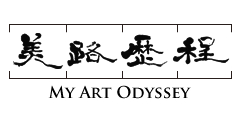

福島繁太郎(1895~1960)の著書『エコール・ド・パリ』(1948~1951 全3巻)を読んでいる。70年以上も前に出た本だが、古さを感じさせない。単に美術コレクター、美術評論家というだけでなく、1920年代を中心に、実際にパリのアートシーンの渦中に身を置き、時代の先端を行く画家たちの作品、そして画家本人たちと接してきた人の筆になるだけに、活き活きとした魅力に溢れている。
福島は初めから画商だったわけではない。東京帝国大学法学部を卒業後、1921年、英国に渡った。法律学を学ぶためだったという。だが、現地で次第に美術鑑賞の面白さに目覚め、23年にはフランスに居を移した。コレクターとして美術収集に精を出すのみならず、私財を投じて『フォルム』というフランス語による美術専門誌を発行、斯界での存在感を高めた。
当時のパリは、エコール・ド・パリの全盛期。フランス人のみならず、世界各地から才能溢れる気鋭の画家たちがパリに集まった。第1次世界大戦後のこの時期、パリは文字通り芸術の都、輝ける世界の中心地だった。
福島が現地で出会った画家たちのうち、とりわけ懇意にしたのは、マティス、ルオー、ドランだった。慶子夫人も含め、家族ぐるみの付き合いで親交を重ねた。
福島の著書『エコール・ド・パリ』は、太平洋戦争後、まだ日本が連合国軍の占領下にあった時代に発行された本だが、図版の掲載も処々にあって、ヴィジュアル面にも気を遣った編集になっている。多くはモノクロだが、中にはカラー写真による作品紹介もある。
マティスに関して言うと、マティスの章を設けた第1巻に、3点のカラー図版が載る。印刷技術がまだ発達していない時代なので、写真そのものは、現代のものに比べると見劣りするが、そのハンディを超えて俄然輝く1点がある。
『若い水夫 Ⅱ』(1906)――。現在はニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵するが、福島の本では『水夫』と題されている。先にあげた『ダンス』同様、まだ福島が渡欧する前、若き日のマティスが、これぞフォービズムだ、と言わんばかりの勢いで描きあげた作品である。
福島は綴る。「この一九〇六年の作品に於て、色彩のハルモニーに重きを置いて、実物とは異る色彩をつけている事は、ゴーギャンの教えに依るが、之を更に一層大胆に行っているのである。ことに眼や口を緑色で描いた事は、全く人を驚かした。大きな部分を明暗なくあっさりと塗り潰し、深き蔭を太い線をもって示すのは浮世絵版画より示唆を受けたものと思われる」(『エコール・ド・パリ 1』)――。
西洋美術史にあってマティスがどれほどに革命家であるか、福島は明確な定見をもっていた。同時に、その本領がフォービズムのみに留まるものでないことも熟知していた。
「しかし、なんと云ってもマチスは素描家であるより、カラリストである所に天賦の才能がある。マチスの用いる、目の覚める様な緑や青、人の意表に出ずるピンク色も、普通の絵具のチュウブから絞り出したものに過ぎず、何等特別製と云う訳ではない。多くの画家や画学生も之を用いている。しかもマチスが、一度之を駆使すると俄然新鮮な活気を持ってくる。と云うのは、マチスが色の取合せに特別な才能を持っているからである」――。
美術への情熱が嵩じた福島は、やがて美術品の購入、収集に手を染める。パリで初めて購入した作品はドランであったというが、次に買ったのがマティスの『パイナップルのある静物』という絵であった。
マティスとの関係においては記念碑的な作品になるわけだが、福島は一度は手に入れたこの絵を、日本に持ち帰る前に手放してしまっており、本人も後悔することになる。
今では、ワシントンのナショナル・ギャラリー・オブ・アートが所蔵するこの作品は、マティスが1917年以降、しばしば訪ね、居住し、制作の拠点とした南仏ニースで描かれ、燦たる光に溢れ、種々の色彩が明るいハーモニーを奏でている。
南国の果実であるパイナップルがそこに置かれていることに、何の違和感もない。背景に置かれた屏風を彩る花柄など、欣喜雀躍して、今にも踊りだしそうだ。
福島繁太郎がフランスに滞在したのは、1923年から1933年までだが、この間のマティスはいわゆる「ニース時代」を生きており、先の『パイナップルのある静物』がそうであったように、初期のフォービズムを脱して、光と色彩に溢れた室内画や人物画、風景画など、旺盛な制作活動を続けていた。
「一九一七年になって、マチスは南フランスのニースに移り、年の大部分をここに過す様になった。光の麗かな南フランスとの接触はマチスの色彩を益々明るくした。カラリストとしての天分は十分に磨きがかけられ、彼の造型法も特色を発揮して、マチスの芸術は其の完成期にはいってくる。 マチスは南フランスの風光に魅されて、自然の呼びかけに戻ってきた。この時代より一九三〇年頃迄が、彼のあらゆる時代を通じて最も自然に接近した時代である」――。
この時代、テーマとして多く描かれたのは、イスラム世界でスルタンに仕えた後宮の女性、「オダリスク」だった。
1912年から13年、2度にわたって訪ねたモロッコ体験が影響していることは疑いの余地もないが、マティスの「オダリスク」はアラベスクへの憧憬にヌードの女性像が融合した独自の世界で、西洋人のモデルにアラビア風の衣装をつけさせて描くのが常であった。
多くの「オダリスク」が描かれたが、その最初の作品が、東京都美術館で開かれたマティス展に出品されている。『赤いキュロットのオダリスク』(1921 ポンピドゥー・センター)がそれだ。
赤一色に塗られた床、背景に置いた2点の衝立の青と黄の色と紋様、ピンクの花を活けた花瓶、横たわる女性のキュロットやベール、そしてベッド……。どれもがいかにもマティス好みの空間構成をなし、その中心に白肌の女性の肉体がある。それぞれの構成要素は饒舌な筈だが、全体として見ると、落ち着いたハーモニーがある。
この時期、マティスのお気に入りのモデルは、アンリエット・ダリカレルだった。もとはバレーダンサー兼バイオリニストだったというダリカレルは、1920年からマティスの絵に登場し、1927年に結婚するまで、モデルをつとめた。この女性がミューズとなったればこそ、マティスは「オダリスク」のイメージを借りながら、次々と理想の女性像を描くことができたのである。
ダリカレルは音楽をたしなむ女性だったので、マティスの作品にも、音楽に関係する素材が増加した。福島がコレクションしたマティス作品の中にも、ダリカレルをモデルに、音楽に絡めて描いたものがある。
『黄衣の婦人』(1923)――。楽譜を手に画面中央に座る、鮮やかな黄色のドレスを着た女性。背景にも足元にも、例によってアラベスク模様が広がる。奥のテーブルには赤いテーブルクロスがかけられ、花々を活けた花瓶が載る。テーブルの右端の足元には、女性が弾くのであろう、ギターが立てかけられている。
室内ではあっても、ふんだんな光を受けて、画面全体がなんとも明るい。この部屋に踊る色彩の数は、いかほどになろうか。あらゆる色を統合し、リードするかのように、女性が身につけた黄色いドレスが君臨する。
着衣の女性ではあるが、これも「オダリスク」の延長なのであろう。女性は部屋(空間)と一体化し、光と色彩の化身であるかのように、女王然と白日夢を生きている。
福島繁太郎の『エコール・ド・パリ』は、美術評論家としての彼の炯眼を示してあまりないが、読み物として見た場合、魅力的なアクセントを添えているのが、処々に挟まれた慶子夫人の手記である。
マティスに関しては、「ニースのマチス」と題して、彼女が接した画家の素顔を紹介しているが、これが作品からだけではわからない、マティスの人となりを活写していて興味深い。
福島夫妻が初めてマティスに会ったのは、1925年、ピアニストのジル・マルシェックスに連れられてパリ郊外の画家の家を訪ねた折であったというが、この時はまだフランス語も満足にできず、深い親交には至らなかった。
慶子夫人は体が弱かったため、夫妻は冬になるとあたたかな南仏を訪ねるようになり、初対面から数年後には、ニースでマティスと再会を果たす。マティスはこの日本人夫妻をよく覚えていて、家の隅々を案内するなどして厚遇した。
1930年の正月を夫妻はニースで迎えたが、繁太郎が仕事でパリに戻った後も、慶子夫人ひとりニースに残って静養を続ける。その間――2カ月近くの間に、週1度ほどの頻度でマティスのもとを訪ねた。
そうした画家とのじかの触れ合いから書かれた慶子夫人の手記は、芸術家の身辺を覗くようなエピソードや証言に満ち、マティス・ファンからすればまさに宝の山である。手記が明かすマティスの創作の秘密を、いくつか拾ってみよう。
マティスは、モデルの身に着ける衣装や首飾りなどの小道具を、彼自身で縫ったりつないだりすることを明かす。驚く慶子夫人に、「なんでもないですよ、モデルは動かないから要所要所を止めておけばそれで間に合うのですから」と述べたマティスは、なおも「オダリスク」の袴の作り方や上着の飾り方などを得意げに語ったという。
色彩について鋭い感覚を持つマティスは、気に入った色のついたものであれば、色紙や貝殻、東洋製の腕輪、その他、コンフェッティの綿玉に至るまで、ありとあらゆる雑多なものを、部屋の壁に釘やピンでとめておいた。
また、デッサン画も多く見せてもらったが、1枚の油絵を描くには、その前に、鉛筆でのデッサンを5、60枚は描くという用意周到さであったという。
マティスは『ヨーロッパの牛』という大作に取り組んでいたが、まだデッサンの段階で、絵の方は一向に仕上がらず、訪問のたびに構図を変えていたという。
さて、慶子夫人の手記に登場したマティスの具体的な作品名はこの『ヨーロッパの牛』だけなのだが、同名タイトルの作品は残されておらず、これがその後どうなったのか、よくわからない。
ただ、タイトルから類推して、ゼウスがフェニキアの王女エウロペを牛に化けてさらったというギリシャ神話に登場する逸話を描こうとしていたのではないかと思い、探したところ、果たして、1929年の作になる『エウロペの略奪』(The abduction of Europa)という絵画が、オーストラリア国立美術館に所蔵されていた 。
マティスにしては珍しい神話的テーマを扱ったこの作品は、油絵なのだが、一見して水彩画と見まがうほどに、色が薄く、線がたっている。デッサンを繰り返してなかなか絵にならなかったと慶子夫人の証言にあるが、あるいはそうした事情が窺われる出来映えなのかもしれない。
ただ、テーマ的には「オダリスク」に通ずるところがあり、画面中央に横たわる女性は、アラベスク模様とは無縁ながら、充分に印象的だ。かつ、その横に控える牛の表情が、なんともよい。マティス自身を含めた世の男たちの愚かさ、哀しさを物語って余りある。
マティスはまた、慶子夫人に絵を描くかを尋ね、さらには彫刻をするようにと熱心に勧めた。「絵を描くという事は、先ず正確なデッサンをとれる腕を作らなければならない。之は科学的のもので
慶子夫人なりに顔の彫刻を仕上げて次の訪問時に持参すると、マティスは笑いながらダメ出しをして、適宜説明を加えながら、彫刻を直してくれた。「頬ペタには目の下にホラ、ここに筋肉がある。もう一つはソレ、ここにあるだろう、あなたがお化粧する所だ、それから下の方にもう一つのが此処からこう走っているのです」――。
マティスはアトリエにいる時以外にも、始終ポケットに小さな粘土彫刻を入れており、家族との雑談の折にも、手なぐさみとしていたという。
慶子夫人に彫刻を勧めたのは、絵の腕を磨くためのレッスンとしてであったが、マティスという画家は本来、絵画制作と同時に、彫刻作品も手がけた人だった。
『アンリエット Ⅲ』は、1929年の作になる彫刻。絵画作品のモデルをつとめたアンリエット・ダリカレルを使って、マティスは1925年、27年と彫刻を作ってきた(『アンリエット Ⅰ』『アンリエット Ⅱ』)が、これは彼女をモデルにした一連の彫刻作品の最後となるものである。
アトリエを案内された折になど、慶子夫人もきっと目にした作品に違いない。高く張った頬骨や口元の引き締まった筋肉など、慶子夫人の手になる彫刻を直しながら語ったマティスの言葉を思い返しながら鑑賞すると面白い。マティスの言葉が、そのまま彼の手になる彫刻にも重なる気がする。
彫刻を直してもらったその日、慶子夫人がマティス宅を出た時には、強い風が強いていた。しばらく歩き進むと、大声を出しながらマティスが後を追ってきた。風が強いので車で送ろうと言い、いったんはふたりでマティス宅に歩いて戻り、それから彼の自家用車で夫人の宿まで送ってくれたという。
マティスの気さくな態度が微笑ましいが、さりげなく語られた逸話の中にも、巨匠の素顔が覗き、人となりが息づいている。
慶子夫人は(彫刻はともかく!)、文章を綴ることに関しては並々ならぬ才気の持ち主であり、彼女の筆にかかると、初老の大芸術家が、血の通った人間として、何かとても愛らしく浮かび上がってくる。その言葉、行いの逐一が、やっぱりマティスだなあという、妙な納得感とともに腹に収まるのである。
さて、福島繁太郎が集めたコレクションのうち、日本に残るマティスの作品はないのだろうか――。
12年に及んだ滞欧生活を経て、1933年に福島が帰国した際、80点の美術作品が日本に持ち込まれている。もともとは150点もの作品のコレクションがあったというが、ヨーロッパに残してきたものや、帰国前に売却したものもあって、半数近くに減ったものらしい。
福島コレクションは、やはりヨーロッパで美術作品の購入、収集にあたった松方幸次郎のコレクションが後に国立西洋美術館に収められたのとは違って、一か所にまとめて収蔵されることがなかったため、散逸、分散が激しく、今では後追いが困難を伴う。
それでも、福島がコレクションした作品を可能な限り集めた「旧福島コレクション展覧会」が、1955年に東京のブリジストン美術館と倉敷の大原美術館で開かれ、その後、『旧福島コレクション』という図版入りの本になって出版された(1955 美術出版社)お陰で、本に載る写真と照合することで、ある程度の割り出しが可能となる。なお、この時の図版では、日本に持ち込まれたマティス作品として、7点が紹介されている。
結果として、少なくとも以下の2点の絵が、今もなお日本に存在することが判明した。ともに、アーティゾン美術館(旧ブリジストン美術館)が所蔵している。
『両腕をあげたオダリスク』(1921)――。福島はこれを『オダリスクⅡ』と名づけていた(もう1点、別に『オダリスク』を所蔵していたため)。野性的な逞しさを感じさせる女性のヌードもさることながら、背景に描かれた模様、色彩が、ともに強い印象を放つ。
この、一見して
個人的な印象になるが、髪を布で巻いているせいもあって、私の目には女性が東洋人、日本人女性に近いようにも感じられる。極端なたとえに聞こえるだろうが、
日本にあるもう1点は、『石膏のある静物』(1927)――。福島はこれを『赤い静物』と名づけていたが、なるほど、全体として、マティスならではの赤色の印象が際立つ。福島がマティス作品としては最初に買い求めた『パイナップルのある静物』と同様、パリのベルネーム・ジュール画廊で開かれた近作展覧会で購入したという。
マティスは静物画も描く人だった。この絵など、明らかにセザンヌの影響もあるのだろうが、テーブルの上に置かれた果物に眼差しを向ける、その視野をぐっと広げて、室内画とでもいうか、光に溢れた部屋のあちこちに置かれたさまざまなオブジェの、それぞれの色彩による自己主張をとらえつつ、全体としてひとつのハーモニーを奏でるように仕立てるさまが、いかにもマティスらしい。この画家の本領が発揮された傑作と言えるだろう。
松方コレクションにしても然りだが、日本人コレクターが欧州まで出かけて行くと、斯界に通じた専門家のアドバイスを得て、既に評価の定まった作品を購入するケースが多い。その場合、作品は時代的に少し前に生まれたものに限られる。
だが、福島コレクションの凄いところは、まさに時代の渦中にわが身を置いて、常にアップ・トゥー・デイトな作品を求めた点である。現在進行形のアート最前線に息づく活きのよい作品を、自分の目で確かめ、チョイスした結果のコレクションなのである。
時の経過によって、散逸、分散の運命を免れなかったことは残念だが、それでも、時代の息吹に溢れたマティス作品が、なおも2点、日本に残っていることを嘉としたい。
これらの作品が、マティスの画業の一里塚であることはもちろんだが、パリの異邦人として画家本人とも親しく交わった福島繁太郎・慶子夫妻の生の足跡でもあることを、長く記憶にとどめたく思うのである。