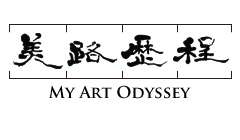

コロナで美術館に行けなかった数カ月の間、この騒ぎが収まったら、どの絵画作品を見たいかと考えた。パリのルーブルを始め、ウィーンの美術史美術館、ロンドンのナショナル・ギャラリーなど、世界を代表する美術館を再訪し、思う存分美術を堪能したいという気持ちは、憂鬱に沈みがちな心をもちあげてくれる気がした。
しかし、今何を見たいかという希望は、やはりコロナの影響を受ける。多くの人命が喪われ、なおも終息の目途は立たず、地球上のあちこちで非寛容の
そして定まったのが、この作品。私の選んだポスト・コロナの1点は、オディロン・ルドン(1840~1916)の『目を閉じて』であった。
セーヌ河畔のオルセー美術館を初めて訪れ、ルドンの展示室に足を踏み入れた時の衝撃は、今なお忘れがたい。きら星のように輝く印象派の名作に接して手ごたえを覚えた後に、その部屋に入ると、全く違った宇宙が開け、しばらくは方向感覚を失ったような戸惑いに立ちすくんだ。目が次第に慣れてくるにつれ、バッハのコラールでも聴くような静かな熱さが心にひろがってきた。
自然界に溢れる光と色彩をどう画布に移すか、何よりもそのことに腐心した印象派の画家たちの作品に対し、ルドンはあくまでも人間存在の内面から輝く光にこだわった。外に向けて意識が開かれた絵と、ひたすら内側に向かって沈潜し意味を問い続けた絵。時代としては前者の全盛なのだが、世の流行りには目もくれず、ルドンは独自の道を極め、孤高の境地を切り開いた。
オルセーのルドン展示室では、誰もが何がしかの哲学や思想を感じるであろう。絵が湛える深い精神性に魂を揺さぶられもするだろう。日本人なら、『仏陀』という絵に驚かされもしよう。東西の差を止揚し、キリスト教を超え仏教とも融和しようとする姿勢は明らかで、特定の宗教を超越した宗教性は、ルドンが終生希求してやまないものだった。
『目を閉じて』もオルセーが所蔵するルドン作品のひとつ。画家50歳、1890年の作である。一見して穏やかで、瞑想的な雰囲気に満ちている。水の広がりの彼方に、目を閉じた女性の胸像が浮く。女性と書いたが実はかなりユニセックス的で、イエス・キリストのようでもある。
目を閉じているのは、もとより単なる眠りとは違うが、生きているのか死んでいるのか、生死の境が崩れて、行き来自由になったようなところがある。死者の苦しみ哀しみを、生者が共感をもってその胸に引き取り、互いの魂の間にこだまを交わしながら、祈りに昇華させている。
前半生、ルドンは孤独だった。1880年、40歳で結婚。1886年には長男ジャンが誕生し、喜んだのも束の間、半年後には赤ん坊が死んでしまう。1889年になって次男のアリが生まれ、その幸福のなか、『目を閉じて』が描かれたという。長男の死を受けとめつつ、次男誕生の喜びを噛みしめたのだろう。
ルドンは目に独特のこだわりがあった。画業に手を染めて最初の20年間、敢えて色を用いずモノクロの暗いトーンのなかに怪奇幻想を紡ぎ続けた。ゲゲゲの鬼太郎もびっくりというような一つ目のイメージを繰り返し描きもした。世の偽りを見据えるように、白黒の眼球は宙に浮き、
闇を突き詰めた先にようやく見つけた色のある世界。まだ色は薄く淡く、キャンバス地も露わなほどだが、手前の水の広がりには確信的な強い光が射している。静謐のなか、祈りが熟し、熱を帯びてくる。啓示を待つような、ルドン特有の魂のエクスタシーがじわじわと胸に迫る。
実は日本にも、ルドンの「故郷」がある。岐阜県立美術館――。所蔵絵画のうち、西洋美術は意識的にルドンを軸に集められ、ルドン関連作品は250点を超える。『目を閉じて』というタイトルの、別バージョンの油彩画もある。1900年代に入って描かれた絵なので、オリジナルのものに比べ格段に色彩に富んでいる。
私の選んだポスト・コロナの1点の別バージョンがこの日本にあるのだ。東西の垣根を超えようとした人だったので、画家本人も喜んでいるであろう。パリに飛ぶ前に、まずは岐阜を訪ねるかと、秘かに想を練っている。